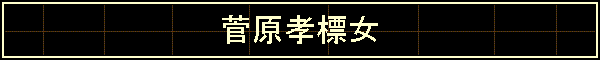菅原孝標の二女(?)。母は藤原倫寧女。道綱母は伯母。
寛弘五(1008)年の出生とされている。
10歳のとき、父孝標が上総介となり任国に同行。文学好きの継母や姉の影響で、物語の世界に憧れを持つようになる。13歳で帰京。
32歳のとき、祐子内親王(後朱雀天皇皇女)家に出仕するが、まもなく結婚。夫の橘俊通との間には子も生まれ、その後も気ままな宮仕えを続けていたらしい。が、現実への不満からか、過去の不信心を悔いたものか、38歳ころから物詣でにいそしむようになる。
天喜六(1058)年、51歳で夫と死別、「更級日記」の執筆を行ったとみられている。
ここに着目!
 | “夢見る少女”は実像か |
「光源氏などのやうにおはせむ人を、年に一たびにても通はしたてまつりて、浮舟の女君のやうに山里に隠し据ゑられて、花紅葉月雪をながめて、いと心ぼそげにて、めでたからむ御文などを時々待ち見などこそせめ」という一文は、更級日記の中でも有名なくだりとして、いつも引き合いに出される箇所である。孝標女は、ことあるごとにこうした夢想を繰り返していたらしい。それが、物語ばかり読んでいた少女期の記述と重なって、孝標女という人は若いころは夢見がちであったのが、年を経て夢想を打ち砕かれ、最後には老残の身となったのだというような考え方がなされてきた。しかし、本当にそうなのだろうかと思わずにいられない。女なら、多かれ少なかれこうしたことを考える時期があるはずだ。たとえばあの紫式部なども、日記には書いていないけれども、若いころは物語に夢中になっていたくちではないだろうか。物語の女君になったつもりで、「わたしなら、ここでこうするわ」などと、既存の物語を勝手に書き換えたり、それが高じて物語の習作を書くようになったりという経緯があったとしても、不思議はあるまい。孝標女だけが、特別浪漫的な性格だとは言い切れないのである。
加えて孝標女は、上総から帰京して早々、厳しい現実を突きつけられる場面が幾度となく訪れている。
慕っていた継母の、父との離別。帰京した直後、継母が孝標や孝標女の実母と三条の邸に同居していたかどうかは明らかでないが、継母にしてみれば同居はむろんのこと、別に住むということもまた、孝標女の実母に正妻の地位を譲ったようで屈辱以外の何物でもなかっただろう。男女の仲が、物語にあるようなきれいごとだけでは済まされないということを、孝標女は十三歳にして目の当たりにしたはずである。
そして疱瘡の流行。三年後の自宅の焼失。世相の悪いことに加えて、17歳のときには姉が死に、幼児と乳児の姪たちが残された。孝標女たちの母は健在であったにもかかわらず、古風な女で、しかも頼りなかったのだろうか。孝標女は未婚で出産の経験もないというのに、二人を自分の左右に寝かせるなどして、みずから育てていたらしい。孝標女の母が出家してからも、孝標は家に後妻を入れることもせず、孝標女を一家の主婦として家事を任せていたのである。母の出家は孝標女が29歳のころだが、実際にはもっと前から一家を切り盛りしていたのではあるまいか。女房なども、おそらく大勢いたわけではないだろうから、自然と孝標女が主婦になってしまったのだろう。
そうした状況にあって、孝標女が夢想と現実の区別を付けていないとか、あるいはいつまでもかなう見込みのない夢を抱いていたとかいう日記の記述は、信じるにあたらない。意外にしっかりとした、地に足が付いた人だったという気がする。孝標女の物語耽溺は、主人公と一体化することから始まったが、次第に差異を感じるようになっていたのではあるまいか。同じ常陸介の娘でありながら、浮舟のように身分高い男に愛されることもなく、平凡な生涯を終えてしまいそうな自分を、もう一人の自分が見つめていたのかもしれない。物語への憧れも捨てきれず、夫や子どもたちとの生活にも心底からは満足できず、出家して仏道修行に専念することもできない。支えを持たない中途半端な彼女の心を慰めることができたのは、結局日記を書くという作業だったのだろうか。 |