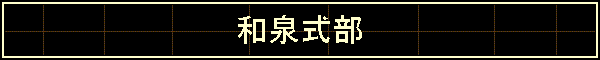大江雅致女。母は平保衡女で、昌子内親王の乳母である介内侍と言われるが疑問。
貞元元(976)年ころの出生と考えられている。父母ともに昌子内親王に仕えていたことから、童女のころから昌子内親王の女房として内親王邸にて成長したものと思われる。
はじめ橘道貞と結婚して一女小式部内侍を生んだが破綻、冷泉天皇皇子為尊親王、次いで弟の敦道親王と熱烈な恋愛をしたことは有名。両親王とも死別した後、道長女藤原彰子に仕え、紫式部や赤染衛門の同僚となる。30歳を過ぎて藤原保昌と再婚したが結局離婚したらしく、小式部内侍にも先立たれた。晩年の足跡は明らかでない。
ここに着目!
 | 和泉式部と紫式部 |
紫式部は和泉式部を評して「けしからぬ」ところがあると言ったが、それは男癖が悪いということだろうか。ためしに和泉式部と噂のあった男性を日記や歌集などから拾ってみると、夫となった橘道貞と藤原保昌、それに為尊親王と敦道親王のほかにも源俊賢、源雅通、源頼信、藤原頼宗、道命阿闍梨などがいる。名前を明記していないだけで、実際にはもっと多くの男性と交渉があったと思われる。
が、だからと言って和泉式部ひとりが浮かれ女などと呼ばれる理由はないはずである。女性が複数の男性と付き合うことは別段咎められることではなかったし、夫以外の男性を通わせるのも自由である。清少納言や赤染衛門も、女房として働きながら、複数の男性との恋を楽しんだ。しかし、彼女たちは浮かれ女とは呼ばれなかった。
一つに、和泉式部が為尊・敦道親王をめぐって騒ぎを起こしたとき、まだ宮仕えする身ではなかったことがあるかもしれない。最初の夫との不仲の原因は必ずしも為尊・敦道親王との交渉のせいではないと言われているから、すでに道貞は通って来なくなっていたとも考えられる。当時の和泉式部は、父の邸でひっそりと暮らすバツイチの女だった。父の雅致もいちおう受領階級ではあるが、系図もはっきりしないこと、歌人としての名声もないことから、紫式部や清少納言の父より社会的地位は低かったのだろう。そういう家の女がいきなり皇位継承権のある男性二人と熱愛というのであるから、世間の噂になるのは当たり前である。もし、和泉式部が宮仕えする女性であれば、世間ももう少し穏やかな反応をしたのではないか。娘の小式部内侍もなかなか派手な恋愛をしていて、公任の子定頼と道長の子教通の二人と付き合った上、教通の子を生み、後に藤原公成の子も生んでいる。いずれも上流の公達だが、母ほど非難されているわけではない。やはり女房は職掌柄男性と会う機会も多く、恋愛は大目に見られていたのだろう。その点、和泉式部は許されなかったのである。
もう一つは、和泉式部の性分によるものと思われる。本人が意識していたかどうかはわからないが、和泉式部という人は恋しないでは生きていけない部分を持っていたようだ。それでも、本人が魅力的でないと現実に男性が現れることはないのだが、式部はふっくらと肥えて、色白で髪も美しい、当世風美人だったに違いない。それに歌才もあるとなれば、男が放っておかない。男が大勢寄ってくるから、敦道親王にしてみれば不安になる。不安になると、本気になる。親王が中流階級の女性を家に連れ帰って召人にするというのは、さして珍しい事件とは思えないのだが、身分高い男の方が真剣になってしまうと、騒ぎは大きくなる。親王と式部が祭見物に行ったとき、これ見よがしに車に物忌みの札を掲げ、式部の乗っていた側だけ御簾を下ろしていたというパフォーマンスなどは、「この女はわたしのものだから、ほかの男は手を出すな」という親王の示威行動のようなものである。そこまでしないと独占できないくらい、和泉式部は男を引き寄せてしまうものをもっていたことになる。紫式部は、こうした側面を一言「けしからぬ」と言い表してしまったのだ。
穿った見方をするなら、紫式部は羨ましかったのかもしれない。紫式部もある意味では恋しないと生きていけない性分だったように思うのだが、和泉式部のようには男が寄ってこなかった。「源氏物語」を書くエネルギーの源は、華やかな宮中でさえ満足できる恋にめぐりあえなかった、紫式部の欲求不満なのかもしれない。
 | 心身一体の恋 |
和泉式部の様々な恋は、「和泉式部集」「和泉式部日記」に歌となって残っている。和泉式部の歌(すなわち恋)は、どのような特徴があるのだろうか。
たとえば、最も有名な歌、「ものおもへば沢の螢もわが身よりあくがれいづるたまかとぞ見る」を挙げてみる。自分の魂が螢のように彷徨っているのだと歌っただけでは、もちろん意味はわかるが迫力がない。自分の身から飛び出していったという、その発想が和泉式部らしいのである。いつも自分の身が前提としてあり、歌を読んだ人に、心だけが存在するというようには感じさせない。亡くなった人を思う、哀傷の歌が式部には多いが、作者の心の痛みは、いつのまにか読者の体を切るような痛みとして伝わってくる。式部の歌が現代でも人気のあるのは、痛みが直に我々を突き刺すからだ。
おそらく恋に限らず、和泉式部は周囲の人を自分の身を削るように愛したのではないだろうか。式部は「大鏡」「栄花物語」「宇治拾遺物語」などにも登場するが、そのエピソードはどことなく生々しい。それはやはり、和泉式部の生き方と通ずるものであろう。 |