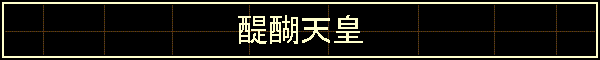宇多天皇の一男。母は藤原高藤女胤子。
9歳で立太子、13歳で即位した。摂関はおらず、菅原道真、藤原時平を内覧として(のち左右大臣)親政を行った。菅原道真が左遷されて後は時平、また時平死後は弟の忠平を台閣の首班とした。
醍醐天皇の治世は「延喜の治」として、70年ほど後にはすでに理想的な時代と考えられていた。「古今和歌集」の撰進などが、その主な業績である。が、実は凶作や疫病に悩まされ、立太子させた春宮が二人も早世するという不穏なものであった。46歳のとき、内裏清涼殿への落雷で公卿の中に死傷者を出した。醍醐天皇はその報に衝撃を受けて倒れ、7日後に咳病を患って没した。
ここに着目!
 | 延喜の治の実態 |
醍醐朝は寛平九(897)年から延長八(930)年までの30年余り続いたが、中でも延喜元(901)年から延喜九(909)年までの9年間は、道真を追放した時平が、廟堂の覇者として国政に力を注いだ時期である。延喜元(901)年「日本三代実録」の完成、延喜二(902)年の荘園整理令の発布、延喜五(905)年の「古今和歌集」の編纂、延喜七(907)年の貨幣の改鋳と「延喜式」の編纂、目に見える形での律令制再建の動きが活発になっていたことを表している。特に荘園整理令は、時平が率先して公卿会議を開いて決定したものである。法令の目的の一つは、王臣家や諸院、諸宮などの権門と地方の有力者が結びついて、地方の荘園が増加するのを食い止めることだった。時平自身、権門の一人であるから自分で自分の首を絞めるようなものだが、それを敢えてしなければならないというところに、当時の律令制の崩壊が見えるようである。効果のほどはともかく、若い時平の意気込みが窺われて、後世の人々の心を捉えたのかもしれない。
だが、時平の死でそれらのほとんどは挫折した。延喜十四(914)年、醍醐天皇が公卿から国司まで、官人らに政治に関する意見を募ったところ、前文章博士三善清行が意見封事を提出した。12箇条から成るこの意見は、地方政治の弛緩や奢侈に流れる風潮などを指摘したものである。けれども、この意見は現実の政治には反映されなかった。醍醐天皇は、父宇多上皇の享楽的な生活に影響を受け、政務より風流文事にいそしむようになっていたらしい。形の上では天皇親政ということではあるが、天皇が積極的に政治に参与しないばかりか、忠平らまでが時平の後を継ごうとはしなかった。詩宴や遊びに明け暮れる彼らの眼に、度重なる凶作や疫病に倒れる京の庶民の姿はどう映っていたのだろうか。
 | 宇多天皇と道真 |
醍醐天皇は、道真を左遷させた張本人である。実際に事を起こしたのは時平だが、道真の追放を許可したのは天皇であり、時平といえども天皇の意見を無視することは不可能である。
醍醐天皇の日記「延喜御記」には、道真が宇多天皇から承和の変のことを聞かされ、暗に天皇廃立を促された、と語ったという記事がある。醍醐天皇がそれをどこまで信じたかは明らかでない。が、道真左遷の報を聞いて駆け付けた宇多上皇に会おうともせず、道真の弁明も聞こうとしなかった醍醐天皇の頑なな態度を考えると、天皇廃立の噂は天皇自身が聞くところだったのかもしれない。父の宇多上皇とその寵臣が、自分を廃して弟の斉世親王の立太子を企てているとなれば、心騒がぬはずはない。時平が讒言したのを、根拠もなしに天皇が鵜呑みにしたというよりは、天皇自身も宇多上皇の態度などに、思い当たるところがあったのではないか。
それにしても、道真は配所にあっても醍醐天皇のことを忘れなかったが、醍醐天皇の方はどうだったのか。道真は延喜三(903)年に没している。もし時平の死後もなお道真が生きていたら、天皇は道真を京に呼び戻したのだろうか。 |