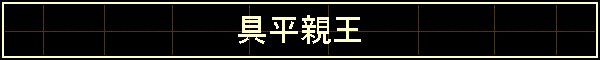事跡:
康保元(964)年6月19日、出生
康保2(965)年8月13日、親王宣下
康保3(966)年8月27日、承香殿にて着袴、親王家では御遊があり荘子女王に禄賜る
康保4(967)年正月、年給を賜る
康保5(968)年5月25日、父村上天皇、没
7月15日、母荘子女王、出家
貞元2(977)年8月11日、元服
永延元(987)年7月、兵部卿として相撲の別当になる由の宣旨下る
9月、中務卿兼明親王(前中書王)没、これ以降に中務卿となる?
正暦元(990)年12月、大江匡衡らを召して詩を賦させる
正暦2(991)年2月、『弘決外典鈔』撰述
長保元(999)年9月、大雲寺にて姉楽子内親王の周忌供養を経営
長保2(1000)年11月、荘子女王の御読経に際し外題の清書を行成に依頼
寛弘元(1004)年5月、道長が東三条院のため法華八講を開催した際、外題を書写
寛弘2(1005)年10月、木幡浄妙寺の三昧堂供養の際、外題を書写
寛弘4(1007)年4月、内裏内宴で作文開催、翌日二品となる
寛弘5(1008)年7月、荘子女王、没
寛弘7(1010)年7月28日、没。北白河の寂楽寺に埋葬
このため、8月5日の釈奠の宴・6日の内論議が中止となる
家集『具平親王集』があるが断簡。拾遺集以下勅撰集に11首採られている。
ここに着目!
 | 恋人か、それとも光源氏のモデルか |
近藤富枝の『紫式部の恋』は式部の恋人探しから始まっている。藤原宣孝以外の男とは恋らしい恋をしていない、王朝時代には珍しい恋少なき女であったという式部像に、疑問を抱かれたからだろう。
そして白羽の矢が当たったのが具平親王である。
式部の若き日の恋の相手である親王の存在は、『源氏物語』のストーリーや光源氏の人物像に影響を及ぼしているとしている。結婚前の式部が具平親王家に出仕したという説もあるくらいで、これが本当なら紫式部の伝記は大幅に塗り替えられることになる。ただし、現時点では式部の恋人説も出仕説も裏付けとなる史料はなく、あくまで推測の範囲に留まっている。が、具平親王とはどのような人であったか考察しておくことは、『源氏物語』を書いた当時の式部の内面を考える上で、いろいろと興味深いことが発見できそうである。
親王の生涯には、光源氏の前半生に相似する部分が少なからずあるように思われる。
まず思いつくのは、後ろ盾となる外戚の力不足である。母の荘子女王は天暦4(950)年、入内して麗景殿女御と称された。本来なら入内した女御は父の後見を受けるものだが、このときすでに父代明親王も母藤原定方女(紫式部の祖母とはおそらく異母姉妹)もこの世になかった。それで兄の源重光・保光などが後見をしていたらしく、具平親王も保光の邸で誕生している。荘子女王は天暦10(956)年に麗景殿女御歌合を開催するなど、風流でしかも温雅な性格を持った方であったが、政治的には全く無力だった。村上天皇中宮安子と父の師輔らが実権を握っていたからである。与えられた麗景殿という殿舎も象徴的で、『源氏物語』では花散里の姉がこの殿舎に住まっているが、やはり桐壺帝の思し召しはさほどでなく、弘徽殿女御などに押されて忘れられた存在となっている。
また、5歳で父を喪ったことも、父と母の違いがあるが、幼くして母と死別した光源氏と通ずるものがある。光源氏の場合は後見には役不足の母や祖母を亡くしたが、父の桐壺帝は健在で、帝の配慮により臣籍降下させられた後は、父の庇護のもと、宮中で何不自由なく成長することができた。だが具平親王は父帝のほうが亡くなってしまうのだから、光源氏よりもさらに恵まれない境遇ということになる。
そんな具平親王も、おそらく、7~10歳になると読書始をされたであろう。
師は二人いて、一人は橘正通である。正通は自作の漢詩の中で、具平親王が幼少より非凡であったことを詠い、その才能を絶賛している。光源氏も「わざとの学問はさるものにて、琴笛の音にも雲居をひびかし、すべて言ひつづけば、ことごとしう、うたてぞなりぬべき人の御さま(桐壺)」と賞賛されている。紫式部はこのとき、親王のことを意識していただろう。
もう一人の師は慶滋保胤で、この人は宗教結社「勧学会」というものを作っていた。勧学会がどのような活動をしていたかについてはまだ不透明な部分もあるが、だいたい一年に2回(3月と9月)、大学寮の学生20人と僧侶20人が集まって、法華経を唱えるものであったらしい。保胤はその中心人物で、勧学会に賛同した多くの学者や漢詩人たちと交流があった。保胤が寛和2(986)年に出家することで、勧学会の活動は立ち消えになってしまうのだが、そのとき具平親王は23歳であった。保胤を通じて、勧学会のメンバーとは知己になっていたに違いない。
具平親王の周りに集まった面々は、残る和歌や『本朝麗藻』などに所載の漢詩から、かなり特定できる。紫式部の伯父為頼や、父為時もその一人であった。大曽根章介によると、具平親王の邸宅に集まるのは卑官散位の者が多かったらしいが、彼らはただ風流文事を目的にして親王邸に来るわけではなく、少しでも任官の手蔓になるのではと、期待する部分もあっただろう、と言う。
もっとも、中務卿というのは閑職であり、親王自身には政治的な権力はない。だからたとえば親王が親しい学者や文人仲間をしかるべき文官の地位に就けるよう口添えする、などということは不可能だったようである。下心があるにせよ、自分を慕ってくれる学生や学者たちが、能力がありながら卑官に甘んじているとすれば、親王も手を拱いているしかない自分の無力さを歯がゆく思っていたに違いない。
「賢木」の巻には、桐壺帝崩御の後、敵対する右大臣らが政界に幅をきかせるようになり、参内もしなくなる光源氏の様子が描かれる。右大臣を快く思わない頭中将と共に、「春秋の御読経をばさるものにて、臨時にも、さまざま尊き事どもをせさせたまひなどして、またいたづらに暇ありげなる博士ども召し集めて、文作り韻塞ぎなどやうのすさびわざどもをもしなど」気晴らしに日を過ごす。光源氏が自分の思うようにならない世の中に背を向けて、風流文事にうつつをぬかすのはこの「賢木」の巻あたりから須磨流滴の間くらいなものであるが、ここには具平親王の鬱屈した感情の一端が表れていると言っては言い過ぎになるだろうか。紫式部が具平親王邸に出仕していて、親王をそば近くで見る機会があったなら、その記憶を物語執筆時に思い起こしただろう。憶測すれば、恒例と言いたげな口振りの「春秋の御読経」は勧学会における集会を暗に指しているのかもしれない。
もちろん、光源氏はいつまでも沈淪を強いられることはない。明石から召還されて帰京してからは、政治家として着実に栄華の階段を登り詰めていく。けれども、具平親王には終生そのようなことは起こらなかった。式部が日記の中で、具平親王の娘隆姫と、道長の息子頼通の縁談について道長から相談され、「まことに心のうちは、思ひゐたることおほかり」とどこか重苦しい気分を吐露しているのは、そんな空想と現実の落差に思いをいたしたからだろうか。それとも、若き日の恋を思い出してしまったせいなのか。従来のような、縁談の橋渡しは大役で荷が重いから、といった理由では説明できないように思う。藤原伊祐の項にも記したが、親王の子が従兄伊祐の養子として育てられているという一件もある。
具平親王が式部に恋の苦しみを与えたかどうかは定かではない。が、優れた資質を持っていても、それを政治の世界で生かすことができなかった親王の憂悶を、直に逢ったことがなくとも、式部が感じなかったはずはなかろう。とすれば、光源氏の生き様は、具平親王の見果てぬ夢を具現したもの、と考えてもよいかもしれない。具平親王も『源氏物語』を読んだであろうが、感想を聞くことができないのが残念で仕方がない。
参考文献:
具平親王の生涯(上) 大曽根章介 源氏物語とその周辺資料
具平親王考 大曽根章介 国語と国文学 S33/12
文人貴族の系譜 中世研究選書 小原 仁 吉川弘文館
S62/10
上代学制の研究 桃裕行 吉川弘文館
国文学 H12/8 古代文学に見る女性たち 中野幸一
本朝文粋 新日本古典文学大系
河原院と池亭 大曽根章介
|