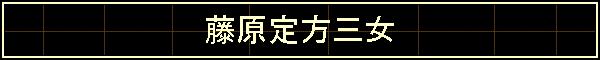|
事跡:
寛平5(893)年ごろ、出生?
延喜7(907)年ごろ、藤原兼輔と結婚?
延喜10(910)年ごろ、長男雅正を出産
延喜13(913)年ごろ、二男清正を出産
承平元(931)年ごろ、没?
承平3(933)年2月18日、夫兼輔没
ここに着目!
 | 兼輔との恋愛 |
藤原定方十一女(紫式部の父方の祖母)の項にもあるように、紫式部の曾祖父兼輔は、藤原定方三女と結婚し、雅正などの子を儲けている。兼輔が定方と親しかったのは家集などからも窺われ、また定方三女との間に生まれた雅正が定方十一女と結婚したところをみると、二人は単に親しいばかりではなく、腹心の友とでもいう間柄にあったと考えるしかない。
ところで、『大和物語』第百三十五段・百三十六段には、兼輔と定方三女の馴れ初めが描かれている。それによると、二人は兼輔が内蔵助を務めていたころに逢い始めたらしい。時期的には延喜3(903)〜延喜7(907)年ということになる。定方十一女の生年は不明だが、定方や雅正・為頼らの生年から勘考して、だいたい寛平5(893)年ごろではないかと思われる。そうすると、兼輔と恋愛・結婚したのはごく若い15歳ごろとなる。当時のこととて、早すぎるということはない。『大和物語』では定方三女のほうはあまり乗り気ではなかった。30歳になる年長の兼輔に強く求愛されたか、父定方の勧めもあって断りきれなかったのか、若い娘ならさもありなんと思われる心境である。
けれども、女も次第にほだされてきたらしい。百三十五段には、
「たき物の くゆる心は ありしかど ひとりはたえて ねられざりけり」
という和歌がある。初め後悔していた逢瀬なのに、そのうち独り寝が寂しくなってきたと言っているのである。それには、兼輔の多忙も一役買っていたらしい。百三十五段・百三十六段ともに、兼輔が宮仕えで忙しく、なかなか定方三女のところに通ってこられなかった様子が述べられているのだ。女はそれに対して、
「さわぐなる うちにもものは 思ふなり わがつれづれを 何にたとへむ」
と待つ身の辛さを訴えるようになる。男がしつこく通ってきていたならば、女はますます嫌気がさしてしまったろうが、ほどほどの逢瀬がかえって二人の仲を保っていたのかもしれない。
兼輔の多忙というのもあながち嘘ではないだろう。兼輔は家柄や血筋ではなく、どちらかと言えば実力で中納言にまで累進した人で、若いころから有能な官僚であった。後のことになるが、延喜16(916)年には宇多上皇のかねてよりの望みであった行幸を実現させている。上皇は退位後仁和寺に住んで風流三昧の生活を送っており、醍醐天皇も父の悠々自適の暮らしに感化されて、やはり風流韻事を重んじる方であったから、兼輔は醍醐天皇と上皇との橋渡しもしていた。天皇、上皇両方の信任を得ていれば、忙しかったというのも肯ける。実は後撰和歌集にも清正母の名で
「兼輔朝臣にあひ始めて、常にしもあはざりける程に
降りとげぬ きみが雪げの しづくゆへ たもとにとけぬ 氷しにけり」
という歌が残る。これもまた、兼輔の忙しさを強調している。
そんな状況であっても、兼輔は定方三女を大切に思っていたようである。多忙の最中にも、自分の無沙汰を定方三女がどう感じているかと気遣っている。後に妻が亡くなったときには、「亡き人の共にしかへる年ならば暮れゆく今日はうれしからまし」という哀傷の歌を紀貫之に送っている。この妻というのが誰かは断言できないが、兼輔は身分の割にはほかに記録に残るほどの身分高い妻がいた形跡がなく、おそらく正妻格であった定方三女の死を悼む歌と考えるのが自然だろうと思う。
参考文献:
平安時代私家集の研究 久保木哲夫 笠間書院 S60/12
三条右大臣集
兼輔集
大和物語
後撰和歌集
|