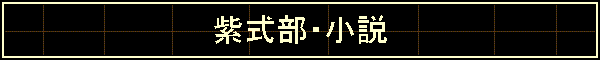紫式部を主人公にした小説を集めてみました。
紫式部物語 その恋と生涯 ライザ・ダルビー 光文社
アメリカ人作家による作品とは思えないほど、日本の古い習俗や年中行事の微細な描写が随所に散りばめられている。『紫式部集』『紫式部日記』の研究成果もかなり反映していて、式部の詠んだ歌はほとんど本文中に出てくる。一般に内向的と言われる紫式部だが、娘時代の前半部は割と明るい、からりとした性格に描かれているので新鮮な印象を受ける。
【章立】
プロローグ
式部の娘、賢子が自分の娘に宛てて書いた手紙という体裁。紫式部の死後、遺品の中に回想記を見つけたことを書いている。
紫式部回想記 ここから回想記。式部が自身で書いたものであるから、物語全体が式部の視点で語られる。
蜻蛉庵 回想記を書いた契機を述べる。『蜻蛉日記』に触発され、自分の人生を回想記にしたためておこうと考えたという。
1若紫 15歳で母と死別した式部は、翌年祖母の家から賀茂川に近い父方の家に移った。
2ちふる 17歳。家刀自として雑用に追われながらも読書にいそしみ、勉強好きと評判の娘になる式部。そのころ、幼友だちのちふるが上京して再会できたが、ちふるはすぐに筑紫へ旅立った。友もなく、義母との窮屈な同居生活の中、式部は光源氏の物語を「朧月夜」の巻から書き始める。
3朧月夜(光源氏の恋の冒険) 式部は物語を筑紫へ送ったが、結婚して立場の変わってしまったちふるは、返事をくれなかった。
4朝顔 たえず漢詩を口ずさんでいるという若者に、式部は強引に関係を持たされる。
5柳 21歳になっても、式部には縁談はなかった。為時は式部が『源氏物語』を書いていることを知るが、特に禁止はしなかった。
6瑠璃 都で天然痘が流行し始めたため、式部は東山に住む親戚の女性のもとへ避難する。おばと呼ぶその人は、『蜻蛉日記』の作者であった。ここではいとこの娘るりと出会い、二人で物語制作について語り合うようになる。
7時鳥
為時は式部を連れて、藤原道兼の家司の家で開かれた詩宴に出席する。為時は道兼が政権を握ることに期待をかけていた。が、長徳元年、道兼は関白になるも、直後に疫病で他界。政権は道長へと移る。
8蚯蚓
姉の孝子、そしておばが天然痘で相次いで亡くなった。
9新年
長徳2年、為時は越前守に任官が決まった。式部は姉の法要の席で、妹を亡くしたという娘、山吹と出会う。
10旅の記録
式部は帰京後、宣孝と結婚するという条件のもとに、為時から同行の許可を得た。山吹との別れを惜しみ、式部は越前に向けて出発する。
11「枕草子」
越前に着いてほどなく、式部はるりが宇治川に身を投げ、自殺したことを知る。
宣孝が送ってきた『枕草子』を読みふける式部。
12明國
唐土から、周世昌を初めとする宋人の一行が到着し、為時と対面する。式部は周の息子の明國を知り合う。
13雪月
越前での冬が訪れる。式部は明國と語り合うのが楽しくてしかたがない。
14東風
明國から絵を習い、お国のことを聞いて楽しく過ごす式部のもとに、宣孝からの手紙がくる。
15唐物語
明國は国に伝わるという不思議な話を聞かせる。二人に、別れが近づいていた。
16流し
明國は式部に愛用の硯などを渡すと、越前を発っていった。
17五月晴れ
明國と別れてからは、式部は宣孝や山吹と文通を続け、『源氏物語』を書き進める。が、雁が京へ向かって飛び立つ秋、帰京を決意する。
18心づくしの秋
式部は帰京後、祖母の家に従姉妹らと同居した。長徳4年夏、式部のもとへ、宣孝が通うようになる。
19鬼の影
式部は宣孝が自分のために新しい邸を建てたことを知るが、宣孝の体調が悪いと聞き、本邸に見舞いに訪れる。そこで、宣孝の本妻が生んだ娘に『源氏物語』を読んだと話しかけられる。
20解け水
式部は宣孝の邸に移り、九月九日、結婚式を挙げる。
21北の方
冬、式部は女児、賢子を出産した。賢子が2歳になった年の春、宣孝は急死する。
22墨染めに霞む空 宣孝の没後、式部は一年を喪に服す。
23薄きとも見ず 道長邸での詩宴に父為時が招かれ、式部の宮仕えを遠回しに打診される。
24唐竹 知り合いの宰相の君が里下がりした折、式部は道長、伊周、彰子といった宮中の人々の動静を聞く。
25雲の上 道長から出仕の要請を受けた式部は渋っていたものの、結局暮れもおしつまってから出仕する。
26暗きより 新参女房は道長から儀礼的に同衾するものと聞かされた式部だが、道長は意外にも御座所で拾遺和歌集の撰歌の話をしただけに終わる。宰相の君に、道長から顔を見られたことのほうが恥だと言われ、怒った式部は里下がりしてしまう。
27おだえの水 宮中からは出仕の催促があった。式部は宰相の君と歌の贈答で仲直りし、再び出仕する。
28清少納言 主の皇后定子亡きあと、宮仕え先に恵まれない清少納言に、式部は対面し、『枕草子』について語り合う。
29女郎花 土御門邸にて、中宮主催の香合が行われ、式部が調香した香が一席を取る。
30雪の下草 式部は里下がりして、『源氏物語』の新編(玉鬘物語)を書き始める。
31桜狩り 式部は興福寺から届く新年の桜の取り入れ役を伊勢大輔に譲る。同僚大納言の君が、物の怪に憑かれる。
32叩く水鶏 中宮彰子は懐妊し、土御門邸に戻った。法華三十講が盛大に行われる。
33敦成親王 秋が深まる土御門邸、中宮は9月に第二皇子敦成を出産する。
34光さしそう 三夜の産養から、九夜の産養までの記録。
35水鳥 その夜、式部は小少将の君と語らった。行幸に向けて、準備に追われる式部たち。
36万歳千秋 一条天皇が生まれた我が子を見るため、行幸。
37わが紫 敦成親王の五十日の祝いの席で、式部は公任に「わが紫やさぶらふ」と言葉をかけられる。
38うき寝せし 中宮の女房たちは手分けして『源氏物語』清書に励む。式部が里下がりから帰った後、一行は内裏へ戻った。
39五節の舞 五節の舞が行われた。式部は9歳になる娘の賢子のために教訓となる覚え書きを書こうと考える。
40年暮れて 里下がりしていた式部は、年の瀬になって内裏へ戻ったが、新年を迎えるとすぐ退出した。
41ささがに 伊周ゆかりの者による中宮呪詛事件発覚。この年、一条仮御所が焼亡、中宮は第三皇子敦良を出産。
42野辺に小松 中宮、枇杷殿に移る。
43憂さのみまさる 式部は本心を認めた手紙を父や山吹に送るようになる。
44宇治 一条帝の崩御に伴い、中宮は式部ら女房を連れて枇杷殿に移った。この年、父が越後守として赴任したものの、同行した惟規は現地で没する。式部は山吹に出家を勧められ、身辺整理を済ませると、出家する。
エピローグ 賢子の手紙 晩年の式部の様子を語り、式部の書いた『源氏物語』最後の章をみつけたことを記している。
稲妻(「源氏物語」の失われた終章) 出家した浮舟は稲妻に打たれ、失明する。匂宮は浮舟への執着がなくなったことを感じるが、薫は再び浮舟に会いにくる。
【オリジナル】
・紫式部の少女時代の親友としてちふる・瑠璃・山吹などが登場。家集から窺われる細やかな友情を描く。
・越前滞在中、宋から来た一行の一人明國と出会い、恋愛したことにしている。
・「ささがにの〜」が、実成との贈答歌ということにしている。
・紫式部が自分の生き様を回想記に書いていたことになっている。
・紫式部が「夢浮橋」以降に『源氏物語』の終章を書いたことになっている。
【諸説の選択】
・惟規は兄か弟か→弟
・出生年→天延元(973)年
・『源氏物語』はどの巻から書かれたか→朧月夜の巻からとしている
・紫式部は出家したか→出家したとする
・没年→式部は寛仁3年に没した。
【難点】
・式部の母が式部15歳のときに亡くなったとした理由が不明。小説を永延ごろから始めると都合がよいということで設定したのではないか。
・頼通・教通の名前が「頼道」「教道」になっている。
・式部が宣孝の本邸に訪ねていく場面が何度かあるが、普通は考えられない。
・式部が為時に連れられ、公卿などの邸で開催される詩宴に出席したとあるが、当時宮仕えもしていなかった式部の立場からすると、不自然。
・宣孝と結婚したころ、式部が公任と話す場面があるが、親族と言うほど近しい関係ではないのに直に話すのはおかしい。
・異母兄弟の惟通、定暹がそれぞれ5歳、3歳のときに、元服後や出家後の名前なのは、幼名にすべき。
・家集の17番「難波潟〜」は明國の歌、21番「磯がくれ〜」は、明國に送りたいと式部が思った歌とする。家集では明らかに筑紫へ行った女友だちとの贈答歌で、事実を枉げている。
・『源氏物語』の終章を創作する必要があったのかどうか、疑問。
【参考】
先日、平安王朝クラブのメンバーの一人が作者のライザ・ダルビー博士に手紙を出しました。
紫式部が15歳のとき母親を亡くしたことなどについて、誤りを指摘したのですが、博士の返事を抜粋してみます。
「歴史的な事とそれから人と場所の正しい読み方については、わたし自身は特別な知識は持っていません〜(中略)〜専門家に見てもらいましたが、間違いがまだ残っている」
「歴史的な証拠が曖昧なところがいっぱいあります。例えば、紫式部の弟惟規が家族と一緒に越前まで行ったかどうか、本当に分かっていないと言ってよいと思います。こういう場合には、わたしは勝手に一方の説を選びました」
「お母さんが何年に亡くなったかということについても、わたしが読んだ限り、いろいろな学者がいろいろな意見を持っているらしいです。〜(中略)〜光源氏が幼い時にお母さんを失ったという事は、必ずしも紫式部の経験を反映している訳ではありません。〜(中略)〜小説を書くことは、自分の経験を乗り越えて想像力を使うことではありませんか」
「実は、わたしの元の目的はできるだけ歴史上の人物を保存することでしたが、書いているうちにそれは難しくなりました。〜(中略)〜結局、わたしは歴史学者の為に書いているのではなく、やっぱり小説を書いているということが分かりました」
「紫式部の生涯と作品は深いインスピレーションの海です。それぞれの人のいろいろな見方があると思います。ある書評によると、わたしの紫式部は『20世紀末の現代的な紫式部』と判断されていました。本当だと思います。考えたら、そうじゃなければおかしいでしょう」
散華 −紫式部の生涯− 杉本苑子 中公文庫
紫式部の一生を手堅く、力強く描き出しているのはこの作者ならではのこと。主人公に関しては史実に忠実、周囲の人物は作者の自由な空想や脚色が入って娯楽性がある。紫式部の生きた時代の政治背景や生活習慣なども主人公たちの口から適宜語られる。紫式部の内面描写は細緻にわたっていて、興味をそそられる。
【章立】
<峠路の賊>
祖先の墓参りのため山荘から山科へ行った小市(紫式部)らは、途中で賊に会う。その後、京極邸に戻った一行は、伯父の為長の病気平癒を願って持仏堂にいたところ、大地震に襲われる。
<蜻蛉日記>
為時に東宮師貞の侍読の役が与えられた。小市は、その口利きをしてくれた曾祖父のもとへ為時がお礼に参上するのに従い、大伯父から『蜻蛉日記』を渡される。
<魔火>
叔母の周防のもとに、奇妙な文が届くようになった。このころ、姉の大市は皇太后昌子内親王のもとへ出仕。小市は従兄伊祐とともに清原元輔のもとを訪れ、娘の清少納言と会うことになる。
<麗しの女御>
中納言義懐を後ろ盾とする花山天皇の御代が始まった。為時は式部丞となり、姉の大市は義懐の妻となった。一方、小市は三月上巳の日、鴨川の河原に出たところで宣孝に恋文を渡される。その後、同行していた御許丸(和泉式部)が乱暴されていたところを男に助けられる。男は山科で会った賊で、保輔といった。
<蓮の葉の露>
保輔の香を嗅いで、小市は叔母周防の恋文の差出人が保輔であると知った。保輔は現在の中央政界のことをつぶさに語り、父為時に用心するよう小市に忠告する。そしてその言葉通り、1年あまりで花山朝は崩壊した。
<冬の季節>
義懐は出家し、大市はその打撃で寝込むようになった。為時も失職し、一家は暗い日々を過ごす。小市の慰めは、親友万奈児との語らいだった。
<死神>
中関白一家の栄華をよそに、京極邸はますます陰鬱になっていった。大市や為頼室(伯母)の死、為時ばかりか惟規も官途に就けない。世間では疫病が蔓延し、中央政界の公卿たちも次々に没した。政権は誰の手に渡るのか、まったく予測がつかない状態であった。
<夏衣>
長徳2年正月、為時はようやく越前守の地位を得た。小市は父に従って、任国へ行くと申し出る。このころ、道長は伊周を左遷させることに成功し、ようやく政権を我が手に掴む。
<越前国府>
越前での生活が始まった。が満足な話相手のいない毎日に嫌気がさしたとき、伯父為頼の体調不良が知らされる。宣孝との結婚の期待を胸に、小市は看病を口実に帰京する。
<移りゆく日々>
帰京後、宣孝の妻となった小市。幸福とは言えないものの、一女賢子をもうける。だが3年目、長保3年に宣孝は疫病で急死する。
<光る源氏 輝く日ノ宮>
喪中の小市に義理の息子隆光が求愛するが、小市は相手にしなかった。小市は『源氏物語』を書き始める。初めは伯母や友人だけに見せていた物語が、やがて書写を重ねて評判になり、出仕の要請が道長よりもたらされる。
<出仕>
寛弘2年、小市は中宮彰子のもとへ出仕するも、道長の儀礼的な求愛に憤り、京極邸に舞い戻る。
<道長呪詛事件>
左大臣家からの再三の説得で、小市は再び宮仕えに出る。折しも主の中宮が第二皇子敦成を出産という慶事の直後、伊周の家司らが道長を呪詛するという事件が発覚、小市は捏造の事件と知りながらも、政権に対する道長の執着を冷徹な目で見据える。
<宇治十帖>
寛弘6年には第三皇子が誕生するが、その陰で伊周はひっそりと没した。光源氏の華やかな生涯と自身の乖離を感じ始めた小市は、『源氏物語』正編より色調の暗い宇治十帖の執筆に取りかかる。
<人形から賢后へ>
一条天皇が危篤に陥るや否や、道長は天皇や彰子に気遣いもせず、第一皇子敦康親王を退け、孫である敦成親王を強引に次期東宮にしてしまう。新たに即位した三条天皇にも早期退位を求めていやがらせを繰り返す。彰子はそんな父の態度に反発し、賢人と言われた右大臣実資に接近する。
<ねむの花>
小市は彰子と実資の橋渡しをしていたことを道長に知られ、女房を解雇される。小市は京極邸に戻ってから体調を崩し、まもなく娘に看取られて亡くなった。
【オリジナル】
・紫式部の叔母として周防を登場させ、袴垂と呼ばれた盗賊、藤原保輔との恋を描く
・紫式部の姉(作中では大市と呼ばれる)が昌子皇太后のもとに出仕していたとし、その夫を藤原義懐とする
・紫式部の従兄伊祐が周防を、大市が伊祐に恋心を抱いていたとする
・宣孝の子隆光が式部に求愛したことにしている
・和泉式部が紫式部の幼いころからの友人として登場する
【諸説の選択】
・惟規は兄か弟か→弟とする
・姉妹の約束をした女友だち→橘為義女としている
・紫式部と藤原道長の関係→式部は道長の愛人の一人だったとする
・『源氏物語』はどの巻から書かれたか→桐壺の巻からとしている
・紫式部は出家したか→出家していないとする
【難点】
・道長の妻倫子が受領層の出身であったというのはおかしい(皇孫源雅信の娘)。
・伯父為頼の官歴に摂津守、丹波守があるが、紫式部の幼時はまだ任ぜられていないのに、すでに前司となっているのが事実と異なる。
・女友だちとの交流が最小限にしか描かれず、娘時代の恋愛も宣孝との文通以外は皆無で、華やぎに乏しい。紫式部の性格も暗く、式部一家が不遇であったせいで全体に寒色といった色調が濃い
小説紫式部 香子の恋 三枝和子 福武文庫
『散華』よりやや明るい性格の紫式部。
【章立】
第1章 越前に向かう
長徳2年秋、父為時の越前守任官に伴って任国へ下向する香子は、途次、宣孝や歌を交わし合った幼友達を想い出す。
第2章 宣孝・不本意な結婚
冬の厳しい越前での生活になじめず、香子は長徳4年春、物語を書くために単身帰京し宣孝と結婚。が3年後、宣孝は急死する。
第3章 物語作者として
宣孝の喪も明けないころ、香子は宣孝の子隆光に求愛されるも拒絶。その体験をきっかけに『源氏物語』を執筆。物語の流布とともに、香子のもとに道長からの出仕の依頼があり、寛弘2年、香子は中宮彰子のもとに出仕する。
第4章 道長・恋と空しさ
出仕直後、道長に情交を迫られた式部は自邸に逃げ帰るようにして戻ってしまう。だが同僚や中宮からの要請で、再び出仕することになる。
【オリジナル】
・宣孝とほかの妻の間の子隆光と恋愛関係があったことにしている
【諸説の選択】
・越前よりの帰京→長徳4(998)年とする
・紫式部と道長との関係→式部は道長の愛人だったとする
・惟規は兄か弟か→弟とする
・『源氏物語』をどの巻から書き始めたか→「桐壺」からとする
【難点】
・この作者はいつも地の文が「ですます調」で、やや緊張感に欠ける
・物語の中でならどんな恋もできるが、実際の恋は苦手という紫式部像は、一般的な式部のイメージと大して変わらない。
・隆光の求愛、道長との情交の描写とも、『散華』と酷似している
【章立】
第一章 めぐりあいて
長保3年8月、香子は月を眺めながら、4ヶ月前に死んだ夫宣孝との逢瀬を想う。あなたは物語が書ける人だ、と夫から言われたことをきっかけに『源氏物語』を書く香子。幼いころ山科の祖母のもとに暮らしていたときの記憶をもとに「若紫」までを書き上げる。
第二章 わかたけの
物語を書き進める香子のもとに、亡夫の長男隆光が訪れる。直に逢いながら、しかし何事もないまま一夜を明かす。
第三章 かきほあれ
宣孝の娘から和歌をもらった香子は返歌を贈る。このころ、『源氏物語』は「葵」まで書かれていた。
第四章 みのうさは
寛弘2年、道長から出仕の要請を受けた香子は中宮彰子のもとに伺候する。
第五章 わりなしや
宮仕えは肌に合わないと、数日で里に帰る香子。が中宮らの懇望により再び出仕した。中宮は待望の男子出産で土御門邸は沸き返る。その一方で、親しい友の加賀少納言が出家してしまう。
第六章 としくれて
健康を損ね、また彰子と実資の連絡を務めていたことを道長から疑われた香子は宮仕えを辞めた。自邸で心静かに家集を編纂し始める。
追記 亡き人を
紫式部の出家を見守った加賀少納言が、式部の失踪を語り、その胸の裡を忖度する。
【オリジナル】
・宣孝は「痔」を患っていた
・加賀少納言は死んだ姉の友だちだったとする
【諸説の選択】
・惟規は兄か弟か→兄とする
・『源氏物語』をどの巻から書き始めたか→「桐壺」からとする
・紫式部は出家したか→したとする
【難点】
・宣孝が「痔」であったというのは、『小右記』長保3年2月5日の記事(春日祭代官を命ぜられるも痔病のため辞退)を参考にしたものと思われる。が、これは宣孝が急死する2ヶ月あまり前のことであり、宣孝は流行していた疫病にすでに冒されていて、痔というよりは疫病の影響が出ているのではないか。また、宣孝は祭のときなどにたびたび舞人を勤めたり、遠方へ勅使としても立っている。持病として痔を患っているとは考えにくい。
・式部は宣孝からみると正妻に次ぐ本妻の地位にあったとするが、当時正妻、本妻などという区別はない
・『源氏物語』の「葵上」という巻があるように書かれているが、「葵」ではないか?
・異母弟の惟通が皇后宮(定子)権大進であったとしているが、これは同名異人のはずである