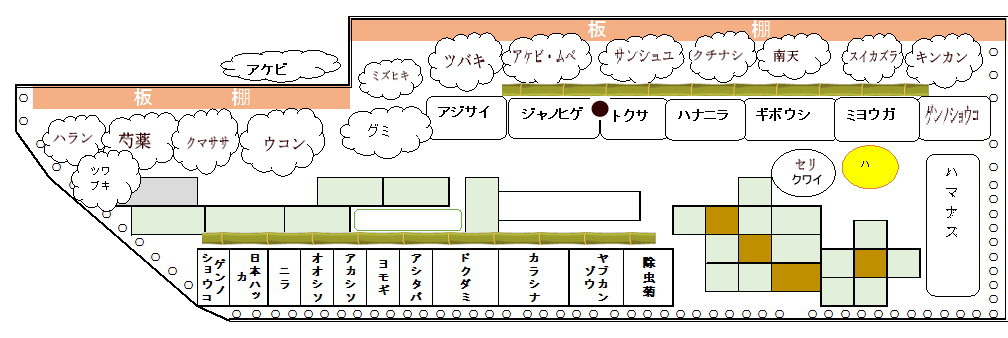
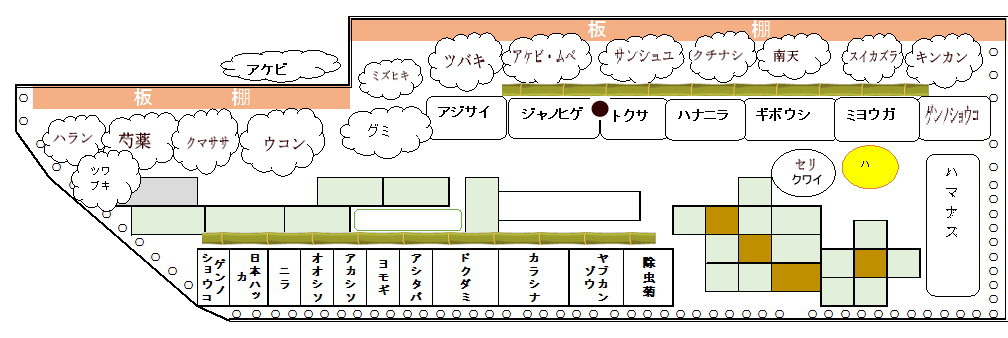
| 和のハーブゾーンの花 須磨離宮公園監修・ハーブ園名札集より(一部ネット調べ) | ||||
| 品種名 | 草 状 | 開花期 | 原産地 | 薬 効 |
| アケビ | 蔓性 | 4月 ~5月 | 日本 | 果実にはビタミンCが大量に有り疲労回復・肌荒れに効果有り |
| アジサイ | 低木 | 6月~7月 | 日本 | |
| アシタバ | 多年草 | 5月〜10月 | 日本南部 | ビタミン12を含み貧血や高血圧予防に期待されます。 |
| ウコン | 球根 | 9月~10月 | 熱帯アジア | 秋に芋を掘り陰干しにする。胆のうや肝臓の働きをよくする |
| シソ | 多年草 | 9月 | 中国 | 古くから栽培されてきた香辛野菜で、独特の芳香が有り天ぷら他に利用 |
| ギボウシ | 多年草 | 6月~9月 | 東アジア | 多種の園芸品種が作られている観葉植物 |
| グミ | 低木 | 4月~5月 | 東南アジア | 酸味を生かしてドレッシングにして食べるのもお勧め |
| クワイ | 多年草 | 8月~9月 | 中国 | 正月のおせち料理に縁起が良いとして使われる。 |
| クチナシ | 常緑低木 | 6月~7月 | アジア・アフリカ | 乾燥果実を漢方薬として止血・利尿として利用 |
| クマササ | 常緑低木 | 殺菌力が有り食品を包むのに利用、胃炎・口内炎等に効果有り | ||
| キンカン | 常緑低木 | 初夏~初秋 | 中国 | 砂糖漬や果実酒で、咳止め等に利用 |
| ゲンノショウコ | 多年草 | 夏季 | 日本・中国 | 根・茎・葉・花を煎じて下痢止めや胃薬として利用 |
| ジャノメヒゲ | 多年草 | 8月~9月 | 日本・東アジア | 根は漢方の「麦門冬」で咳止強壮等の生薬剤です |
| サンシュユ | 落葉小低木 | 3月~4月 | 中国 | 乾燥果実は滋養強壮・疲労回復に利用されて来た |
| シャクヤク | 多年草 | 初夏 | 中国東北部 | 秋に根を掘り日干ししたものを芍薬と言う漢方の鎮痛剤として利用 |
| 除虫菊 | 多年草 | 7月〜9月 | 日本・東アジア | 植えているだけで、虫よけになります。 |
| セリ | 多年草 | 7月~8月 | 日本自生 | 春の七草として古くから食用や乾燥させて薬用にも利用 |
| ツバキ | 常緑低木 | 3月~4月 | 日本・中国 | 椿油は昔からの化粧油として利用されて来た |
| ツワブキ | 多年草 | 10月~12月 | 乾燥した葉・茎・根は健胃や魚中毒に・生葉はおでき・切り傷に利用 | |
| トクサ | 多年草 | 地上部を日干しにした物を木賊と言い痔・下痢・解熱に利用 | ||
| ハマナス | 落葉低木 | 6月~8月 | 北日本 | 乾燥花はお茶にして下痢剤、果実は果実酒として需要強壮剤利に利用 |
| ハナニラ | 球根草花多年草 | 3月~4月 | ハナニラは鑑賞用花。食用の花ニラ(花韮)とは違う | |
| ハラン | 常緑性 | 南西諸島 | 食品の包装や、にぎり寿司などの下敷きに利用される | |
| ミズヒキ | 多年草 | 9月~10月 | 日本・中国 | 止血・鼻血・内出血・腰痛・胃痛の痛みを和らげる |
| ムベ | 蔓性 | 5月 | 日本・中国 | 10月に赤紫色に熟しますが、アケビの様にさけない |
| ナンテン | 常緑低木 | 初夏 | 日本・中国 | 乾燥実は咳と目に、科乾燥葉はうがい薬や浴剤に利用 |
| ノカンゾウ | 多年草 | 6月〜9月 | 日本 | 乾燥したつぼみを煎じて解熱剤に利用。 |
| ニラ | 多年草 | 6月 | 中国 | 特有の香りがする葉と花茎を利用、カロテン・ビタミン類・カルシュームが豊富 |
| ヤブカンドウ | 多年草 | 6月~9月 | 中国 | 乾燥した蕾を解熱に、乾燥根は不眠症に煎じて利用した |
| ドクダミ | 多年草 | 6月~7月 | 乾燥葉のお茶は高血圧や動脈効果や高血圧、生葉は汗疹やはれものに | |
| ヨモギ | 多年草 | 8月~9月 | 日本 | 草餅や草だんごの食材に、乾燥葉は煎じて湿疹・汗疹の冷シップに |
| エゴマ | 1年草 | 8月~9月 | 焼肉などに辛味噌などを付け、生葉で巻いて食べる | |
| ワサビ菜 | 多年草 | 日本 | ビタミンAになるカロテンが豊富に含まれているのが良いですね。 | |