第1章 MSの概要
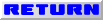
1 MS(モビルスーツ)の定義
MSとは、Mobile SUIT(Space Utility Instruments Tactical = 戦術汎用宇宙機器)の略称で、あらゆる戦術に対応できる高い汎用性を持った戦闘兵器である。
名称にもある通り、本来は宇宙用兵器として開発されたものだが、“人型”をしていることから、地上においても高い性能を発揮し、MSが一般化した現在では戦術汎用宇宙機器というよりも汎用人型機器といった認識が強くなっている。
2 ロボットの歴史
起源
人類が自らの形を模した人型機械を生み出したのは、諸説あるが9世紀頃に考案された「カラクリ時計の人形」が始まりであると言われている。
それがMSとはつながっているとは考え難いかもしれないが、自動車とて「ただの丸い輪」(つまり車輪)や「丸木」(正確にはころ)が起源だったと言われているのだ。
しかし、やはりMSの起源は“ロボット”と言った方が、誰もが納得できよう。MSも呼称こそ違えど、ロボットの一種であることは間違いない。
当然、その「カラクリ時計の人形」の時代にロボットという言葉はなかった。ロボットと呼ばれるようになるには、それから実に、10世紀以上も後になってからのことなのだ。
それまでは、中世のヨーロッパ辺りではオートマトンと呼ばれていた。オートマトンとは、西洋式のカラクリ人形を指す。
また、現在、等身大の人型機械を指す言葉としてアンドロイドがある。一見、新しい言葉のようにも思われるが、これもロボットという呼称よりも起源は古い。
ロボットという呼称
ロボットという言葉が誕生したのは、1920年にチェコのカレル=チャペックという作家が発表した『R.U.R~ロッサム・ユニバーサル・ロボット会社~』という戯曲であった。
ロボット[Robot]とは、チェコ語の強制労働[robota]や労働者[robotik]からの造語である。これだけでも、ロボットが初めから、“奴隷”や“道具”として考えられていたことがわかる。
しかし、ここで登場するロボットは、今日想像されるようなロボットとは違う。この作品のロボットは、人間の代わりに労働作業をさせるために、人体構造を極限まで単純化し、大量生産を可能とした人間なのである。言いかえれば人口生命体、現在は生体ロボットと呼ばれているものだった。
機械化したロボット
この後のロボットがどうして機械化していったかは、定かではないが、ロボットという言葉が誕生する以前、18世紀の産業革命に前後してヨーロッパ各地で作られたオートマトンに要因があるらしい。
その頃、複雑かつ巧妙に作られたオートマトンが公開された。そして、機械を組み合わせれば、生物的な動きをするものが生み出せるというイメージを定着させたのだ。
二足歩行ロボットの挫折
だが、人型のロボットを作るのことは、意外なほど困難を極めた。二足歩行における姿勢制御が、予想以上に難しいものだったのだ。
二足歩行ロボットの起源は、1983年にカナダのジョージ=ムーアという人が作った蒸気人間だったとされている。しかし、この蒸気人間は腰の部分に支持棒がつながっていて、同じところをグルグルと回るというだけのものだった。
また、二足歩行の研究が続けられる一方で、ロボットが「必ずしも人型である必要はない」という考え方が強まり、二足歩行ロボットの有用性を疑問視する声もあって、ロボットは自動車製造に代表される産業ロボットとしての道を歩み出した。
二足歩行が困難だったのは、歩行機構そのもののハード的な問題よりも、姿勢制御というソフト的な問題が大きかった。
それは、ロボットには不可欠なコンピュータ技術が開発開始当時に立ち遅れていたことが大きな原因であり、当時は、ロボットを片足で立たせるのに世界最大級のコンピューターを数台要したのだ。
20世紀末のコンピュータ技術の大躍進によって、コンピュータは急速に高性能化した。同時に大幅に小型化され、ようやく問題解決の糸口を見つけるに至り、遂に二足歩行は実現された。
しかも、それを実現させたのは日本の自動車メーカーであったというから驚かされる。
そして、そのロボットの滑らかな歩行は、誰もが驚き、感動した。ヨチヨチ歩きと酷評された二足歩行ロボットは、10数年の歳月をかけて確実に成長していたのだ。
人型機器たるMSのフォーマットは、この時に確立されたと言っても良いかもしれない。
それにしても、確かに旧世紀の日本の技術力は紛れもなく世界一と言えるものだったが、まさか自動車メーカーが作り出すとは誰も思わなかっただろう。
3 MSの歴史
MSの必要性
二足歩行は実現されたが、それでも巨大ロボットたるMSが必要とされる理由は無い。
だが、ミノフスキー粒子の発見と、その特性が状況を一変させた。
詳しくは後項に譲るが、ミノフスキー粒子は単調波から超長波に及ぶ全ての電磁波を著しく減衰させる性質を持っている。
それはつまり、艦砲射撃による長距離攻撃やミサイルなどの誘導兵器が使用不能になるということであり、これにより近接戦闘が不可避となるのだ。
近接戦闘、そしてその他の雑用をこなす汎用性、それらを統合すると、人型巨大ロボットたるMSの必要性が浮かんでくる。
MS誕生
史上初のMSは、もはや言う必要も無いかとも思われるが、宇宙世紀(以下U.Cと略す)0073年にジオン公国が開発したMS-01ザクである。
だが、ジェネレーターの出力不足で予定の機動力を発揮することは出来ず、3号機までは手足を動かすのがやっとで、装甲も薄く、とても実戦に耐えうる機体ではなかった。
それから半年ほどの月日が流れ、高出力で小型なミノフスキー型核融合炉が開発され、4号機で実戦型MSは実現された。
そして、U.C0075年5月、初の量産型MSであるMS-05ザクⅠがロールアウト、2年後のU.C0077年8月には更に強化したMS-06AザクⅡがロールアウトした。
余談だが、一般的に「ザク」と言えばMS-06系ザクⅡのことを指し、ザクⅠは旧ザクと呼ばれることが多い。
ザクⅡは、U.C0079年1月3日の一年戦争開戦までに頻繁に改良を受け、B型、C型を経て、歴史に名を残すF型、MS-06FザクⅡとなった。その後、地球進行の際、地上戦仕様としてJ型も生まれた。
また、他にも数多くのバリエーションを展開した。それは、この機が非常に汎用性の高い機体であることを如実に示している。これほど多くの用途に適応した機体は、それ以後出現していないと断言しても良いのではないだろうか。
ちなみに、形式番号でC型の以後、D型、E型を飛ばしてF型になっているのは、D型がデザート(砂漠戦用)、E型がイーワック(偵察用)として割り当てられていたためである。
基本的に標準型のザクは、Fで表され、製造期間やタイプによってFS、F2、FZなどの型がある。
白いMS
MSを語る上で、ザクと並んでが忘れてはならない機体がある。RX-78ガンダムだ。
一年戦争勃発後、約2週間が経過した同年1月15日に行われたルウム戦役で、連邦軍はMSの戦力としての高い性能を目の当たりにした。
実は当時、連邦軍も、ジオン公国がMSという新型兵器を開発しているという情報を得て、U.C0078年3月に開発を開始していた。
しかし、ジオン公国がMS-01ザクの開発に成功してから5年、基礎研究も含めれば10年近く遅れていた当時の連邦軍の技術では、ルウム戦役には間に合うはずもなかった。
そしてまた、当時の連邦軍は未だ大鑑巨砲主義が強かったため、MS開発も遅れていたのだ。ルウム戦役敗北の最大の原因はそこにあると言える。
ルウム戦役でMSの有効性を身をもって知らされた連邦上層部は、MSの開発を急ピッチで行わせた。その甲斐あってか、U.C0079年7月、後に伝説と化す白いMS『RX-78ガンダム』が誕生した。
ガンダムがザクを越える機体となったのは、ビーム兵器や新素材などの周辺技術がジオン公国よりも進んでいたからだ。
ビームライフルやビームサーベルなどの強力な武器、そして軽量かつ堅牢なルナチタニウム(後のガンダリウムα)という当時において“最強の矛と盾”を、ガンダムは生まれながらに与えられていたのだ。
また、ガンダムをベースに各部を簡略化し、生産性を高めた量産型MS、RGM-79GMは非常にバランスの良い機体で、パイロットからの評判も良かったという。
時代の裏舞台
一年戦争末期、ジオン軍は従来の構想とは異なった兵器体系を展開し始める。
ニュータイプ専用機、公国内のフラナガン機関で新たな戦力として研究されていた「ニュータイプ」に適合した機体の投入である。
一年戦争の主戦場に、これに匹敵する連邦軍製機動兵器が登場したという記録はない。だが、実際には開発されていた。
ニュータイプ能力を有すると思われるRX-78の搭乗者、アムロ=レイ専用に開発されたガンダムがそれだ。RX-78NT1、通称「アレックス」と呼ばれる機体である。
本来は、サイド6を経てアムロ=レイへと手渡されるはずであったが、その途中でジオン独立部隊と交戦状態に陥り、機体は破壊されてしまった。
時に、月面グラナダにおいて連邦政府とジオン公国との間に終戦協定が締結される直前のことである。
過度期
そして迎えた戦後。連邦軍は、公国軍のMS研究資料及び技術者を手中に収め、MS技術の遅れを取り戻し、同時に新たな主力兵器を模索する時代に入る。
その際、戦略を盛り込んだMSの開発が極秘裡に提案されていた。それがGPシリーズのガンダムだ。
U.C0083年9月29日にロールアウトしたRX-78GP01は、RX-78の正当な後継機を目指した機体で、汎用で白兵戦向きの設計概念は全く同じものである。ただし、当然のことながら新なる試みはなされている。
RX-78では宇宙空間であっても地上であっても特別な装備換装は行わなかったが、GP01では宇宙用装備が存在する。宇宙戦装備を施されたGP01は“フルバーニアン”と呼ばれ、当時としては最高の機動力を実現していた。
GP01が完成する9日ほど前の9月18日には、GP02がロールアウトしていた。GP02は戦術核を使用することを前提に開発された機体である。MSの機動力を活かして敵地深くに侵入して核を発射、中枢部を早期に叩いて、敵を弱体化させる戦法が想定されていた。
MAとしての可能性を探ったGP03の三系統(不確定情報では四系統)の試作機が存在したが、どれも量産されるには至らなかった。
この時期は、次期主力機を目指して何体もの機体が開発されたが、実際に正式採用されたものは少ない。
躍進
MS誕生から15年余りを経て、MSに第一の転機が訪れる。ムーバブルフレーム構造の実用化と可変MSの登場である。
ムーバブルフレーム構造は、装甲と構造材を兼用する従来のモノコック構造と異なり、装甲の内側に骨格を形成している。いわゆる内骨格となるわけで、各間接部の装甲の動きが柔軟になり、より人間的な動作を実現し、機体強度や機動性もより高次元なものになった。
このムーバブルフレームの技術を応用したのが可変MSである。トランスフォーマブルMS(以下TMS)は、一年戦争時にMSよりも戦闘能力を先鋭化させたMA(モビルアーマー)と、MSとしての本来の能力を合わせ持たせるというコンセプトで開発された。
MSは高い汎用性を有するが、それが故に戦闘能力と巡行能力に限界があった。それをMA形態に変形することで解決しようとしたのである。一年戦争時代は、ドダイやGアーマーなどといった支援航空機で巡行能力を補っていたが、より円滑に行動するにはMSに可変能力を盛り込んだ方が、様々な面でメリットの方が多いのだ。
この考え方自体は一年戦争当時からあったものの、強度や重量の面で技術が熟成されておらず、駄作しか製作できなかった。ムーバブルフレームがなければ実現されなかったと言われる由縁もここにある。
この時期、U.C0087年前後は、連邦軍が盛んにMSを開発していただけに、どれが初のTMSかは明言できない。しかし、一年戦争時に連邦軍が開発したRX-78GT-FOURが起源となったのは確かだろう。
さて、MSZ-006Zガンダムは、この時期において最も成功したTMSである。
追加装備をする必要もなく、単体で大気圏突入能力を持ったZガンダムは、TMSの意義を完璧なまでに具現化した機体である。
この後、TMSは可変をさらに推し進め、数機が合体してMSに変形する機体まで誕生した。
だが、変形機構に合体機構まで組み込んだMSは極限まで複雑化し、もはや単にMSとは呼べなくなったと言っても良い状況だった。そして、コスト的な問題や、MSにそこまでの能力を望む必要があるのかといった声が上がるなどあり、僅か5年ほどでTMS全盛期は終わっている。
TMS誕生以後、20年ほどはMSそのものに革新と呼べる変化はなかった。強いて挙げれば、サイコ・コミュニケーション・システムを搭載したニュータイプ専用MSが造られるようになったこと位だろう。
ただし、機体を肥大化は急激に進行し、多くの武器を内包するようになった。
変革
MSが誕生して40年余り。様々な機能を内包し、恐竜的に大型化してきたMSも限界が近付いていた。
MSの大型化の要因となったのは、強力な火器を内蔵して単体での攻撃力を高めようとしたことだった。確かに、MSの高機動に高い攻撃力が加われば、最強の兵器となり得ただろうが、攻撃力の強化に気を取られるあまりに、機体は大型化し、機動性も低下していた。
ただし、それは限られた機種ではなく、MS全体が大型化し、機動性を低下させていた状況であったため、性能的には全くデメリットとはならなかった。
デメリットが出たのは、建造や整備を行う工場と、MSを搭載する艦艇についてであった。
MSが大型化すれば、当然その周辺設備も大型化を余儀なくされる。整備台などが大型化するくらいで済めばそれで良かったのだが、いずれは工場の建て直しや、新しく艦艇を建造する必要も出てくるだろうということは、誰もが容易に想像できた。それはコスト的に大きな負担となり、また無駄でもある。
さらに、MS一機の稼働に要する人員や、燃料消費量の増大といった問題も招き、もはやこれ以上の肥大化を見過ごすわけにはいかなくなっていた。
そこで連邦軍は、MSの小型化を提案した。
この時期の連邦軍は、内部でMSを開発できる余力はなく、全て外部の機関、企業に委託していた。
4 MSの分類
(1)大きさによる分類
MSを大きさで分類すると、MS、ミドルMS、プチMSなどに分けられる。
おおよその大きさは頭頂高で、一般的なMSが10~30m、ミドルMSが5~10m、プチMSが2~3m程度である。
(2)用途による分類
用途別に見ると、MSは戦闘用と作業用に大別される。
戦闘用は更に、汎用MS、用途限定MS、局地戦MSに大別され、用途限定MSには長距離支援用、偵察用、強襲用など戦術に応じた分類、局地戦MSは極寒地用、砂漠用、コロニー内専用など稼働地域による分類である。
作業用は一般的にMW(モビルワーカー)と呼ばれ、プチMSやミドルMSも含まれるが、MSクラスの大きさのMWもある。
(3)世代による分類
「第一期」と「第二期」に大別され、U.C100年代に入ってから行われたMSの小型化以降は>「第二期」に分類される。
「第一期」は第一世代から第五世代まであり、その概ねの基準は、第一世代がモノコックフレームのMS、第二世代がムーバブルフレームのMS、第三世代がTMS、第四世代がニュータイプ専用MS、第五世代がミノフスキークラフトを搭載したMSである。