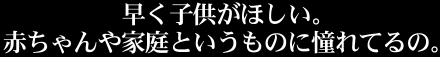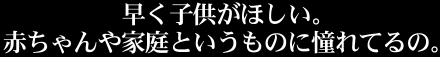|
-ではまず、みんなが知りたがっている質問から。一体ヴァネッサ・パラディとは何者なんでしょう?誘惑のロリータ、シャネルのベビードール、それとも白馬の王子を夢見る少女?
どれも当たっているわ!でも本当はね、意外だと思われるかもしれないけど、わたしは臆病で内気なの。傷つけられるんじゃないか、失敗するんじゃないかって怖がっているような人間よ。たとえば、セルジュ・ゲンズブールに初めて会ったときも、怖くって緊張していたの。彼のことは前から大好きだったから、『あのすごい人がここにいる。あの人がわたしなんかに興味を持ってくれるかしら?』なんて心配していたのよ。でも、その後一緒に食事をしたり、電話で話したり、他愛もないことで笑い合ったり、とてもいい関係ができたわ。もちろん、わたしたちが深い仲だとか、わたしが有名になるために色仕掛けをしたとかいろんなことを言いふらした人もいて、それで結構傷ついたけど。でも今ではそんな中傷に対しても、言いたい人には言わせておけばいいと冷静に思えるようになったから、前ほど苦しまない。もちろん白馬の王子様を夢見ているわよ。でもそれ以上に赤ちゃんや家庭というものに憧れているの。ただ、赤ちゃんの父親となるべき人がまだ見つからなくて…。
-どんな子供時代を送ったんですか。
素晴らしい両親の下で素晴らしい子供時代を送ったわ。かわいい妹もいてね。両親は特殊なプラスチック化合物の建材を販売してるの。ふたりはいつもわたしのこと、わたしの成功を信じて、支えてくれた。ジャン=クロード・ブリソーの『白い婚礼』に出演したときも、母が精神的に支えてくれたの。サン・エチエンヌの街も陰気な雰囲気で、わたしにとっては孤独で苦しい撮影だった。あの映画でセザール賞を貰ったけど、わたしには嫌な思い出しか残ってないわ。ブリソーはわたしのことなんて信頼してなくて、スタッフの前でもわたしを人間以下に扱った。わたしをバカにして、侮辱したの。わたしと口をきいてくれる人さえいなっかたわ。そりゃ、あのときのわたしはとても女優と呼べるものじゃなかったかもしれないけど、それだからって売女以下に扱っていい理由にはならないでしょ。母はわたしの苦悩を知って会いに来てくれて、優しく励ましてくれたの。『わたしのかわいいベベ、だいじょうぶだから、すべてうまくいくから』って。お金が入るようになってから、クーペ型だか、カブリオーレ型だか、ベンツの最新モデルのすごくかっこいいのを両親に買ってあげたわ。アメリカから半年ぶりに帰って来たときも、妹にたくさんお土産を買って来た。彼女のことは大切に思っているの。ヴァネッサ・パラディの妹というだけで辛い思いをさせてるし。
-どうして?
学校でもわたしのことで意地の悪いことをよく言われるららしいわ。パリの両親の家の近所にも『ヴァネッサ=あばずれ』なんて落書きをされたの。小さな娘にとってはこんな根拠のない中傷は耐えられないことよ。
-あなたも突然もたらされた成功によって辛い思いをしたんでしょうか。普通の女の子の青春というのがなくなってしまって。
わたしにだって青春はあったわ。それに別にこうなる前から大人と関わって生きてきてるわけだし。大人といるのは好きじゃないけど、かと言って、学校といった枠組みや、そういう環境から飛び出してやるという考えも好きじゃなかった。そんなのばからしいと思ってたもの。
-半年ほどアメリカに滞在したそうですが、フランスの家族から遠く離れて暮らすのは大変じゃなかったですか。
確かにそうね。でもわたしの場合家族との絆がとても強いから。わたしが落ち込んで支えが必要なときにはいつも両親がいてくれた。でも17歳からは独立して暮らしていたのよ。アメリカでは叔父も一緒だったし。叔父は俳優なんだけど、わたしのマネージャーでもあるの。それに今はファクスの時代だもの。もちろんフランスから遠く離れて辛かったけど、この国のしつこくて意地悪な人たちの目から逃れて、自由に街を歩くことができて嬉しかったわ。
-あなたにとって海の向こうの異郷に行くということは、そんなに重要だったんですか。
そう。いろんな意味でね。仕事の面でも必然的に。レニー・クラヴィッツとはとても自然な雰囲気の中で仕事ができたわ。彼は大好きなミュージシャンだったから、まさか一緒に仕事をする日がくるなんて思ってもみなかった。個人的な意味でもこれは重要だったのよ。ラディカルに変化しなければ、わたしは成熟することもできなかったし、ブルース魂に目覚めることもなかったわけ。
-そのアメリカという遠く離れた場所で、辛く寂しいときには、どうしていたんですか。
そうね、みんなそうだと思うけど、寂しくなって落ち込んだときには、頭を抱え込んで、目の前が真っ暗になって、ただただ泣くの。苦痛や苦悩にひとりで耐えて、何時間も悲しい音楽を聴いて…。その後に友だちや母に電話して、お喋りするのよ、長いこと。そうしたら、かなり元気になるの。
-あなたを値踏みするかのようなフランスでの受け止められ方、そんな人気をふりきるためのアメリカ長期滞在だったのでしょうか。
ううん、そんなこともないけど。でも確かにフランスにいると、時々はツアーをしたり、毎度同じことを繰り返すだけのテレビのバラエティー・ショーにも出演しなきゃいけないのよね。でも人生は素晴らしい出会いがあってこそ楽しいものでしょ。新たな出会い、今までと違う生活、異文化――それを自分でも求めていたんだと思う。でもみんなが言ってるみたいに、わたしがアメリカの市場征服を狙っているのは嘘よ。
-アメリカではアパートを買ったんですか。
まさか、そんなこと。わたしはシンプルで地味な女の子なのよ!アパートを借りて満足してた。LAで3カ月、NYでも3カ月、セントラル・パークの真ん中のアパートを借りてたの。
-レニー・クラヴィッツにはあなたからコンタクトしたのですか、それとも彼の方から?
わたしのレコード会社が初の英語アルバムを出そうとアメリカ人のプロデューサーを探してたのが始まりで、確か'91年だったかしら。レニーの名前が上がったときには信じられなかったわ。彼の大ファンで、アルバムも全部聴いてたんだから。ラッキーだったのね。彼のパリ公演の際に、マネージャーが彼とわたしをスタジオで引き合わせたんだけど、わたしはもう舞い上がってしまって、話せない、目も合わせられない状態でね。で、翌日彼が夕食に招待してくれて、そこで初めて打ち解けて話せたの。あらゆることについて話したわ、音楽はもちろん、人生や恋愛についても。それでお互いに一緒に仕事をしたいと思ったわけ。
-パリで?
ううん、LAで。その後NYで再度合流して、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのカバー曲をやってみたの。去年の6月頃よ。8月にはレニーがわたしのために曲を書き始めてくれて。わたしがいることを喜んでくれてるみたいだったから、わたしも彼の側にいようと…。
-あなたとレニーの関係は仕事以上のものであると言われてますけど――。
ええ、恋の話しだってしたわよ。ほんとにあらゆることをね。自然だったの。黒人と白人の恋物語とか…すてきでしょ。でもすべてばかばかしいお遊びなの。どうして男女の間柄というとみんなすぐに肉体関係があると思いたがるのかしら?お互いの仕事に敬意を持って、お互いに尊敬と親愛の感情を持っていれば、単なる仕事以上の付き合いと言えるでしょ。特に気に入ったわけでもない相手と寝てしまう友だちも確かにいるわ。でもわたしの場合は友だちの大部分が男の人だというだけなのに、わたしがベッドの中で何から何までやっているってことになるのよ。レニーのことはとても親密に感じているし、わたしたちの間にはいい関係が出来上がっている。でもいろんな嘘を言いふらしたり悪口を言ったりする人たちは許せないわね。だってそういう人に言わせると、わたしたちに恋愛関係があったってことになるんでしょ。
-アメリカでも有名になったという実感はありましたか。
まだアメリカではスターだとは言えないわ。でもね、アメリカに行った目的はそれだけじゃなかったの。英語のブラッシュ・アップもしたし、アメリカ式の仕事のやり方というのも学んだし、わたしの成長を促してくれるような人たちにも出会った。それが一番大切なことね。
-最近成長という言葉をよく口にしていますけど、あなた自身の中に大きな変化があったわけですか。
そうね、成長したし、成熟したとも思うわ。素晴らしいことよ。でも、それって当然のことだと思わない?ただわたしの本質的な部分は変わってないと断言できる。成功がわたしを変えたりはしてないって。変わったのは周りの人たちの方よ。わたしはいまだにシンプルな人間で、みんなが言ってるような思い上がった人間じゃない。だってわたしを取り巻いてくれているのは監視兵や寄生虫みたいな人じゃなくって、わたしを信頼してくれてる人たちなの。そういう人たちとめぐり合うこと自体簡単じゃないのよ。本当に喜び、苦しみを分かち合える人は、家族と数人の友人だけ。そんな人たちのおかげでわたしもうまくバランスが取れてるの。
-今後の活動についてのプランは?
何も決めてない。すべて計画しちゃうなんて怖くない?27歳でこれをする、37歳であれをするなんてとんでもないわ。そんなことしてたら、すぐに年を取ってしまいそう。わたしは自分で現在の成功もコントロールしてるし、わたしを応援してくれるファンの人たちのことだって考えてるわ。4月にはパリのオリンピアでコンサートもするし。でも、万が一明日すべてが終わったとしても、わたしにはすてきな思い出がたくさんあるから後悔なんてしない。さっきも言ったけど、今のわたしは仕事よりも家庭を持つことに憧れているの。
-あなたは'89年の『白い婚礼』でロミー・シュナイダー賞とセザールの新人賞を獲ったわけですが、次の映画の企画はないんですか。
今のところはないわ。アメリカとフランスでアルバム『ビー・マイ・ベイビー』のプロモーション活動をするので手一杯よ。アーティストとして同時にいろんなことに手を出すのは良くないと思うの。シナリオを読んでみて、わたしが気に入ったものがあれば話は別だけど。自分で作り上げていくような役柄、本当のキャラクターというのを演じてみたいわ――もう辛い思いはしたくない。どうしても演じてみたい役があれば、映画に出ることもあるかもしれない…。でもわたしの方も望まれた形での出演でないと嫌だわ。ひとつ言っておきたいんだけど、わたしはこれまでごまかしなんでしたことはないし、そんなこと考えたこともなかった。つまり、自分でやりたいと思ったことしかやってこなかった。仕方なく義務的にやったことなんてないわ。お金も十分稼いだし、銀行に貯金がいくらあるかなんて気にしない。そういう面倒は母がみてくれているからすべてうまくいってるの。お金の亡者になることもないのよ。もちろん、お金があるからこそこんなことも言えるっていうのはよくわかってる。でも、本当にわたしは自分の好きなことしかやらない。すきな人と一緒なら一生懸命働くわよ。仕事も、ハートも、才能も素晴らしいと思える人たち、これでいくらお金が貰えるかなんて気にしない人たち――そんな人たちと一緒に働くところに喜びが生まれると思うの。そうやってわたしは毎日を生きているのよ。
-あなたがシャネルのイメージ・ガールとして登場したことに日本では驚きの反応があったのですが、あれはあなた自身も別人になった気分でしたか。
そりゃ、女らしければ女らしいほどいいだろうし、きれいならきれいなほどいいっていうのは当然よね。その方が説得力があるもの。でもどんな女の子でも化粧という魔法を使って自分を磨けば、生まれ変わることができる。それを否定する必要はないわ。わたしは特にきれいなわけじゃない、周りの人がきれいに仕立ててくれる――そういうことよ。自分ではいつもお尻が大きいなんて思ってたんだもの。わたしがシャネルのモデルをしたからってやっぱりわたしのお尻は大きいままよ。ああいう写真って、ある意味では映画の1シーンみたいなものなのよ。ただ、実際のわたしは金ラメだらけの人間じゃないから、ああいう超ソフィスティケートされた世界とは正反対の生活を送ってると思う。
―最後に、ヴァネッサ・パラディにとって'92年はどんな年だったのでしょうか。
いい年だったわ、本当に。今後2、3年分の計画が今頭の中にいっぱい詰まってるの。でもそれがすんだら、今度は喜んで次の新しい役柄に挑戦しようと思ってる。母親という役柄にね。本当に早いうちに子供がほしいの。
|