Review
2006

Donald Fagen / Morph The Cat
フェイゲンの新譜が、「密林」より到着しました。
発売が20日過ぎになる?云々のメールは一体なんだったんでしょうか。
欧州盤と米国盤とで、その辺の情報が錯綜してたのでしょうか。
ま、とにかく、メールでのリリースよりも早く到着したのは何よりです。
で早速聞いてみましたが、なかなか好印象でした。
どこを切っても、フェイゲン濃度の濃い、本物感の強い直球のアダルト・コンテンポラリー。
やや軽めな印象のあった「カマキリアド」よりも、ジャケの雰囲気の近い「ナイトフライ」寄りのサウンドでしょうか。
昼の「カマキリ」夜の「猫」という感じ?
ま、「ナイトフライ」ほど印象的なナンバーが多いわけではないですが、
それでもシングルカット曲の「Hギャング」などは、数回聞いただけで、「サビ」をふと口ずさんでしまいます。
スティーリー・ダンの近作との違いは、いい意味でSDほど作りこまず、よりストレートにフェイゲンの好みである
R&Bやジャズのエッセンスを反映させてる感じがしました。
あと、前作では、SDのベッカーが全編ベースを弾いてましたが、
今作は、LAよりフレディ・ワシントンを招いてますが、これが正解、正解。
スティングなんかにも呼ばれたりして、若手ドラマーの成長株であるキース・カーロックとのナチュラルなグルーヴは、
フェイゲンのフロートしたメロデイを上手く下支えしてて、サウンド全体に適度な重厚感を持たせてます。
正直、「ガウチョ」以降のSDやフェイゲンのサウンドというのは、
70年代の全盛期の音を自らでコピーしてるだけの印象があっていまいち入り込めませんでしたが、これは、そんな印象が少なく、
ひたすら、フェイゲンの個人的趣味をいい形で強く反映させた本物の大人のポップスとして長く楽しめそうな作品ですね。
70年代のSDのファンや「ナイトフライ」からフェイゲンを知るファンには、
間違いなく即買いでしょうが、SDやフェイゲンをあまり知らない若いファンは、
何は無くともまず「ナイトフライ」を聞いてから、本作を聞くことをお薦めです。
本作だけを聞くと、フェイゲンを知らない人なら、なんとなく中途半端な印象を
持つ人もいると思いますが、「ナイトフライ」を先に聞いて、その「印象のエコー」
の中で、これを聴くと、また違った印象になると思いますんで。
ソロ2作目の「カマキリアド」は、ま、一番最後でもいいと思います、「スノウバウンド」とか良い曲も入ってて決して悪くはないんだけど、
どうもドナルド・フェイゲンらしい「オーラ」がいまいち出てない気がするもんで。。。

Greg Mathieson / Another Night At The Baked Potato
グレッグ・マシソン率いる「The Jazz Ministry」の2005年に勿論、LA、ベイクドポテトで
録音された2枚組みライブ盤が、3月にグレッグの自主制作盤として発売されてるようです。
1週間ほど前に、その情報を仕入れて早速、サイトからオーダー、で一昨日、到着しました。
2000年には、グレッグ、マイク・ランドゥ、エイブ・ラボリエル、ヴィニー・カリウタの
「Dyna Four」で同じような形態の作品をリリースしてましたが、まぁ、それの続編のような感じで、
今回は、「The Jazz Ministry」、ジャズ内閣とでも言うんでしょうか?
まぁ、少々大袈裟な感じもしないではないですが、、、で、「Dyna Four」と何が違うのか?
といえば、ドラムがヴィニーではなく、エイブの息子になってること。
ヴィニーの不参加ということで、テンションが下がってる人も多いかと思いますが、なかなかどうして、エイブの息子のタイコも相当なものです。
最近では、ポール・マカートニーにも雇われてるとか?の実力派で、親父譲りの豪快な体型(苦笑)から繰り出す
ヘビーでロックテイストなりズムは、かなりカッコいい。
マイク・ランドゥと、ハードロックバンドを結成してたというだけあって、彼とのコンビネーションもいい。
「Dyna Four」は、ややメンツの割りには大人しい印象のあったサウンドですが、
タイコに若いエイブ,Jr.が入ったことで、いい意味でのドスドスしたロック色が増して若返った印象です。
演奏ナンバーも、「ベイクドポテト・スーパーライブ」時代からの「I Don't Know」などの
お馴染みのナンバー中心ですが、昨年リリースされたグレッグのソロ作やグレッグ&エイブのデュオ作に収録されてた
「QTπ」などが新しくライブバージョンとしてパフォームされてるあたりが目新しい。
また相変らず曲の長さもさすがライブ盤、それも自主制作ということで、編集なしの
超ロングなもので、短いもので7分ちょい、一番長いもので19分もあり、ベイクドポテトの日常をお腹一杯楽しめます。
グレッグのサイトだけでなく、HMVのサイトでも限定入荷とかで、入手可能です。
送料込みで、日本円で約4000円ちょっととややお高い気もしますが、その筋のファンは、やはり、必聴アイテムでしょう。
※2006.12.18 現在 HMVでは廃盤扱いで、グレッグの個人サイトも何故かアクセス不能? タワーレコードの通販では入手可能らしい。

渡辺貞夫 / One For You - Sadao & Bona Live
先日、HMVにオーダーしてましたナベサダの最新作のライブ盤「ワン・フォー・ユー」が到着しました。
「サダオ2000」や「ホイールズ・オブ・ラブ」などと同様に、リチャード・ボナとの共演なんですが、スタジオ作以上にいいですね。
ボナ、タウンスレーというリズムと、今や貞夫さんの腹心とも言うべき、絶対の信頼を置く
セネガルの打楽器奏者、ンジャ・セ・ニャンが織り成す、ボーダレスな地球のビートとも言うべき
ビートは、貞夫さんのナチュラルなアルトを懐深く抱き込んでいます。
ボナのベースも、ライブということと、彼自身が、深くトリビュートする貞夫さんとの共演ということで、
かなり、アクティヴな印象ですが、決して、尊敬する貞夫さんのサウンドを邪魔するのではなく、
音楽で会話してるような心地よい雰囲気が伝わるものです。
貞夫さんのアルトですが、このライブではかなりリラックスした雰囲気ですが、
今年4月のベイシーでのライブソースを聴くと、年齢を感じさせないアグレッシヴなパフォーマンスも披露してますので、
ボナとの交友を温めるという方向性からそういう演奏スタイルになっているのでしょうが、
もう少し、熱い部分もあっても良かったかな?とも思います。
とはいえ、本作は、21世紀に入ってからの貞夫さんのオリジナル作としては、
最高のものだと思いますので、貞夫ファン、ボナファンとも必帯の1枚です。

Christian McBride / Live At Tonic
いや~これ、凄いっすね、マジで。
レイ・ブラウンの正式継承者みたいなイメージの優等生的な印象もあったマクブライドですが、
いい意味で、ブチ切れてますね。
マクブライドのベースに火を着けたのは、ドラムのTerron Gullyですね。
重量感がありながら、スコン、スコン、とファンキー&グルーヴィーにキメられる凄いドラマーですね。
クセモノのチャーリー・ハンターや、ジェイソン・モランの使い方も上手いし。
ここ2作ほどの、マクブライドのソロ作は、初期のウェザーリポートのサウンドを
下敷きにしたようなもので、やりたいことは分かるけど、いまいち、煮詰めきらないというか
サウンドの焦点がややボケた感じで、そんなに良い印象は無かったんですが、
「ジャムバンド系」のミュージシャンやエッセンス、スピリットを入れることで、完全に突き抜けました。
いや~これは本当にカッコいいジャズです。
こういうサウンドを自然体でパフォーム出来るミュージシャンがいる限り、まだまだジャズという音楽も安泰だと思いました。

Ian
Hunter / All American Alien Boy
ジャコの数少ない「ロック」系セッション作として有名な
英国のロックシンガー、イアン・ハンターの「All American Alien Boy」が
6曲のボーナストラックが追加され、欧州プレス盤としてリイシューされました。
密林日本で、1600円ほどと、安かったので、ぶっちゃけ、ジャコ目当てで、オーダーし聴いてました。
このイアン・ハンターという人ですが、何でも、「モット・ザ・フープル」という
バンドの人らしく、あのクイーンも、このバンドの前座!?をしてたこともある?!という
ことですが、そっち系のにはあんまり詳しくないので、この程度しか・・・。
その「よしみ」からか?1曲、クイーンから、フレディとブライアン・メイが、バックヴォーカルで参加してるものもあります。
どっかに、「英国のボブ・ディラン」みたいな表現がありましたが、
歌い方とかは、確かにそんな感じの「下手ウマ系」、サウンドも言われてみればなるほど・・・。
アフロな「HG」みたいなジャケから想像するような硬派なロックというよりも、
英国の人があえて米国で録音するという企画なんで、R&Bとかゴスペルとかのフレーバーが
強く、だから、ジャコやデヴィット・サンボーンがほぼ全編で録音に呼ばれたのでしょう。
本作の影の本丸、ジャコですが、1曲、タイトル曲で、ソロを聴かせてくれてますが、
表面的には、そう派手なものではなく、グルーヴを大切にしたシンプルな演奏に徹してます。
とはいえ、それで、ツマランのか?といわれれば、決して、そんなことはなく、芳醇で、
包容力のあるジャコのベースと、「ニセ・ボブ・ディラン」(ファンの人、すんまそん・・・)みたいな歌との、組み合わせはなかなか面白いです。
あと、ジャコ以上に、ハマってるのは、サンボーンのアルト。
ファンキーな曲では、デヴィット・ボウイの「ヤング・アメリカンズ」でのソロみたいだし、ゴスペルチックな曲では、十八番の「泣き」が炸裂。
ジャコマニアでは、かなり、有名な本作ですが、実は、コレ、サンボーンマニアにも必聴では?と思います。
他に、ドン・アライアスやらコーネル・デュプリーなんかも参加してます。
本作は、76年作、ということは、ジャコのファーストソロ作と同じ年。
で、ライナーの最後には、直接、プロデュースやらを手がけてるわけではないけど、制作に協力した?みたいな表現で、
ボビー・コロンビエーの名前が。
なるほど、彼はジャコのファースト作のプロデューサーでもあるわけで、そんな縁からここにジャコがいるのでしょう。
その後、ジャコは、天気予報などでの大活躍で一躍大スターになり、
このような「お仕事」的なセッションには、あまり参加することはありませんでしたので、
シンプルなバッキングに徹したジャコが聴ける作品として、珍重されたのも、うなずけますね。
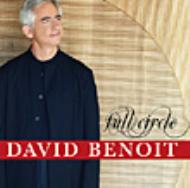
David Benoit / Full Circle
昨日、久々にマルビルのタワレコに行きましたが、
その店頭、1980円のセールだったんで、David Benoitの新譜「Full Circle」を購入しました。
米国盤に貼られてるシールに「return to his roots・・・」と書かれてるように、
80年代の「Freedom at Midnight」~「Urban Daydream」のような
雰囲気の生楽器主体のLAフュージョンで、「その筋」のファンには、かなり懐かしく楽しめる作品となってます。
そこここに散りばめられたブラジルやラテンの軽やかなムードが、
かなり湿度を下げてくれそうなクール&ドライなフュージョンサウンドのBenoitは、かなり久しぶり?
久々に、「Freedom~」や「Every Step Of The Way」などの名盤を
プロデュースしたJeffrey Weberとのリユニオンを果たし、彼制作のトラックでは、
John Robinson(ds) Nathan East(el-b) Brian Bromberg(ac-b) Paul Jacksobn,Jr.(g)
Oscar Castro Neves(ac-g)Luis Conte(perc)らによる、ライブ一発録り的なサウンドになっていて、かなり、気に入りました。
他には、Jeff LoberやPaul Brown制作のものもありますが、モロ打ち込みのようなサウンドではなく、
ある程度生楽器のライブ感を取り入れたものになってるので、安心です。
また、大仰なストリングスのようなものや、リチャード・クレイダーマン?みたいな
イージーリスニング的バラードは今回、封印されてるので、全編オケモノだった前作が
不満だった「LAフュージョン」なBenoit好き(私もそれです)には、直球、即打撃な作品です。
下のフランクスの新譜とともに、夏のBGMにもいい感じじゃないですか?

Michael Franks / Rendez-vous In Rio
マイケル・フランクスの新譜「ランデブー・イン・リオ」がリリースされました。
前作が、彼のイメージとは?な冬をテーマにした作品だったんで、
いまいちしっくりこなっかったというのが正直なところですが(音の方はアコースティックな
ボサっぽい感じで決して悪くはなかったんですが・・・)、今作は夏前のリリースということで、
テーマはタイトル通り「ブラジル」、フランクスの本領発揮!!。
音の方も、前作のようなアコースティックでジャズっぽいものではなく、ややコンテンポラリーでフュージョン的なものなんで、
AORやスムースジャズファンにも強くアピールできますね。
1曲目から、チャック・ローブの涼しげなガットギターによるボサっぽいリズムが心地いいこれぞマイケル・フランクス!
みたいなサウンドが登場。
2曲目のタイトル曲は、現在のツアーバンドのメンバー中心の演奏で、サンバフュージョンな心地よいナンバー、
FOしてゆくクリス・ハンターのソプラノソロも良い、
4曲目の「ソーホーのサンバ」も、蒸し暑い気温を2~3度下げてくれそうなクールでブリージンな雰囲気・・・。
他にも、AORの名手ロビー・デュプリー」が参加したものや、ジェフ・ローバーが手がけたスムースジャズ的なものなどもあり、
ボサっぽいもの一辺倒じゃなく、適度なサウンドの起伏もあり、作品通して飽きの来ないものになってます。
近年のフランクスの作品の中ではベストな出来です!
夏のBMGに大活躍しそうな良い作品です。

Branford Marsalis / Braggtown
ブランフォード・マルサリスの新譜「Braggtown」が到着しました。
Branford Marsalis (ts,ss) Joey Calderazzo (p) Eric Revis (b)Jeff “Tain” Watts (ds)
というお馴染みのレギュラーユニットによる最新スタジオ録音で、
近作は、コルトレーンモノなどの「企画モノ」が多かったですが、これは久々のオリジナル作です。
凄く楽しみにして聴いてみましたが・・・
また、何かこう袋小路に入り込んだような・・・吹っ切れない演奏・・・。
70分ちょいという結構なヴォリュームの作品なんですが、スルーで聴くのは、結構、キツかったです、正直なとこ。
コルトレーンやオーネット・・・などなどの断片が登場するオリジナル曲ばかりで、
ブランのサックスを含めた面子全員の演奏は、確かに凄いし、密度も濃いんですが、
演奏してる方のベクトルが凄く内向きというか内省的に感じて、演奏自体の良さが聴く者に伝わらない感じなんです。
演奏がなんかこう無機的なんですよ。
末期コロンビア時代も、そんな感じで、自身のレーベルであるマルサリス・ミュージックを起こしてからのブランは、
そんな状態から吹っ切れたていたのですが、また逆戻りしたよう?。
同時に購入した、ケニー・ギャレットやジョー・ロヴァーノの新譜がかなり面白かっただけに、
このブランのぶっちゃけ無茶苦茶「陰気」な作品には、がっかりしてしまいました。
もっと外向きのベクトルで勝負するために、いい意味でスティング時代や、
バックショット・ル・フォンクなんかの頃の心意気を思い出して欲しいですね。
別に演奏をもっとポップにしろという話ではなく、ジャズ本来持っているヒップさのようなものを
直感的に感じられるようなテイストが欲しいということです。
本作のような「音楽家の研究発表会」的なものは、聴いてて、やっぱり面白くないですよ。

Bruce Hibbard / Never Turnin Back
日本オンリー(苦笑)でAORの名盤で名高いブルース・ヒバードの80年の作品「Never Turnin Back」。
サウンドは、直球AORなんですが、CCM~コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージックとして
作られたものなんで、宗教というものにはどれも何かこう胡散臭さを覚えてしまう私には
そこがひっかかってたんですが、セコハンで安かったんで、買ってみました。
プロデュースは、コイノニアのギタリストとして知られるハドレー・ホッケンスミスで、
ビル・マックスウェル(ds)、ハーラン・ロジャース(key)も、サポートミュージシャンとして参加。
ブルース自身やハドレーもベースを弾くということで、コイノニアのリーダー、エイブの参加は無しというのはちょい残念ですが。
サウンドのほうですが、まさに、日本人好みのソフト&メロウな直球AOR。
80年代前後のAOR作品の中にちょいちょい入ってた、エアプレイやTOTOモドキな産業ロックモノは一切無し。
ひたすら、メロウグルーヴなAOR、AOR、AOR、やや頼りなさげなヴォーカルは、エリック・タッグのようでサウンドも、
彼の70年代後半のものにちょい近いけど、もっとポップで西海岸的。
タッグのサウンドにあったやや趣味的なものがなく、その分、80年代前後の歌謡曲やニューミュージック的な分かりやすさがあります。
そのあたりがやや「ベタ」に感じるところではありますが、いや~もっと早くちゃんと聴いとけばよかったですね!
本当に、気持ちいいサウンドです。
AORは夏のイメージですが、これは、カラカラの真夏というよりも、ちょいウェット感もあるんで、
春とか秋の季節のドライブミュージックにぴったり?。もう10回近く、延々と聞いてても、飽きません。
ヒバードのソングライトの優秀さもさることながら、ハドレーを中心にしたコイノニア一味のバックのサウンドが
しっかりしていることもその大きな要因だと思います。
新品でも、クールサウンド盤で入手できるので、ソフト系のAORの好きな人は、是非、聞いてみてください。
元「ポパイ」や「ブルータス」なおぢさんには「ドキューン」な音なんですが、
今の10代や20代前半の人にはどう感じるんですかねぇ~、この手の音は。蛇足ながら、その辺にも凄く興味があるんですが。。。

George Benson & Al Jarreau
/ Givin’ It Up
今日、ジョージ・ベンソン&アル・ジャロウの初コラボ作「ギヴィン・イット・アップ」が、到着しました。
まず、CDケースが、プラ製の「ジュエルケース」なんですが、四隅の角が丸くなってる新しい?ものだったのには少々びっくり。
二人のコラボ作が出るという情報を入手して以来、延々と楽しみにしてた作品だったので、到着後、即開封、CDトレイに載せ、プレイ。
1曲目は、ジャロウが歌詞をつけて「歌モノ」にした「ブリージン」。
元シーウィンドのラリー・ウィリアムスがアレンジを施したとのクレジットですが、これが当たり前ながら、無茶苦茶イイ!気持ちイイ!!
ベンソンバージョンのオリジナルのテンポや雰囲気を上手く活かしつつ、微妙に転調させるなどの小技が効いた素晴らしいもの。
ジャロウの軽妙な歌詞に、ベンソンのギターが寄り添うようについてゆく展開。
印象的なあのメロディをベンソンのギター&スキャットで演ったパートもイイ。
エイブ・ラボリエル=ヴィニー・カリウタのシュアなグルーヴも最高。
曲半ばのブレイク部分の最後に「チラッ」と演ったエイブの「フラメンコギター」なフィルもカッコいい。
ここまでベンソン版の原曲を活かしつつ素晴らしいアレンジが出来たんだから、
もうひとひねりして、作曲者のボビー・ウーマックに、本当のオリジナルバージョンの
ガボール・ザボ盤のようなリズムギターを弾かせるというのはどうでしょうか。
蛇足ながら、ガボールは、故人なんで、「イタコ」でも使わん限り無理ですが。。。
本作のオープナーにして、本作の「大当たり」は「ベタ」で恐縮ですが、やっぱりコレ?
2曲目は、1曲目の「逆バージョン」。
ジャロウの「モーニン」をベンソンのギターをメインにリメイクしたもの。
こっちは、「ブリージン」よりもやや今の「スムースジャズ」的なアレンジで悪くはないけど、1曲目と較べると、若干、軽すぎ?
3曲目は、マイルスの「TUTU」に、ジャロウが歌をつけたもの。
この曲の作者であるマーカス・ミラーも、アレンジとベースで参加。
マイルスバージョンほど、「ドス」の効いたものではなく、
この曲のもってる「ブルース感」を強調したもので、ベンソンのジャジーなギターと
ハービー・ハンコックのクールなアコピソロもフィーチャー。
マーカスは、ほとんど原曲のようなスラップをやらず、渋く「縁の下の力持ち」状態。
ドラムは、マイルスの縁者?らしいマイケル・ホワイト。
4曲目は、ジャズスタンダード「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」
新人ヴォーカリストのジル・スコットとベンソン、ジャロウの三つ巴。
ダークに成り過ぎないスムースなブルース感が良い。リズムは、マーカス=カリウタ。
5曲目は、シールズ&クロフツのポップヒットカバー「サマーブリーズ」。
1曲目の「ブリージン」と並んで、かなり気に入ったトラック?
と思ってクレジットを見ると、これも、ラリー・ウィリアムスのアレンジだった。
ベンソン&ジャロウのヴォーカルの「ハモリ」の響きが最高。
また、ソロパートの分担も、それぞれのキャラを上手く活かしてる。
この曲のリズムも、4曲目同様、マーカス=カリウタ。
しかし、今作でのマーカス、いつもの「ギラギラスラップ」を期待すると完全に「肩透かし」を食らうほど、
地味というかシュアというか、歌伴のお手本の如くボトムのラインをしっかり締めることに専念してる。
今年の「東京ジャズ2006」の演奏も、そういうものが多かったから、芸風を少し変えてきてるのかな?マーカス君。
6曲目は、ジャロウ抜き、ベンソンのアコギ&歌メインによるバラードの小品。
7曲目も、ジャロウはバックヴォーカルというかコーラスに徹し、
ベンソンのギターをフィーチャーしたミディアムなメロウフュージョン。
本作全体にいえるけど、ベンソンのギターが、ポップスター化のきっかけになった80年の「ギヴ・ミー・ザ・ナイト」よりも前、
出世作「ブリージン」~「リヴィン・インサイド・ユア・ラブ」あたりまでの雰囲気というか風合いが感じられて、
個人的には、かなり気に入ってるところ。
この曲も、「リヴィン~」あたり入っててもおかしくないようなもの。
「ハモリ」のサックスは、マリオン・メドゥウス。
8曲目は、6曲目~7曲目の逆パターン。
ジャロウの歌とゲストのパティ・オースティンとのデュオがメインで、ベンソンは渋くギターでオブリガードをつける展開。
80年代の有名ブラコンプロデューサー/鍵盤弾きのバリー・イーストモンドとジャロウのペンによる都会的なバラード。
スティングバンド入りで、「確変」したペット奏者クリス・ボッティもフィーチャー。これも、リズムは、マーカスとカリウタ。
9曲目は、ジャロウと、ソロアルバムも何枚か出してて、EW&Fなんかにも参加してた西海岸の鍵盤奏者フレディ・ラヴェルの共作。
本作中、一番コンテンポラリーというかブラコンというかポップというかそんな感じのミディアムナンバーでアルバムタイトルナンバー。
これだけが、ギター以外がほとんど打ち込みで、ジャロウの歌がメイン。
悪い曲じゃないけど、なんかこれだけ、アルバム全体では浮いた感じがしなくもなく少し古臭い?
サイドギターは、ベンソンバンドのマイケル・オニール。
10曲目は、ホール&オーツというよりも、ポール・ヤングのカヴァーといったほうが分かりやすい「エヴリ・タイム・ユー・ゴー・アウェイ」。
ここまで聴いて気付いたけど、6~7が「ベンソンタイム」8~9が「ジャロウタイム」
でここからまた、二人のコラボタイムということだったのねん。。。
これも、「ブリージン」「サマー・ブリーズ」同様、かなり良いカヴァー。またまたこれも、ラリーのアレンジ!。
ディーン・パークスと、マイケル・トンプソンのアコースティックなリズムギターを
活かしたややフォーキーなアレンジが、ベンソンとジャロウの歌と原曲のよさを上手く引き出してる。
安っぽいスムースジャズやブラコンみたいなアレンジにしなかったのは大正解!。
マーカス、カリウタのリズムに、ダ・コスタの打楽器の伴奏もヨイ。
11曲目から、ややジャジーなゾーンに突入。
でまずは、マイルスの50年代の名曲にヴォーカリーズの名手ジョン・ヘンドリックスが歌詞をつけたもの。
フォープレイなんかも最近、好んでこの曲、演ってますね、スタンダードには、何かこう流行廃りのようなものがありますなぁ。
スタンリー・クラーク=ヴィニー・カリウタ=パトリース・ラッシェンのトリオが、ベンソン&ジャロウをスウィンギーにサポート。
ジャロウの小粋というか軽妙なスキャット、ベンソンの正調ジャズギターも渋カッコいい。
特に、ジャロウのスキャット、「スペイン」みたいにデコに青筋立ててやるものは、
やや「引いて」しまうところがあるけど、こんないい意味で軽いヤツはやっぱりいいなぁ。
12曲目は、オルガンが効いたアーシーなR&Bスタイルなジャロウのオリジナル。
都会的なものだけでなく、ベンソンのギターはこういうスタイルのものも実は上手い。
リズムは、結構レア?なスタンリー・クラークとヴィニー・カリウタ。
久しぶりに新譜レビュー、それも、全曲っつーのをやったなぁ。。。
ま、それだけ、本作に対する期待が大きく、聴いたあとも、その期待を裏切ることのない優れたものだったということ。
逆に言うと、最近の新譜系にいいものが少ないということですが。。。
でラストは、本作の結構な「売り」になってるポール・マカートニー参加による
サム・クックのカヴァー「ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー」。
これも、ややアーシーでゴスペルな雰囲気。
80年代、ベンソンバンドのディレクターをやってたランディ・ワルドマンが弾くピアノがレトロなR&Bテイスト。
後半、ゴスペルチックなコーラスが盛り上がりテンポアップしつつ、フェードアウト。
ポールの歌は、ま、歌ってるなぁ、、、程度。
宣伝で、「たまたま横のスタジオにいたポールが本作の録音にハプニングで参加云々・・・」といわれてるけど、多分、嘘だと思う。
ベンソンやジャロウクラスでも相当な権利関係とかギャラ関係などがうるさいのに、
ポールクラスのワールドスターが、その辺を後回しにして、録音をしてく訳がない。
もちろん、ブラックミュージックに対し高い畏敬の念を持つポールが、
率先してゲスト参加したということは容易に想像できるけど、それ相当なビジネス上の根回しが無いと、無理な話だったと思う。
そんな感じで、この作品、マジでいいです、マジで。
ベンソン、ジャロウのファンは当然としても、すべてのジャズ~フュージョンファン、
いやR&Bファンにも拡げていいです、買って損はありません。
もうそろそろ、「今年のベスト3」は?みたいな話も出る頃になりましたが、これは絶対その中の1枚に入ること間違いありません。
■2006年Best3

Mark
Egan / As We Speak
初代P.M.G.やエレメンツ、ギルのマンディ・ナイト・オーケストラなどで活躍した
ベース奏者、マーク・イーガンの新作がリリースされました。
ドラムは、PMG時代からの盟友、ダニー・ゴットリーヴ、ギターに、ちょっとサプライズ?!な
ジョン・アバークロンビーを率いたトリオのよる作品で、2枚組みの大作です。
前作からイーガンのソロ作は、彼自身の主宰するレーベルから発表していて、
今作もいまのところ、入手方法は、彼のウェブサイトから購入するしかないようです。
注文から約10日ほどで、到着しましたが、新作のプロモ用のハガキに書かれた直筆サインがオマケで入ってました。
「ボワ~ン」としたイーガン独特のエフェクトによるフレットレスベースが奏でる
4ビートのリズムやメロディラインと、アバークロンビーのセンシティティヴな軟体動物系
ジャズギターが実にマッチしてるんですね。
ベースとギターが、表裏一体となって、クールに盛り上がってゆくそのサウンド、かなり気持ちいいです。
いつになく、センシティヴで空間を活かしたドラムを弾いてるゴットリーヴも素晴らしい。
アバークロンビーのギタートリオといえば、マーク・ジョンソン=ピーター・アースキンを率いたECM時代のものが有名ですが、
ベースが電気ベースとはいえ、かなり、それに匹敵するほどの素晴らしさだと思います。
ECMといえば、本作にも、クールで研ぎ澄まされたみたいなそんな空気感も感じますね。
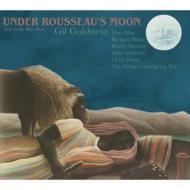
Gil Goldstein / Under Rousseau's Moon~Live at Blue Note
ギル・エヴァンスと同じ名前を持ち、彼のスピリットを今に伝える
NYのコンテンポラリージャズ界の頭脳ともいうべき、ギル・ゴールドスタインの新譜。
ドラムレス、3人編成の弦楽器入り、というユニークな編成で、
ジャコで有名なバードの「ドナ・リー」ジャコの「リバティ・シティ」「スリー・ビューズ・オブ・ア・シークレット」、
クールの誕生な「バップリシティ」「ムーンドリームス」のような曲を
ジャコ役?のリチャード・ボナや、ランディ・ブレッカー、クリス・ポッター、
マイク・マイニエリ、ドン・アライアスとライブパフォーマンス。
アレンジャーとしての力をアピールするユニークな編曲によるストリングスセクションと、
自身のアコーディオンやピアノ、それにゲストミュージシャンとのアンサンブルを聴かすことが目的のようなライブ。
なんで、ゲストがバリバリにソロをとるライブという期待をもって聴くとやや肩透かし?かも。
えっ?というアレンジのブレッカーブラザースの「サム・スカンク・ファンク」やマイニエリの「サラズ・タッチ」なども演奏、
そこで共演者を上手く立てる演出も面白い。
ドラムレスながらも、ドン・アライアスの打楽器(この人はドラマーでもあり自身のグループ、ストーン・アライアンスでは
ドラムを演奏)が活躍してるので、ドラムレスで弦入りということで、なにやらチェンバーミュージック的にもなりがちだけど、
心配御無用。残念ながら、このライブ演奏が、ドン・アライアス最期の録音になってしまったようです。
最後に蛇足ながら、もし、マイケル・ブレッカーが元気だったら、ポッターの代わりに参加してたかも?とふと考えてしまった。
■2006年Best3

Samantha Sang / The
Altimate Collection
70年代後半(確か77年?)、「サタデー・ナイト・フィーバー」で大ブレイクした
オーストラリア出身のビージーズのバリー・ギブとアンディ・ギブのペンによる「エモーション」という曲で、
全米大ヒットを飛ばした、ビージーズの同郷出身のシンガー、サマンサ・サングの全作品を2枚組みCDにまとめた作品。
彼女のウェブサイトや特別なアイテムを通販で扱うウェブショップ以外では、入手しにくいほぼプライベート盤。
とにかく、大ヒット曲「エモーション」が好きで、いろいろと彼女の作品を探したもののCDは勿論、アナログでもなかなか見つからん、、、
う~ん、、、、と長い年月が経過しましたが、今年初旬、AOR専門の某ネットショップで、本作を発見!!!
興奮しつつ即オーダーしゲットしたのが本作です。
1枚目のCDには、その「エモーション」と同時期で同傾向の曲がずらりで、ソフト&メロウグルーヴの極地ともいうべき珠玉のナンバーの連続。
フィリーソウルのデルフォニックスのカヴァー「ララは愛の言葉」、
ニュージャージーの甘茶系ソウルヴォーカルグループ、モーメンツがチョビヒットさせた「アイ・ドント・ワナ・ゴー」などのカヴァーも、
オリジナル同等か、それ以上のメロメロな素晴らしさ。
ただ、2枚目はといえば、前半こそ、70年代後半のディスコみたいなものもあれど、
中盤以降は、なんか安物ミュージカルの劇中歌のようなものが続いてて、「エモーション」的なソフト&メロウとはかけ離れた?なものですが、
ま、1枚目メインで、ボーナスCDが2枚目だと思えば、十分、十分。
このCDのマスターになったソースの多くは、ところどころに小さいながら入ってる「プチッ」でもわかるように、
どうやら、LP盤の様子、LPでも超レアなものなので、これはこれで納得しますが、その辺りに神経質な人には要注意。
■2006年Best3
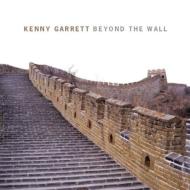
Kenny Garrett
"Beyond The Wall"
新録「純ジャズ」モノでベストだったのがコレ。
マッコイ・タイナーへの「捧げモノ」で、ジャケに「万里の長城」があるように中国にインスパイアされて作ったらしく、
「お経」?のようなそれ風の演出がちょこっとあるのはご愛嬌だが、
その辺を除くと、至極マジメな60年代後半風のソリッドなジャズの力作。
ケニーのアルトがここまで自由にまた伸びやかにまた豪快にブロウしてるのは、彼名義のソロアルバムの中では、一番だと感じた。
ファラオ・サンダース、ボビー・ハッチャーソンという60年代なベテランと、
マルグリュー・ミラー、ボブ・ハースト、ブライアン・ブレイドという中堅~若手による重量級リズムを組み合わせた化学変化のさせ方も見事。
重量感がありながら、それでいて、ギャレットの想いが駆け上がるような疾走感もある素晴らしいリアルタイムな本物のジャズ。
■2006年Best3+1
●基本的には掲示板に書き込んだものを一部加筆の上、転載しております。