Review
march

w/ Brian Blade(ds) Danilo Perez(p) Brad Mehldau(p) John Patitucci(b) Chris Potter (woodwinds) Terri Lynne Carrington(ds)
Alex Acuna(perc) etc,
ルーティンで作品を出す訳ではなく、「創りたい時に作る」ショーターの新作。
タイトルは、スペイン語で「喜び」らしいが、バックで薄っすら流れる木管楽器を活かしたホーンセクションや弦楽器の風合いは、
マイルスの「スケッチ・オブ・スペイン」の様。サウンド全般にもそんな感じが漂っている。
抽象的なメロディを持つものが多いものの、難解な感じはせず、何かの映画音楽を聴いている感じにさせてくれる。
喜怒哀楽を完璧に表現しきっているショーターのソプラノ&テナーは、見事、見事、素晴らしい!!!。
レギュラーユニットを中心に録音されているが、サポートミュージシャンの影は正直薄い。しかし、それはそれでいいのでは?。
ここには、ショーターの作り出す音楽空間があり、サポートするものは、それを構成するパートに過ぎないのだから。
人間の喜怒哀楽を表現するための即興演奏の要素では、きちんとジャズの語法を用いながら、古臭いジャズのスタイルに固執せず
独自の音空間創りを進めるショーターの2003年段階における最高のリザルトといえる作品。
(2003年3月7日)

Philippe Saisse Acoustique Trio featuring Kelli Sae “Ready To Go”
w/ Philippe Saisse(p,key) David Finck(b) Scoota Warner(ds) Kelli Sae(vo) Andy Snitzer(sax) Daniel Sadownick(perc)
80年代からのファンにしてみれば、シンセサイザー使いの名手的イメージがいまだ残るフランス、マルセイユ
出身のセスの新作。キラキラと硬質な輝きを発する彼のピアノに目をつけた日本の「アオシス・レーベル」が企画した
「アコースティック・トリオ」の第3弾は、ずばりグルーヴィーな「アシッド・ジャズ」。(古い・・・いや、懐かしい・・・)
インコグニートの新しい女性ヴォーカリストが参加し、11曲中7曲も歌ってる。
トリオ+ヴォーカルという形をとっているが、セスが、フェンダーローズやシンセサイザー類を上手くオーヴァーダビングして
バックトラックを作っているので、音の薄さは感じない。
「スコンスコン」とヒップホップ的なリズムが心地よくキマるワーナーのドラムとコントラバスで16ビートのウネりを作り出す
フィンクのリズムも気持ちいい。
インストは3曲だけだが、アンディ・スニッツァーのサックスをフィーチャーしたファンキーな4曲目を初め、アシッドジャズと流行のスムースジャズを
ミックスしたようなサウンドでカッコいい。
シャカ・カーンから、プリンス、ローリングストーンズに至る幅広いジャンルの人に信頼されてきたセスの音楽的センスが光る。
今まで知らなかったが、ピアニストとしては、リチャード・ティーにも大きな影響を受けたそうだが、なるほど、と思わせるファンキーなパートも
あったりする。
(2003年3月7日)

Christian McBride(b) “Vertical Vision”
w/ Ron Blake (soprano & tenor saxophones, flute) Geoffrey Keezer (piano, keyboards) David Gilmore (acoustic & electric guitar)
Terreon Gully (drums) Danny Sadownick (percussion)
マクブライド曰く、「アーリーフュージョン」がテーマの作品。
「アーリーフュージョン」とは、60年代終わりから70年代初期のクロスオーヴァーサウンドで、
具体的には、結成当初のウェザーリポートあたりをさすのだろう。作品のラストに、ザヴィヌル作の「ブギ・ウギ・ワルツ」をやってるので
多分そうなのだろう。
フレットレスベースを使った3曲目のバラードなどは、ジャコ時代のウェザーの様。ロン・ブレイクのサックスもショーターをコピ
ってるみたい。
良くも悪くも茫洋とした雰囲気は、確かに70年代初期を思わせる。
ウェザーファンでベースを少しかじってる私的には、面白いしカッコいいと思うけど、一般的に薦められる作品かといえば?。
やりたいことは解るが、サウンド全体の演出面があんまり出来ていない感じ。
ジョージ・デュークの最新作は、全編に渡ってマクブライドが参加しているが、その中のラストの曲での演奏が、ジャコのコピーそのもので
びっくりしたが、今のマクブライドの興味の中心は、そのあたりなのだろう。
ウェザー風?なサウンドメイクから開放され、メンバー全員が一体となり、ウェザーになりきってるラストの「ブギ・ウギ・ワルツ」
が一番印象に残った。
レイ・ブラウンの後継者になることを捨て、アグレッシブに自分の音楽やスタイルを追求する姿勢は素晴らしいが、その努力が実を結ぶまでには
もう少し時間が必要か?。
もし、彼が、フレットレスベース奏者として、ウェザーリポートに参加したならば・・・。
個人的に歴代ベーシストと比較すると・・・残念ながら、まだ最下位、細かいテクニックでは、ビクター・ベイリー以上かもしれないが、
グルーヴの太さと勢いは、遠く及ばない。この手のサウンドを追求するには、まず、小手先で、ジャコを追うのではなく、まず、
プリミティブな力強いグルーヴを作り出せるようになることが先決のような気がする。
(2003年3月7日)

Kenny Lattimore & Chante Moore “Things That Lovers Do”
近年の「歌を失った」R&Bには全く興味が無かったが、ルネ&アンジェラの「You Don’t Have To Cry」
ベイビーフェイス/キャリン・ホワイトの「Love Saw It」テディ・ペンダーグラスの「Close The Door」
キース・スウェットの「Make It Last Forever」・・・80年代一大ムーブメントを巻き起こした「クワイエットストーム」な名曲の
カヴァーが記されたCDの背中を見た瞬間・・・気がついたらレジの前におりました。
プロデュースには、ジャム&ルイスやベイビーフェイスの懐刀ダリル・シモンズらが参加、ベタ企画を上手くクールに演出してます。
ヒップホップ的演出はほとんど登場せず、ひたすら、メロウ・・・メロウ・・・メロウ・・・これがインストならスムースジャズ?という雰囲気。
気分は80年代、NYのソウル局WBLSの人気DJだったヴォーン・ハーパーのバリトンヴォイスが曲の間から聞こえてきそう。
ケニー・ラティモアという若い人気シンガーが、この種の企画に挑戦したということは、アメリカのR&B界にも、「いい歌」を求める動きが
あるということなのでしょうか。
10曲目のパティ・ラベルのカヴァー「Is It Still Good To You」~11曲目のキース・スウェットのカヴァーの流れがセクシーでたまりません。
特に、キースのカヴァーは原曲よりもいいかもしれません。
最近のR&Bを敬遠してた30代半ば~後半のソウルファンにも十分推薦できる「H」なアルバム。
(2003年3月8日)

CTI ALL-STARS “CTI Summer JAZZ At The Hollywood Bowl”
Feat / Deodato (key) Jonny Hammond(org) Bob James (key) Ron Carter (b.el-b) Jack Dejohnette (ds) George Benson(g)
Airto(perc) Hank Crowford Joe Farrell Stanley Turrentine Grover Washington,Jr(sax) Freddie Habbard(tp)
Hubert Laws(fl) Milt Jackson(vib) Ester Phillips(vo)
もともとはLP3枚に分割されてたものが、今回日本企画により2枚組みCDとしてリイシューされた72年録音の「クロスオーヴァー」の名作。
(「名作」といいつつも、いまだ、LPでは、セコハン屋のクズ盤コーナーに1枚100円で放置されてたりもするが・・・。)
個人的には、CTIものというのは、ちと苦手、特に、大仰なホーンやストリングスのアレンジで輪郭がぼやかされた「もや」のかかったようなサウンドが嫌だった。
今回のリイシューでは、デジタル・リマスターが施されたようで、サウンドが鋭角的になったように感じた。
特に、ロン・カーターのエレベ、「モコモコ、モワモワ」してしまりのない音に我慢ならなかったが、ここでは別人のよう。
1枚目の4曲目、ハバートの「First Light」や2枚目3曲目、タレンタインの「Funkfathers」での、ミディアムテンポのグルーヴィーなウネリは、
LPでは気づかなかったが、結構カッコいい。
当時は、「こんなもんジャズじゃない」「スーパーのBGM」などと揶揄されてたCTIものだが、こうして、改めてライブ盤を聴くと、
これはこれでちゃんとしたジャズなんだな、これが。
スタジオ録音ものでは、アレンジ過多なサウンドも、このライブ盤のようなセッション的な場面では、再現が難しいようで、
逆にこれが功を奏して、ミュージシャンの熱さやソウルフルな臭いを発散させたものとなっている。
グローヴァーをフィーチャーしたマービン・ゲイの「Inner City Blues ~ What’s Going On」ハバートをフィーチャーした「First Light」、
スタイリスティックスのカヴァー「People Make The World Go Round」ジョニー・ハモンドをフィーチャーした
アリーサ・フランクリンのカヴァー「Rock Steady」、タレンタインをフィーチャーした「Funkfathers」あたりが
「Jazz meets R&B」な雰囲気で特にカッコいい。
最近、ハンク・クロフォード、ジョージ・ベンソン、アイドリース・ムハマッド、フレディ・ハバードなどのCTIものの輸入盤が
1000円ちょっという廉価でタワレコなどに並んでたりするので、興味のある人は、気軽にチェックしてみては?。
何せ安いんで、失敗しても、あんまり凹まずにすむでしょうから。
ただし、ヒューバート・ロウズのクラシックものみたいなヤツをつかむと、やっぱりダサくてかっこ悪いので、商品はよく選んで買いましょう。
(2003年3月10日)

Marsalis Family “The Marsalis Family: A Jazz Celebration”
Feat / Ellis Marsalis(p) Branford Marsalis(ts,ss) Wynton Marsalis(tp) Delfeayo Marsalis(tb) Jason Marsalis(ds) Roland Guerin(b)
Harry Connick,Jr.(p) Lucien Berbarin(tb)
2001年8月4日ニューオリンズでのライブ盤。
主役は、地元のジャズ教育者の重鎮、エリス・マーサリス、もちろん、マーサリス兄弟のお父さんです。
ニューオリンズでのライブ録音、ウィントンも参加、ということで、なにやら、先祖帰り的なニューオリンズジャズを演ってそうな雰囲気ですが・・・。
嬉しいことに、全部が全部、そんな感じではなく、それ風のトラックは、ハリー・コニック.Jr(エリスはハリーの師匠にあたるそう)
の歌とピアノをフィーチャーした「セントジェームス病院」とラスト曲(国内盤にはそのあとに1曲追加されてますが)のみ、
後は、ミディアム~スロウな4ビートナンバーです。
特に、1曲目に収録されてる、ブランフォードのセカンドアルバム「ロイヤルガーデンブルース」の1曲目にも収録されていたエリスのペンによるナンバー
「Swinging At The Heaven」がスイングしてていい感じです。
いつもは、ジャズ伝道師としての使命感をひとりで背負い込んだような重さを感じるウィントンのトランペットも、
デコに青筋立てながらコルトレーンの亡霊とバトルし続けるブランフォードのテナーも、リラックス、リラックス、スイング、スイング。
この2人、他の場面でも、こんな演奏をしてくれれば、もっと沢山のファンにアピールできるのに?と思います。
お父さんのエリスのピアノですが、ニューオリンズのベテランピアニストながら、結構、モダンです。
2曲目の歌モノ系スタンダード「飾りのついた四輪馬車」でのモーダルで斬新な解釈は、なかなか新鮮。
さすが教育者としての側面を持つだけあり、いろいろなスタイルのジャズを研究している感じです。
他に、プロデューサーとしての方が有名?なトロンボーンのデルフィーヨや兄弟の末っ子のドラマー、ジェイソンも参加してますが、
すいません、印象なしです。
とにかく、このアルバム、温泉で鼻歌を歌うが如くリラックスしたブランフォード&ウィントンの兄弟を楽しむ作品です。
多分、かっこつけこの2人、こんなシチュエーションでない限り、こんな演奏やらないでしょうから。
かつては、犬猿の仲とまで言われた、ブランフォードとウィントンですが、ウィントンが語るところによると、今ではそんな不仲じゃないそうです、
ちなみに。
(2003年3月10日)

Jeff Lorber(key) “Philly Style”
w/ Gary Meek Richard Eliot(sax) Tony Maden(g) Alex Al(b) Lil’ John Roberts(ds) Lenny Castro(perc) Naila(vo) Jerry Hey Dan Higgins
Bill Reichenbach(horns) etc・・・
前作「Kickin’ It」から2年ぶりの新作。
テーマは、アルバムタイトルからも想像できるとおり「フィリー・ソウル」、スタイリスティックス、ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツ
、スピナーズ、ブルーマジック・・・そして、彼らの歌を演奏で支えたMFSB・・・、流麗なストリングス&ホーンズと都会的で洗練されたメロディーライン、あの「フィリー・ソウル」のはずなんですが・・・。
そんな雰囲気、じぇんじぇん、しましぇ~ん、なんでだろう??。
強いていえば、ジェリー・ヘイのアレンジによるホーンセクションが、それ風かな?というくらいです。
どんな感じ?かといえば、90年代のヴァーヴ在籍時のようなサウンド、跳ねる打ち込み系リズムに、コロコロとしたローズ&エレピがポロポロ
のっかかるもの。いつもと一緒。
あのエリック・ベネイやケニーGを発掘した才能を持つローバーが今回紹介する女性シンガー、ナイラ?ですが、ニューソウル風でそれなりの雰囲気は
持ってる感じですが、その程度。
どっかで聴いたことが??みたい感じの曲の連続ですが、今だアメリカでは一定の支持を集めるスムース・ジャズ系の放送局では重宝されそうです。
そんな凡庸なサウンドなんで、ジェフ・ローバーの熱心なファン以外は、そんなに気にする新譜ではないでしょう。
(2003年3月12日)

Randy Brecker(tp) “34TH AND LEX”
w/ Michael Brecker(ts) David Sanborn(as) Ronnie Cuber(bs) Fred Wesley Mike Davis(tb) Adam Rogers(g) Chiris Minh Doky(b,el-b)
Gary Haase(el-b,Programming) George Whitty(key) Clarence Penn(ds) Zach Danziger(programming) etc
昨年秋(2002年)、コンコード・ジャズ・フェス・イン・ジャパンで来日したときのような「アコースティック・ブレッカーブラザース」
のようなサウンドになる?と言われていたランディの新作だが、いい意味で裏切られました!。
名義は、「ランディ・ブレッカー」ながら、出てくる音楽はズバリ「ブレッカーブラザース」、カッコいいです、マジで!!。
90年代にリユニオンされたブレッカーズは、妙に、当時のヒップホップのムーブメントにすり寄り過ぎた感じで、ジャズ的にはいまいち、
中身が薄かった気もしますが、この作品はそうじゃないです。
ストリート感を演出するために、ループのリズムを使った曲もあったりもしますが、基本はちゃんと「ジャズ」に軸足を置いてます。
90年代のリユニオンブレッカーズが、「タテ」に揺れるグルーヴだとすると、今作は、「ヨコ」に粘るグルーヴという感じ?。
ロニー・キューバーのヤクザなバリトン・サックスソロからスタートする1曲目のラテン調のミディアムファンク~ホーンセクションは、ブレッカーズ
+サンボーン+ロニー・キューバー~マイケルのファンキーなテナーソロもフィーチャー~いやいや、カッコいいです、のっけから!。
アダム・ロジャーズのジャジーなギターが効果的にフィーチャーされるクールなファンクナンバーの2曲目~ここでのマイケルのソロも渋カッコいい。
サンボーンの「泣き」のアルトで、ボブ・バーグを追悼したミディアムナンバーの8曲目(ジャズと同じ、いやジャズよりも?釣りが好きだったボブ・バーグに捧げた曲ということでタイトルも「The Fisherman」)、ランディが吹きまくる10曲目のアップテンポな4ビートナンバーなどなど
・・・他にも、もっとカッコいい曲があるんですが書ききれません。とにかく、買って聴いてください。
ここでの主役、ランディですが、ひとりでバリバリ吹きまくらず、マイケルをはじめサンボーン、キューバー、アダム・ロジャースなどにもスペースを与え、その対比の中で、自分のトランペットをカッコ良く響くように演出されてる感じで、我々リスナーの感性のツボを上手くつく演出ですな。
いやいや、こればっかりで恐縮ですが、カッコいいです、これは!!。
最後の曲に、マイケルとともに、現在のランディのカミさんだというイタリア人サックス奏者がフィーチャーされてるのは、ご愛嬌ですが、
こんなカッコいい作品を創ってくれたランディに敬意を表して、この件は許してあげることにしましょう。
(2003年3月12日)
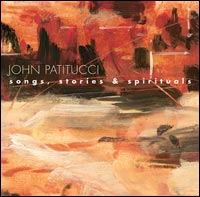
John Patitucci(b,el-b) “Songs, Stories & Spirituals”
w/ Braisn Blade(ds,perc) Ed Simon(p) Luciana Souza Jon Thomas(vo) Tim Ries(fl) Sachi Patitucci(cello) Tom Patitucci(g) etc・・・
今やチック・コリア・エレクトリック&アコースティックバンドのベース奏者と言うより、
ハンコック=ブレッカーの「Directions Band」やショーターバンドの~、といったほうが適切なほど、
コンテンポラリー・ジャズ・シーンにおいて欠くことの出来ない存在に成長したパティトゥッチの新作。
コンコード移籍後の路線は、派手さを廃した内省的なジャズいう感じだったが、近作も、内省的には違いないが、ブラジル味が加えられてるので
いつもに比べると、やや聴きやすいというか楽しめるというか・・・の作品になっている。
GRP時代の95年にブラジルよりジョアン・ボスコやイヴァン・リンスを迎えた「Mistura Fina」というブラジリアン・テイストな作品をリリースしているが、それを地味にした雰囲気?、4曲目の全編エレベを弾いてるナンバーなんかは、その辺の雰囲気に近い。
2曲目は、ジョビン作のブラジリアン・スタンダード「バラに降る雨」だし、
他の曲も、ブラジル人シンガーがフィーチャーされてるナンバーが結構多いので、やや聴きやすい気もするが・・・
パティトゥッチのアルコ弾きによるコントラバスのソロとストリングスの競演したものなどは、
やっぱり地味というか暗いというかなんというか・・・。
6弦の電気ベースでの演奏はいつもと同じ感じだが、コントラバスの演奏はかなり良くなり、重量感や安定感が増したせいか、
少ない音数で理想的な表現が出来るようになった感じ。
ラテン風味で内省的な感じでアコースティックでジャズの雰囲気もするし・・・そうだそうだ、パティトゥッチの今のボスのひとり、
ウェイン・ショーターの新譜の雰囲気だ。
あっちのドラムも、ブライアン・ブレイドだし、空間を感じる浮遊したリズム感は、何か共通のものを感じる。
あちらは、スペインだが、こちらは、ブラジル、サウンド構成はショーターのほど大がかりではないが、
作品全体の演出には影響を受けているのでは?と感じるが・・・ま、こちらの勝手な想像だけど。
そう考えてもう一度二度と聴いてみると、暗い内省的なトラックも興味深く耳に響いてくるようになった。
ぱっと聴きでは地味であんまり面白くないかもしれないけど、聴き込むと、じんわりじんわり、良さを感じる作品。
(2003年3月13日)

w/ Vernell Brown (piano) Charnett Moffett (bass) Chris Dave, Eric Harland (drums).
前作同様マーカス・ミラー制作ながら、今作は、ベースを弾かず黒子に徹しているため、ワンホーンによる「普通のジャズ」となっている。
スタンダードは、1曲目の「恋とは何でしょう」のみ、後はギャレットのオリジナル。
リズムセクションと一体となって疾走する「恋とは~」から始まるこの作品、全体的な印象は、かなりフリーブロウウィング、吹きまくり。
ひとりで突っ走るケニーに遅れまいと、クリス・デイブ(1曲のみエリック・ハーランド)=チャーネット・モフェットのリズムセクションも
必死でついていく、特に、バタバタと暴れるクリスのドラムはいい感じ。
ロニー・ロウズなんかと競演し、2枚ほど出てるリーダー作も凡庸なフュージョン作なんで、どうかな?と思ったピアノのヴァーネルもなかなか、
端正でエッジの効いたピアノは、ケニー・カークランドを少しだけ彷彿させる。
まぁ、そこそこカッコいいアコースティック・ジャズではあるとは思うが、何かいまいち面白くないというか、とらえどころがないというか・・・。
そう感じる要因のひとつは、ケニーのワンパターン、一本調子のサックスだと思う。
陰影感や繊細さの無いケニーのサックスを聴き続けると正直、疲れてくる。
80年代初期の新生ブルーノートの若手精鋭ユニット「OTB」やマイルスバンド、マーカス・ミラーグループなど、
他人がリーダーのバンドでは、自分のパートの演奏する際にはワンパターンでも、ま、それはそれでいいかもしれないけど、
自分のグループではそうはいかない、自分の演奏を上手くコントロールしつつ全体のサウンドを作り出さなくてはならない。
そのあたりがまだケニーに欠落している所だと思う。
また、オリジナル曲もいまいちいい曲が少ない。
もうすでに結構な数のリーダー作を発表しながら、いまだに、代表作、決定打に欠けるのはその辺に大きな要因があるのでは?。
そこを上手くカヴァーする役割のはずのプロデューサー、マーカスだが、何をしたの??という感じで、全然仕事をしてる様子がない。
サックスのサウンドのコントロールやそれを活かした音楽全体の作り方や構成などを、マイルスバンドの大先輩格となるウェイン・ショーターあたりから
もっと学んだ方がいいと思う。
マイルスバンドなどのサイドメンのときは、あんなにカッコいいのに・・・残念だなぁ、この人は・・・。
(2003年3月17日)

Bob
Mintzer Big Band “Gently”
Bob Mintzer Big Band/ Bob Mintzer, Bob Malach (tenor
saxophone, flute); Lawrence Feldman, Charles Pillow (alto saxophone, flute);
Pete Yellin (alto saxophone); Roger
Rosenberg (baritone saxophone, clarinet); Bob Millikan,
FRank Greene, Scott Wendholt,
Michael Phillip Mossman,
Jim Seeley (trumpet, flugelhorn); John Clark, Fred Griffin (French
horn); Mike Davis, Larry Farrell, Keith O'Quinn (trombone);
David Taylor (bass trombone); Phil Markowitz
(piano); Jay Anderson (bass); Peter Erskine (drums).
ジャズを含む音楽全体が不況のド真中、録音の為のパートタイムとはいえ、
正統派のビッグバンドを20年以上もきちんと維持し続けてるのは、
まず、とにかく、素晴らしい、素晴らしい。
グラミー賞も獲得したカウント・ベイシーへ捧げた前作から、2年振りの新作。
スタンダードナンバー「Body&Soul」とサド・ジョーンズの「Don' Ever
Leave Me」以外は、
ミンツァーのオリジナル。
プロを含む数多くのフルバンドのアレンジャーが参考にしている、と言うミンツァーのビッグバンドの
サウンドだが、こちらは、そのあたりには疎いので詳しくは分からないけど、今作では、「Gentry」というタイトルからも想像できるように、
「穏やか」な感じ?そのまま…やん??…木管楽器を上手く活かした丸みを帯びたウォームなフルバンといったところ。
しかし、「ウォーム」だけど、「ダル」な感じがしないのは、Yellowjacketsの「Live Wired」収録のコンテンポラリー・ジャズ・ナンバー
「Bright Lights」を含むミンツァーのコンテンポラリーなオリジナル曲中心の選曲に依る所が多い。
フィーチャーされてるソリストでは、近年、表現力の増したミンツァーのテナーやリリカル~グルーヴィーまでツボをつくカッコ良いピアノを
聴かせてくれるフィル・マコーヴィッツが良い。
また、暑苦しくなりがちなビッグバンドサウンドを絶妙なドラムでクリアな空気感を作りだしてるピーター・アースキンも素晴らしい。
フィル・マコーヴィッツのピアノが、ラッセル・フェランテに少し似てるなか?と思いながら、これを聴いてると
「Yellowjackets meet Bob Mintzer Big Band」みたいな作品も面白いんじゃないかな?と感じました。
最近のYellowjacketsのサウンドも、オーケストレイションが、ビッグバンド的な雰囲気もするので、方向性はそんなに違わないと思います。
そんな作品を本作と同じDMPレーベルの高品質な音で聴ければ最高なのになぁ。
(2003年3月23日)