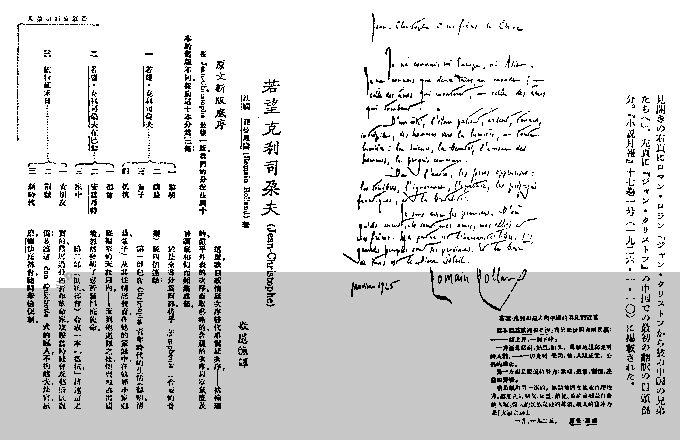|
2 1926年から40年代前半まての第2の時期
時代はくだるが1959年の北京大学学報第2期に、「五四時期のロシア文学およびその他のヨーロッパの国の文学の翻訳と紹介」(47)があるが、これには次のように記されている。
「この時、フランスの現代の進歩的作家ロマン・ロランとパルビュスもまた中国の文芸界の注目をひいた。この2人が第一次世界大戦中に戦争反対の立場をつらぬいたので、彼らは中国人民の敬仰をうけることとなった。『小説月報』はその作品を掲載し、魯迅が指導していた雑誌『莽原』は1926年に《ロマン・ロラン特集号》を出した。」(これは、1958年8月に北京大学共産党委員会の指導した科学大躍進運動で北京大学西方語言文学系のフランス語専攻学生の一部の人たちが翻訳史グループを組織してかいた「外国文学翻訳史」の「五四期部分」に基づくという。)
これはだいたい今日(文革期を除く)の目でみた外国文学翻訳史におけるロマン・ロランの位置づけの―つである。
いま、私の作成した「年譜」によれば、まず第一に、文学雑誌『小説月報』17巻1号(1926年1月10日(④)が注目される。
雑誌の冒頭から、ロマン・ロラン像(Granie作)、ロマン・ロランの塑像、ロマン・ロランの家、などの写真をかかげ、その後に見開きの2頁〔画像参照〕がつづいている。
〔画像〕
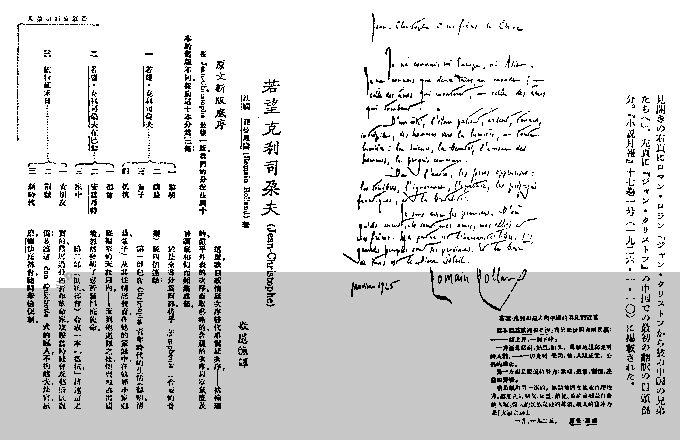
右側の頁にあるロマン・ロラン自筆の「ジャン・クリストフから彼の中国の兄弟たちへ」には、その下に中国語訳がつけられている。
ロマン・ロランは前年の1925年12月に「日本の友たちへのメッセージ」をかいているが、中国へのメッセージは実は日付からすれば、1925年1月になっており、1年近くも早かったのである。
このメッセージがどのように誰の手を通して『小説月報』の編集者の手にわたったのかはわからないが、おそらく中国で『ジャン・クリストフ』の最初の翻訳に手をつけ、当時フランスに居住して、ロマン・ロランをレマン湖のほとりに訪ねたこともある敬隠漁という人を通してであっただろうと想像される。ロマン・ロランのこの手紙には中国語訳にみられる<宣言>という語はないし、原文と中国語訳の間にはややへだたりのある部分もみうけられる。後に、1958年、羅大岡という人がこれを『フランス文学』誌に掲載された原文によって訳出している(45) 『ジャン・クリストフ』とその時代」、による)ので、ここではそれに従って日本語訳をつけておこうと思う。
|
ジャン・クリストフから彼の中国の兄弟たちへ
私は何がヨーロッパで、何がアジアなのかを知りません。私はただ世界には二つの種族があることを知っているだけです。一つは向上する魂の種族であり、他方は堕落する魂の種族です。
一方の人たちは、忍耐づよい、情熱的な、変ることのない、勇敢な力によって、光明―一切の光明、すなわち、科学、美、人間愛、共通の進歩にむかってつき進んでいます。
他の一方は抑圧の勢力、すなわち、暗黒、無知蒙昧、残虐無道、頑迷固陋の偏見と粗暴なふるまい、です。
私は前者とともにいます。その人がどこから来ようと、その人は私の友人であり、同盟者であり、兄弟なのです。自由の人類は私の祖国です。すべての偉大な民族はこの祖国の一つの部分です。そして、すべての人の財産は空の太陽なのです。
1925年1月 ロマン・ロラン
|
|
この手紙を読むと、私はロマン・ロランが1931年の復活祭にレマン湖畔のヴィルヌーヴでかいた「『ジャン・クリストフ』への序」の一節を思い出す。
「そして私がこの作をつくっていたときの私の予想をひどく越えている事実は、『ジャン・クリストフ』がもはやどの国においても異邦人でないということである。最もはるかな土地、最も相違している諸民族、中国、日本、インド、両アメリカ、ヨーロッパのすべての国々の人々の中から ―『ジャン・クリストフは私の同族です。彼は私と同族です。彼は私の兄弟です。彼は私です。‥‥‥』と言いながら来る人々を私は見た。」『ジャン・クリストフ』片山敏彦訳、より)
このようにして、ロマン・ロランの世界的名作『ジャン・クリストフ』は1926年初めに中国語訳をもつこととなった。
『小説月報』という雑誌は、1921年から、「人生の為の文学」を標榜して上海の商務印書館から発行(『小説月報』そのものはすでに1910年に創刊されていたが、21年から新たな編集方針で再出発した)され、中国文学史の上にも大きな足跡を残した雑誌であり、後には巴金、老舎、丁玲など多くの新人作家を文壇に送り出したし、外国文学の翻訳・紹介にも大きな貢献をした。それに魯迅につぐ大作家と目される茅盾はこの雑誌の初期の編集者であったし、魯迅はこのグループに直接加わらなかったが、その立場を支持していた。同じころ、この雑誌ないしグループに対立していたのは、創造杜と呼ばれるグループで、「芸術の為の文学」を主張して、ロマン主義を標榜していたが、この創造杜グループはロマン・ロランにはあまり関心をもたなかったように思われる。私としては索引なども利用して調査をしてみたが、資料は得られなかった。今後さらに調べてみたい。
さて、こうして『ジャン・クリストフ』の中国語訳が『小説月報』に掲載された。訳者の敬隠漁という人については十分にはわからないが、1920年代の前半期に短編小説をかいたり、フランスの詩や小説を翻訳したりしていたが、その後、フランスに住んだらしい(『魯迅案内』小野忍氏論文〔204頁〕による)。ただ敬隠漁訳の『ジャン・クリストフ』は、その後、3号にわたって連載されたが、未完に終っている。
次にみられる資料は、「レマン湖畔」(④c)という文章だが、これは当時学校を出たてのフランス留学生であった敬隠漁が、おそらくは中国からの最初の訪問者としてロマン・ロランをレマン湖畔に訪れたときの印象記である。ヴィルヌーヴ駅を下車してからの潮や山の美しさを述べ、また、彼がロマン・ロランを訪問したのは、『ジャン・クリストフ』を読んだある中国人の助言に従って、ロマン・ロランが若い時にトルストイに手紙をかいた、あの故事にならって、自分もロランに手紙をかき、それによってロマン・ロランに会うことができたことを記している。敬隠漁の若い魂はロランに会って大きな感動を受けたらしい。彼は中国の西湖のあたりの数枚の古画をロランに贈り、ロランからは『ガンヂー伝』と、彼の新しい作品『愛と死との戯れ』、それに『ジャン・クリストフ』の最後の巻を贈られている。敬隠漁はこの「レマン湖畔」という文章を1925年9月にリヨンでかいている。
この『小説月報』17巻1号が不十分にせよ、中国におけるロマン・ロランの翻訳・紹介の始まりであり、ロマン・ロランからの手紙を掲載したことも注目にあたいする。
ついで、『莽原』という雑誌が26年4月に『ロマン・ロラン特集号』を出している(⑨)。『莽原』は26年1月から半月刊で発行されたのであるが、これは実は魯迅みずから編集していた雑誌であった。
魯迅は1926年3月に『死地』(⑧)という文章をかいている。これは中国近代史で、三・一八事件と呼ばれている事件についての文章である。これは重い文章である。三・一八事件というのは、1926年3月に、日本をはじめとする列強が中国内の軍閥を支度して軍事行動を起そうとしたのに対して、北京の天安門前で抗議集会が開かれ、その後これらの人々が段琪瑞政府に請願に行ったところ、段琪瑞の命令で警備兵が発砲し、かれらを襲撃して、死者47名、負傷者150余名を出した事件である。前の話につづくが、現代評論派の陳源らは評論をかいて、請願に行った大衆や学生は自ら<死地>に入ったのだ、と述べた。これを非難したのが、魯迅の『死地』という文章であり、魯迅はこの文章にこうかいている。
「今、ちようど私の目の前に、ロマン・ロランの Le Jeu de l'amour et de la Mort が一冊おいてある。その中に、こう述べている。
カルノーは、人類が進歩するためなら、すこしばかり汚点があってもよい、万やむをえなければ、すこしは罪悪がおこなわれてもよい、と主張した。しかし、彼らはどうしてもクールヴォアジェを殺したくなかった。なぜなら共和国は彼の屍をその腕に抱きたくはなかったからである。それはあまりに重すぎるから。
屍の重さを感じることができ、それを抱くことを欲しない民族にとっては、先烈の≪死≫は後人の≪生≫にとって唯一の霊薬である。だが(屍の)重さを感じなくなった民族にとっては、それはおしひしがれてともに亡び失せるものに外ならない。……」
と述べて、青年たちに命を軽んじないよういましめた。
魯迅のロマン・ロランに対する対し方は、この文章では今までの文章とまるでちがってきているように思われる。ここでは魯迅は今までのように敵の背後の光背として利用されているロマン・ロランを見ているのではなくて、ロマン・ロランの作品から厳粛にひとつの教えを引き出そうとしているのである。
このような事件を経過して、1926年の4月に魯迅が直接編集していた雑誌『莽原』は7期、8期を合併号として、『ロマン・ロラン特集号』(⑨))を発行したのである。
これには「年譜」に見られるように、まずロマン・ロランの写真をかかげ、最初の論文は、張定黄「『戦いを超えて』と『先駆者たち』を読んで」(⑨a)である。
張定黄は、本名を張鳳拳といい、定黄はその字である。日本の東京大学を卒業し後に北京大学教授となったこともある。「難波大助事件」「中国人と日本人」「神戸通信」などの文章をかいているが、創造杜とも関係があり、ロマン・ロラン紹介者としては珍しく『創造季刊』にシェリーの詩や「ボードレール散文詩鈔」などの訳を発表している。後には魯迅も同人(一時、編集もした)であった『語絲』にも関係があった。(編集室注:定黄の「黄」は正しくは王偏ですが、表示不能につき)
張定黄についで、魯迅自身が日本語から中沢臨川・生田長江「ロマン・ロランの英雄主義」(⑨b)を翻訳している。この文の末尾にある魯迅の注によると、これは『近代思想16溝』の最後の一篇をとり出して中国語訳したものであり、この本は1915年に出版されているので、第一次世界大戦には言及していない、と説明されている。私はこの本を未見である。いずれにしても、魯迅みずからロマン・ロラン関係の論文を翻訳した、ということは魯迅がロマン・ロランにどれほど真剣な関心を寄せていたか、ということの一つのメルクマールになるだろう。がんらい魯迅は世界中で圧迫を受けている弱小民族の文学や東欧文学に注目し、その翻訳・紹介に力を注いだ。先進国のフランス文学について紹介したのはロマン・ロランを除いてあまりなかったことのように思われる。
『莽原』は、ついでGranieの画いたロマン・ロラン像、さらに銷少候「ロマン・ロラン評伝」(⑨c)を載せ、その後に次の「ロマン・ロラン著作表」(⑨d)をかかげている。
|
ロマン・ロラン著作表
A 戯曲
1 Les Tragédies de la foi..
2 Le Teatre de la Révolution.
3 Le Temps viendra.
4 La Montespan.
5 Les trois Amoureuses.
6 Le Triomphe de la Liberté.
7 Liluli.
8 Les Vaincus.
9 Le Jeu de la l'Amour et de la Mort.
B 伝記
1 Vie de Beethoven.
2 Vie de Francois Millet.
3 Vie de Michel-Ange.
4 Vie de Tolstoi.
5 Musiciens d'Aujourd'hui.
6 Musiciens d'Autrefois.
7 Händel.
C 小説
1 Jean-Christophe:
(a) Jean-Christophe.
L'Aube
Le
Matin.
L'Adolescent.
La
Révolte.
(b) Jean-Christophe à
Paris.
La
Foire sur la Place.
Antoinette.
Dans
la Maison.
(c) La Fin du Voyage.
Les
Amies.
Le
Buisson ardent.
La
nouvelle Journée
2 Colas Breugnon.
3 Clérambault.
4 Pierre et Luce.
5 L'Ame Enchantée
(a) Annette et Silvie.
(b) L'Eté.
D 論文
1 Au-dessus de la Melée.
2 Les Précurseurs.
3 Le Theatre du Peuple.
4 Les Origines de Théatre du Lyrique moderne.
5 Voyage musical aux Pay du Passé.
|
|
フランス語のまま著作年表を紹介したのはこの当時まだ翻訳が完備していなかったためであろう。この後に1909年7月付のロマン・ロランの手紙の写真をのせ、つづいて常恵訳「ハウプトマンへの公開状」⑨e)、さらに金満城訳「戦いを超えて」(⑨f)および常恵訳「私を誣うる者に答える手紙」(⑨g)をのせる。訳者はこれら3篇がそれぞれ論文集『戦いを超えて』の中の1篇である旨、付記している。金満城には他にいくつかの作品があるが、常恵については今のところわからない。 以上が『莽原』の『ロマン・ロラン特集号』の内容である。
この2カ月後の6月には『小説月報』17巻6期(1926年6月10日)(⑪)がやはりロマン・ロランについてかなりの紹介・翻訳をおこなっている。はじめに、師範学校時代のロマン・ロラン、『ジャン・クリストフ』をかいたころのロマン・ロラン、ロマン・ロランの母、「トルストイのロマン・ロランにあてた手紙」などの写真がかかげられ、徐蔚南訳の『べ―トーヴェン伝』の一部を巻頭言(⑪a)として使っている。このあと馬宗融「ロマン・ロラン略伝』(⑪b)、張若谷「音楽方面のロマン・ロラン」(⑪c)の2論文が紹介に力をっくしている。馬宗融についてはこの頃、この論文が見られるだけだが、張若谷は他に『語絲』に発表した論文がみられる。
これら紹介論文の後に、李劼人訳『ピエールとリユース」(⑪b)がのせられた。
李劼人(1891―1962)は早くからフランス文学の作品の翻訳を手がけ、モーパッサン、フローベル、ドーデーなどの翻訳もあるが、作家としてもすぐれ、新中国になってからも作品をかきついだ。ピエールと、ペテロあるいはピーターは、ヨーロッパで言えば同一名の転音なのであろうが、李劫人訳では『ビーターとリユース』(『彼得与露西』)になっている。この訳は、上下に分けて次号(26年7月10日)(⑫)にも連載された。『小説月報』も『莽原』の場合とおなじく、この後に「ロマン・ロラン著作年表」(⑪e)を付しているが、こちらは著作の発表順に年代を付して排列されており、より整理された形になっている。著作表の内容はおなじで、ただ「伝記」の項に
"Mahatma Gandhi" がっけ加わっている。
この号の『小説月報』(⑪)はとくにロマン・ロラン特集号と銘うっているわけではないから、ロラン関係以外の記事も掲載されているが、この雑誌としては二度目のロマン・ロラン紹介に多くのページ数をさいている。
そしてもし、「年譜」にあるように、敬隠漁が“Europe”誌(1926年9月~1月)にかいた「中国のルネッサンスとロマン・ロランの影響(⑬)という文章を、われわれが読むことができるなら、このころの情況がもうすこしわかるのではないか、と思われるが、私は残念ながら未見である。
さて、ここでもう一度、ロマン・ロランと魯迅の話にもどらねばならない。敬隠漁はフランスに滞在していて、魯迅の名作『阿Q正伝』をフランス語に訳し、1926年の5月号、6月号の"Europe"に連載した。
このことについて、魯迅自身は、この年の年末にかいた「阿Q正伝の成因(1926年12月3日)(⑱)の末尾に次のように記している『阿Q正伝』の訳本については、私は2種類を見ただけだ。フランス語のものは8月号の『ヨーロッパ』に掲載されたが、まだ3分の1だけで、省略のあるものである。英語のものはていねいに翻訳されているが、私には英語はわからないので、なんとも言えない…‥」
ここでは「8月号の“Europe”」だと魯迅は言っているのだが、「年譜」(⑩)では“Europe”41期・42期(5月号、6月号)とあり、これは蜷川譲氏が調査されたものにもとづいたのだが、あるいは魯迅の記憶ちがいであったかもしれない。
さて、以下の話は岩波の『魯迅案内』にも根拠を示した上で紹介されている。ここでもそれを参照の上、もとの資料にあたって紹介してみたい。
姚辛農「魯迅―その生涯と作品」(英文雑誌『天下』所載、1936年11月。これは『魯迅案内』による。筆者未見)(30)によると、ロマン・ロランが『阿Q正伝』を読んで訳者(敬隠漁)あてに手紙をかき、「この物語の微賤な主人公阿Qの悲劇的な運命に対してほんとうに涙を流した」と言ったらしい。
魯迅自身の資料について調べてみると、魯迅が1934年3月24日に姚克、つまり、姚辛農にあてた手紙((28))には、
「敬隠漁君のフランス語は人の話では、りつばなものだそうですが、彼は翻訳に対しては必ずしも真摯ではありません。それは彼の目的がお金もうけで、重訳をすると、まちがいがいっそう多くなるのも当然だからです。……」
とかいていて、魯迅は”Europe”に載った敬隠漁の訳にはやや不満であったらしい。それにこの手紙の文面からわかるもう一つのことは、その翻訳も中国語からの直接の翻訳ではなくて、英語かなにかからの重訳であったかもしれないことである。
もう少し後のことになるが、『亡友魯迅印象記』(1947年10月。今、ふつうに見られるのは1953年の人民文学出版社本であるが、その出版説明に、「最初1947年10月に上海、峨嵋出版社から出版された旨の記載がある)(37)という本がある。これは魯迅の親友の許寿裳という人がかいたものであるが、これによると(55頁)、
彼(魯迅)は私にこう言った。「ロマン・ロランは敬隠漁のフランス語訳阿Q正伝を読んで、『この諷刺的な写実小説は世界的なものだ。フランス大革命の時にも阿Qはいた。私は阿Qのあの苦しそうな顔を永久に忘れることができない』と言った。それでロラン氏は私にあてた手紙を一通かき、創造杜に託して私に転送してもらうことにしたんだ。だが、私は受取らなかった。というのは、当時、創造杜は私と論争のまっ最中で、すき勝手な攻撃を加えていたので、その手紙を握りつぶしてしまったのだ」
と記されている。
ロマン・ロランはこのようにして『阿Q正伝』を読んだのだが、この作品に深い感動を受けて魯迅に直接手紙をかいたのである。ここでロマン・ロランが『阿Q正伝』を「諷刺的な写実小説」であり、フランス革命の時にも「阿Q」のような人物が存在した、というように読んでいるのは、当時の作品評価として、今から見ても正しい、筋の通った読み方であり、評価であると考えられる。しかもロマン・ロランは、阿Qの苦しみ=魯迅の苦しみに深い同情を寄せているのであり、ロマン・ロランが魯迅のすぐれた理解者であったことがわかる。
そうして、1933年12月19日づけの魯迅の姚克あての手紙こはこうある。
しかし、ロランの批評の言葉は、永遠に見つからないだろう、と思います。訳者の敬隠漁の話では、それは一通の手紙で、彼はそれを創造杜に送りました。彼はながくフランスにいたので、このグループが私を嫌っていることを知らなかったのです。で、彼らに発表するようたのんだのですが、その時からさっぱり行方がわかりません。このことはもうだいぶ以前のことなので調べようもありません。
私はもうさがすことはないと心にきめています。
このようにして、たいへん残念なことに、ロマン・ロランの善意は、このときも魯迅にとどかなかった。
その当時、というのは、1928年から2年間ほど、創造杜(第3期創造杜)は、革命文学=プロレタリア文学を主張し、魯迅や茅盾らを旧文壇の大御所だとみなして、極左的な立場からむちゃな批判を加え、魯迅らとの間に論戦を展開した。文学史上、「革命文学論戦」とよばれている。手紙の握りつぶし事件はおそらくこの時期におこったのである。ただそれが28年のことだと仮定すると、すこし時間的な偏りがあるように思う。もっとも当時はまだエア・メールではなかっただろう。26年半ばごろまたは夏の終りにロマン・ロランが魯迅あての手紙を出したとすると、26年末か27年初めには創造杜の手に渡っていたであろう。そのころ、広東にいた創造杜の同人たちはだいたい上海に帰っていたであろう。魯迅は27年1月に広東につき、4月12日の、いわゆる清党事件後、10月に上海へ居を移している。こうした両者の複雑な移動もあり、どのような経路で創造杜の誰に手紙がわたったのかは不明であり、魯迅の言うように「さっぱり行方がわからない」のである。もしこの手紙が魯迅の手に渡っていたら、と考えると、まことに残念なことであると思う。
さて、他方、魯迅の編集していた『莽原』は1926年10月から12月まで、Stefan
Zweig の"Romain Rolland" (⑭⑮⑯⑰⑲⑳)を張定黄の訳で連載し、さらに27年末には画室(評論家・憑雪峰のペンネーム。『回憶魯迅』の着がある。新中国成立後も活躍した)訳の「『民衆戯曲』の序論:平民と劇」((21))を載せている。『莽原』はこの号をもって停刊しているが、終始、ロマン・ロランへの関心をもちつづけていたように思われる。
ところで、1920年代には、ロマン・ロランの作品はどのくらい中国語に翻訳されていたのであろうか。次に紹介するのは『中国現代出版史料甲編』に収められている蒲梢いう人の作成した「漢訳東西洋文学作品編目」、つまり外国の作家の作品の翻訳目録で、そのうちのロマン・ロラン関係のものである。これは1929年3月までのものに限られている。
貝多文伝(Beethoven) 楊晦 北新
貝多分(Beethoven) 徐蔚南 芸術界
彼得与羅西(Pierre et Luce) 李劫人 『小説月利17巻6―7号
自利与羅西(Pierre et Luce)
葉電風 現代
愛与死之角逐(Le Jeu de la l'Amour et de la Mort)(劇) 夏来帯、徐培仁 創造
愛与死(Le Jeu de la l'Amour et de la Mort)(劇) 夢茵 泰東
若望克利司朶夫(Jean-Christophe)(末出)
敬隠漁 商務
孟徳斯傍夫人(La Montespan)(劇)(未出) 李泉、辛質 商務
作品名と訳者名、最下段は出版社名である。訳があることがわかっていて現在印刷中のものは「未出」としている。
これはよく調査されたリストだが、残念ながら出版年月がかかれていない。『べートヴェン伝」『ピエールとリユース』『愛と死との戯れ』は重複しながら出ていることがわかる。『ジャン・クリストフ』は『小説月報』に敬隠漁による最初の部分の翻訳があるだけで、完訳の単行本はまだ出ていない。これだけ翻訳が出ている、とも言えるし、ロマン・ロランのそれまでの著作すべてに比べれば、これだけしか翻訳されていない、と言えるのかもしれない。もちろんインテリは原書あるいはその他の外国語訳で読んでいただろう。そうして、『愛と死との戯れ』については、1930年1月に、沈端先(夏桁)、鄭伯奇らが組織した上海の新劇グループ「芸術劇社」がその第一回公演として上演したことがわかっている。
これらのロマン・ロランの作品はどのように当時の読者に迎えられたのであろうか。具体的な情況はわからないが、後に作家・評論家として著名な茅盾「永遠の記念と景仰」((33))によれば、
「われわれ中国のインテリたちにとってロマン・ロランは見知らぬ名前ではない。彼の大著『ジャン・クリストフ』とトルストイの『戦争と平和』は、ともに今日の進歩的な青年が愛読した本であり、われわれの貧しい青年たちは、この二大名著の翻訳をもつことを誇りとし、またつぎつぎに貸しあって一読することを光栄としている」と述べている。『ジャン・クリストフ』の翻訳が何時完成し、また出版されたのか、実はその本を見ていないのでわからない。たぶん、この文のはじめにかいた、小尾氏からいただいた『ジャン・クリストフ』のもとの本がそれにあたるだろう。つまり、傳雷という人の完訳本である。敬隠漁は翻訳を完成しなかったのか、本にはならなかったらしい。
さて、茅盾は先の文につづいてこう述べている。
「それにわれわれはまた忘れることができない。われわれのこの時代のすぐれた思想家・芸術家である魯迅先生の『阿Q正伝』が敬隠漁君によってフランス語に訳されフランスで出たとき、ロマン・ロランがそれを読んで、どれほど感嘆しそして驚喜したか、ということを。また『ジャン・クリストフ』がはじめて広大な中国の読者と顔をあわせたとき、ロマン・ロランの『ジャン・クリストフから彼の中国の兄弟たちへ』のほんのわずかな短い言葉がわれわれにどれほど大きな励ましとなったかを。その時、われわれはちょうど1927年の大革命の前夜にいた。まさに魯迅先生の言われたように、血みどろの中に空気をかよわせる穴をあけた何千何万の、民主を求め光明を求める青年たちが、ロマン・ロランのわれわれに対する呼びかけを読んだのである。『私はただ世界には二つの種族があることを知っているだけです。一つは向上する魂の種族であり、他方は堕落する魂の種族です。一方の人たちは、忍耐づよい、情熱的な、変ることのない、勇敢な力によって、光明―一切の光明、すなわち、科学、美、人間愛、共通の進歩にむかってつき進んでいます。他の一方は抑圧の勢力、すなわち、暗黒、無知、蒙昧、残虐無道、頑迷固陋の偏見と粗暴なふるまい、です。私は前者とともにいます。その人がどこから来ようと、その人は私の友人であり、同盟者であり、兄弟なのです。』その時われわれは、民主を求め光明を求める戦いの中で、われわれは孤立していないことを知った。われわれは強い確信をもったのである。
われわれは今でも覚えている。『五四』初期に、思想界にまだ中心がなかったとき、資本主義文化を批判するために教えを求め、『ネオロマン主義』の内容を探求したことから、若干の文化工作者の間にロマン・ロランを研究しようというブームをまきおこした。新劇運動の初期にロマン・・ロランの『民衆劇』の理想が提起され討論された。田漢先生はかつて熱心にこの理論を紹介した。」
すこし長い引用になったが、あえて訳出した。いろいろな点でロマン・ロランが中国の知識人にどのような影響と力を与えていたかを知ることができるからである。それにもう一つ注目すべき点は、すでに紹介した『莽原』所載の『民衆戯曲』が、中国新劇運動の初期に劇作家・田漢によっても熱心に紹介されていた、という事実である。これからこの面についても調べてみなければならないだろう。
茅盾はさらにこの文章の別の箇所でこうも述べている。「そうして、われわれがロマン・ロランに対して熱心なのにはほかに特別な理由がある。すなわち、彼が最初にわれわれの注意をひいたのは、彼が前の(第一次)世界大戦期に発表した『精神の独立宣言』(訳注:1916年6月の『精神の独立宣言』をさしており、ロマン・ロランは知識人・作家千余人の署名とともに『ユマニテ』紙こ発表した)であり、また、彼が前の世界大戦期にかいた反戦論文集『戦いを超えて』があるからである。」
以上の茅盾の文章はロマン・ロランの死去を悼む文章としてかかれているのだが、ロマン・ロランが中国でどのように受けとめられているかを明らかにしている、と考えられるので煩をいとわず紹介した。茅盾の「永遠の記念と景仰」については、また後でもふれることにしたい。
ほかに小さな資料としては、1927年の『駱駝』(注:これは『語絲』の後をつぐものであった)という雑誌(22)に、やはり文学者であった、魯迅の実弟の周作人が『ミレー』の翻訳を掲載しているはずだが、私は未見。
ほかに、やはり現在の著名な作家である巴金が、その代表作で、当時のベストセラーであった『激流』(これは長編3部作で、『家』『春』『秋』からなりたっている)の「総序」(24)〔長編『家』はもともと『激流』という題名でかかれ、後に他の2長編を合わせて『激流」という総題名にした。「総序」はしかし『家』が完成したときにかかれたのである〕に次のようなことをかいている。
「数年前のこと、私は涙を流してトルストイの『アンナ・カレーニナ』を読み、本の扉に『生きること自体ひとつの悲劇である』という言葉をかきつけた。
事実はけっしてそうではない。生きることはけっして悲劇などではないのだ。それは『戦い』である。われわれは生きて何をするのか。言いかえれば、われわれはなぜこの命を必要とするのか。ロマン・ロランの答えは、『それにうちかつためにだ』である。」
これは、『愛と死との戯れ」の中で、ソフィが、「いったいなんのために、なんのために、人生が私たちに与えられたのでしよう」とたずねたとき、ジュロオムが「それにうちかつためにだ」と答えた、のにもとづいている。
巴金はアナーキズムの影響を受けた人であり、パリに留学し、パリで作品をかきはじめた。フランス語はできたはずだから、フランス語でロマン・ロランの著作を読んでいたかもしれない。ここで巴金がトルストイよりもロマン・ロランの言葉に賛成しているのも、人生論的にはまことに興味ぶかい。
ほかに1964年の黄俊東「英雄主義者ロマン・ロラン」(48)では、
「1931年、わが国で九・一八事変(満州事変わこと)がおこると、彼(=ロマン・ロラン)はまたアインシュタインなどと共同で声明を発表し、日本帝国主義の侵略行為を非難し、われわれ(=中国)のために正義を主張してくれた」と述べていて、中国人のロマン・ロランへの感謝の気持を表明している。
また、徐懋庸という若い評論家がいて、魯迅に『トルストイ伝』を贈り、手紙をかいて、魯迅にそれと関係して、日本人の名前についていくつかの質問をしている。魯迅は堺利彦、徳富健次郎、加藤直士、城戒(Jokai)などの人名について、ていねいに答えている。私の「年譜」にはこの資料は脱落しているので、ここに挙げておくと、それは、魯迅から徐懋庸あての書簡で、1933年11月15日、11月17日、11月19日の目付けの3通の手紙である(丸山昇「徐懋庸と魯迅」―岩波書店『文学』76年4月号一参照)。
徐懋庸の魯迅あての手紙は見られないので魯迅の手紙が見られるだけだが、この『トルストイ伝』は原文はフランス語らしいから、おそらくロマン・ロランのものであろう、と考えられる。推測すると、たぶん徐懋庸はこれを翻訳しようとして、はじめての手紙を魯迅に出して教えを乞おうとしたらしい。しかし、その後、この『トルストイ伝』訳が本になった形跡はない。魯迅の有名な論文、『徐懋庸に答え、あわせて抗日統一戦線について』(1936年)によってみれば、徐懋庸は魯迅の激しい怒りを買って、歴史の上にも芳しからぬ悪名を留めることとなったが、もともとは魯迅を尊敬し、ロマン・ロランの作品の翻訳をしようとしてその教えを乞うたことがあるということは、一つの文壇秘話になるのかもしれない。
30年代については断片的資料しか見出していないが、それは私が見出せなかったばかりでなく、後半の日中戦争の影響もあったであろう。
1935年の魯迅「孔?境編『当代文人尺牘鈔』」(29)は手紙の模範文を編集した本に魯迅が序文をかいたもので、その中に、ロマン・ロランの日記(『戦時日記』をさす)を死後10年たってから開くようロランが求めた、という話を引きあいに出して、日記や書簡のかき方を論じたもので、ロマン・ロランや魯迅の問題としては、これといった意味はなさそうである。
これよりも、左翼作家連盟に所属して、魯迅にも信頼されていた青年作家で柔石という人がある。この人は31年1月に国民党に逮捕され銃殺された人で、代表作に長編小説『二月』などがある。彼の死について、魯迅は後に「忘却のための記念」をかいて、深い哀悼の気持をあらわしている。
さて、この柔石のかいた「奴隷となった母親」という作品(23)がある。
貧乏なために自分の妻を地主の家に質入れしなければならなくなった男、地主の為に子供を産むことを契約させられたこの男の妻、この夫婦の子供、地主の家族、その人間関係についての悲惨な中国農村の物語である。
簫三の「ロマン・ロランを哀悼す」(32)によると、 「彼(=ロマン・ロラン)は『国際文学』フランス語版で柔石のかいた『奴隷となった母親』を読んだ後、この雑誌の編集部に手紙を出して、『この物語は私を深く感動させた』とかいた。ロマン・ロランは西方でもまれに見るほど中国の新文芸に関心をもつ人だった」
と述べている。
ここでもう一つ時期の確定できぬ資料をつけ加えておこう。これは『魯迅案内』に佐藤春夫がかいた「魯迅の『故郷」や『孤独者』を訳したころ」という文章がある。その中でロマン・ロランが魯迅の「故郷」という作品を喜んだ、と述べ、ただそうかいた根拠がはっきりしない旨を説明している。
魯迅は1936年に世を去り、ロマン・ロランも1944年になくなった。
魯迅とロマン・ロランについて考えるとき、その生涯でこの2人の巨人は互いに強い関心をもち、理解しあっていたように思えるが、しかし今まで説明したような情況からみるとき、不幸なことにいつも近づきながら行きちがっていたように見える。魯迅は1932年冬に北京に行ったが、陸万美という人の「魯迅先生の『北平五講」前後を追記す」(『億魯迅』―人民文学出版社、1956年―所収)によると、それはソビエトのゴーリキーから招待を受けたからであった。ゴーリキーは魯迅がモスクワへ行って、開会を準備していたソ連作家代表大会に参加するよう望んだのであった。それに、魯迅をソ連にやや長く滞在させて病気の療養をし、また創作をしてもらおう、と考えたらしい。そしてこの作家代表大会には、ロマン・ロラン、バルビュス、バーナード・ショーなどが招かれていた。魯迅のソ連行きの計画は中国共産党の援助で進められたのだが、国民党の監視がきびしく果さなかったらしい。もしこれが実現していれば、魯迅はロマン・ロランに会見して親しく話し合うことができたはずだった。
そういう観点から考えると、先にも述べたように、両者は互いに引きあいながら、不幸な行違いの運命をくりかえしたように思える。魯迅はいつも中国人に密着してものを考える人であった。たとえば、1925年にスエーデンからノーベル賞の話があったとき、魯迅はそれを断っている。その理由は、中国にはノーべル賞に値する人物はいない。もし私が黄色人種だからといって特別優待され、ゆるやかな基準で入選すれば、逆に中国人の虚栄心を満足させ、ほんとうによその国と競いあえると思いあがるようなことになるかもしれない。それではほんとうにまずいことだ、と考えたからであった。このように魯迅は中国や中国人という個別に密着して徹底的に考えぬいた人であった。しかし、魯迅は個別に密着することを通して普遍に達していたように思われる。
一方、ロマン・ロランはフランス人であったけれども、フランスやドイツといった国境を越えて東洋にまで手をさしのべ、人類の普遍を考えていた。
この両者は思考の道すじはちがっていたけれども、ともに人類の普遍に達していたのではないだろうか。そうしてこの両者はまた、ともに、単に作家、文学者といった概念を越えて、より大きな存在として仰がれた点でも共通であったように思う。
|