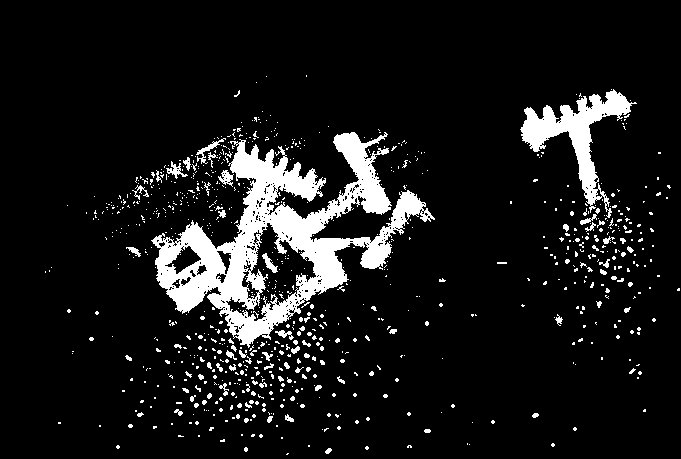
NEXT TOP
エリ子の新鮮な血がひとつ、もうひとつ
赤黒い床に落ちた
俺はエリ子が笑うときの八重歯が好きだったのに
頭をかかえて、エリ子は座り込んだ
毎日、会うのが楽しみだったエリ子が
動かなくなった
俺は手も出せず、足も動かず
どうしてだか「嫌だ。」という言葉が
真っ先に浮かんだ
いつも笑っていたエリ子の凍りついたような青い顔を見て
大変だというよりも
手を貸すということよりも
何よりも真っ先に「嫌だ。」という言葉が
大きく浮かんできた
どんどん後ろに行っていた記憶の中に
どこか似た感情があった
そう、あのロボット
大きな腕で回転したおもちゃのロボット
あのロボットで遊ぶとおもしろかったし
大好きだった
名前もつけていたし
他の人には触らせなかった
でもどうしてしまったのか
ある日、プラスッチックの片腕は折れてしまった
もう、ガクンガクンとするだけで
前転も後転も出来ずにもがいていた
その回転できなくなったロボットを
どうしてしまったか
濁った記憶からは蘇ってこない
遊ぶのが楽しかったロボットなのに
大好きだったはずなのに
八重歯のかわいいエリ子が
座り込んだ姿を見て
声もかけず、手も足もでず
何よりも動かなくなったことが不満で
「とても嫌だった。」