稲の日本史 佐藤洋一郎著
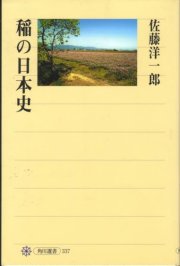 日本のイネも稲作も多重な構造をもっている。幾重もの構造の中で主たる構造をなすものが、縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作(縄文の要素)と、弥生時代に渡来した温帯ジャポニカと水田稲作(弥生の要素)の二つである。縄文の要素は、弥生の要素にとって代わられ、姿を消したものと考えられてきた。だが弥生時代以降のイネと稲作の中に、縄文の要素はしぶとく生き残っていたようである。弥生時代のイネが、熱帯ジャポニカを多く含むこと、また稲作も休耕を伴うなど縄文以来の伝統を色濃く受け継いだスタイルをとっていた。つまりイネも稲作も、縄文時代と弥生時代間には、以前考えられていたほどの大きな断絶があるようにはみえない。むしろ弥生時代がイネや稲作に関しては縄文時代の延長線上にあるともみえる。
日本のイネも稲作も多重な構造をもっている。幾重もの構造の中で主たる構造をなすものが、縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作(縄文の要素)と、弥生時代に渡来した温帯ジャポニカと水田稲作(弥生の要素)の二つである。縄文の要素は、弥生の要素にとって代わられ、姿を消したものと考えられてきた。だが弥生時代以降のイネと稲作の中に、縄文の要素はしぶとく生き残っていたようである。弥生時代のイネが、熱帯ジャポニカを多く含むこと、また稲作も休耕を伴うなど縄文以来の伝統を色濃く受け継いだスタイルをとっていた。つまりイネも稲作も、縄文時代と弥生時代間には、以前考えられていたほどの大きな断絶があるようにはみえない。むしろ弥生時代がイネや稲作に関しては縄文時代の延長線上にあるともみえる。
「稲の日本史」は歴史を大きく五つの時代に分類する。
第一の時代はイネのなかった時代で、生活の糧の主な部分は狩猟と採集によっていたが、部分的には原始的な農業も行われていた。青森県の三内丸山遺跡はこの文化期の典型的な遺跡のひとつで、栽培されていた植物には、ヒエ、クリ、ヒョウタン、アカザ、ゴボウなどが挙げられる。三内丸山遺跡に巨大集落が誕生したころ、西日本各地ではイネの栽培がほそぼそと始まっていた。(日本最古の稲作の痕跡 岡山市内にある6400年ほど前の朝寝鼻貝塚からイネのプラントオパールが発見された。 1999年4月20日)
第二の時代は縄文の要素が拡大した時代である。この時代が始まるのは、西日本では6000年ほど前(縄文時代前期から中期ごろ)、東日本ではずっと遅れて3000年ほど前(縄文時代の後期ごろ)と、大きな開きが見られる。この時代、イネと稲作は列島南西部では相当の広がりを見せ、食料生産の柱のひとつになっていた可能性が高いが、米が主食というような状態ではなかった。そしてこの時代が終わるのは、北海道、南九州と南西諸島を除く列島全体を通して、2500年ないし、2700年前(縄文時代の晩期ころ)のことである。
第三の時代は大陸から水田稲作の技術が持ち込まれた時期(縄文時代晩期ころ)に始まった。この時代は列島のほぼ全体で中世の終わりころまで続く。この時代は縄文の要素と弥生の要素がせめぎあった時代で、弥生の要素は約1500年かかって北海道の大半を除く日本列島ほぼ全体にゆきわたる。弥生時代の人びとの中でもっともポピュラーであった植物資源はドングリの仲間であり、イネがこれに続くがそのウェイトは全体の中ではそんなに大きくない。弥生時代の食は、水田稲作が導入された後とはいえまだ採集に依存する部分が相当に大きく、栽培によって得られる資源の中でもイネに依存する割合が高いわけでもない。日本列島では農耕の開始や広まりは実にゆっくりしたものだった。中世に至っても荘園や寺領内に相当量の不耕田(休耕地)があり縄文の要素が残っている。
第四の時代が水田稲作が定着した時代で、近世から近代初期までがこの時代に含まれる。「見渡す限りの水田」という景観が登場したのは、おそらく太閤検地のあと、あるいは近世に入ってからではないかと思われる。常畑化した水田の稲作を広めようとしたのは人的な力、それも支配者の力であった。人口の増加などによって自由に使える土地に制約が出てくると、それまでのように従来の耕地を放り出して新たに開墾することができにくくなる。一箇所の土地を耕し続ける時間は長くなり、常畑化が進行する。土地を支配する側にとって、いかに狭い土地から高い生産性を上げるかはコストパフォーマンスの面からいってもっとも注目される。近世に入り、新田開発などの大型開発が行われるようになると、反収(一反(10アール)あたりの収穫高)への志向性は一層強いものとなった。
第五の時代が近代から現代に至る時代で、稲作もまた西洋近代化の洗礼をまともに受けた。この時代は、言葉を換えれば弥生の要素と西洋文明のハイブリッドの時代でもあった。イネの反収は、第三時代から第四時代までの2000年間の水準(160−190キロ)から、わずか100年余りの後に三倍弱の518キロに達した。反収が奇跡的なあがり方してきたのは、化学肥料の開発、品種の改良、栽培技術の改良、農薬の普及がある。

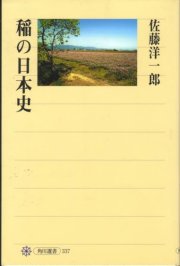 日本のイネも稲作も多重な構造をもっている。幾重もの構造の中で主たる構造をなすものが、縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作(縄文の要素)と、弥生時代に渡来した温帯ジャポニカと水田稲作(弥生の要素)の二つである。縄文の要素は、弥生の要素にとって代わられ、姿を消したものと考えられてきた。だが弥生時代以降のイネと稲作の中に、縄文の要素はしぶとく生き残っていたようである。弥生時代のイネが、熱帯ジャポニカを多く含むこと、また稲作も休耕を伴うなど縄文以来の伝統を色濃く受け継いだスタイルをとっていた。つまりイネも稲作も、縄文時代と弥生時代間には、以前考えられていたほどの大きな断絶があるようにはみえない。むしろ弥生時代がイネや稲作に関しては縄文時代の延長線上にあるともみえる。
日本のイネも稲作も多重な構造をもっている。幾重もの構造の中で主たる構造をなすものが、縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作(縄文の要素)と、弥生時代に渡来した温帯ジャポニカと水田稲作(弥生の要素)の二つである。縄文の要素は、弥生の要素にとって代わられ、姿を消したものと考えられてきた。だが弥生時代以降のイネと稲作の中に、縄文の要素はしぶとく生き残っていたようである。弥生時代のイネが、熱帯ジャポニカを多く含むこと、また稲作も休耕を伴うなど縄文以来の伝統を色濃く受け継いだスタイルをとっていた。つまりイネも稲作も、縄文時代と弥生時代間には、以前考えられていたほどの大きな断絶があるようにはみえない。むしろ弥生時代がイネや稲作に関しては縄文時代の延長線上にあるともみえる。