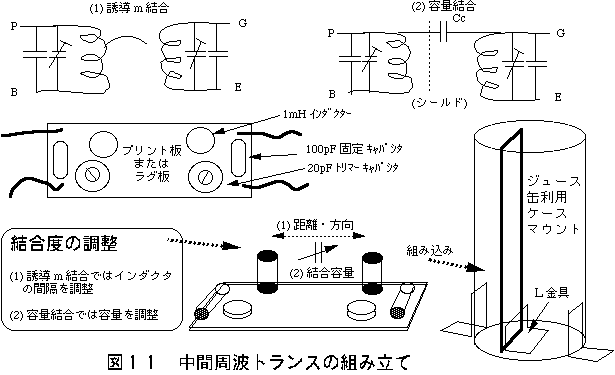
A (db) = 20 * LOG10 [SQRT {1+ (2 * ΔF/Fr * Q) **2} ] にて与えられ、
例えば、並三/並四で 1MHz に同調したときの 100 kHz 離調点での減衰度 A100k/1M は
A100k/1M (db) = 20 * LOG10 [SQRT{1+(2*100/1000*100)**2}] = 20 * LOG10 [SQRT{1+(2*10)**2}]
= 20 * LOG10 [SQRT(1+400)] := 20 * LOG10 [20] := 20 * 1.3 = 26 db
と求められます。 すなわち+100 kHz 〜 -100 kHz の裾にて -26 db := 1/20 の大きさで信号が聞こえることになります。
並三/並四では再生検波回路を併用して、Q が 300 に上がるとすれば、約 -36 db := 1/60、500 に上がるとすれば、約 -40 db := 1/100 となります。 これでは再生検波回路でも NHK第2(693kHz) の裾が NHK第1(594kHz) でもコソコソ聞こえます。
これを高一にした場合は、アンテナ・コイルの Q がアンテナに接続されたことにより 50 に低下するものとして約 -20 db = 1/10 の減衰が得られ、重ね合せて -46 db := 1/200 となり、聞こえにくくなります。
したがって、並三/並四や高一などのストレート方式にて隣接した2局 (9 kHz) を分離して受信するのは不可能なことが明瞭です。 また受信周波数 Fr が高くなると分母の Fr が効いてさらに選択度が悪化します。
初期のヘテロダイン方式やスーパーヘテロダイン方式の中間周波増幅回路では単同調回路ながら中心周波数が低かったので、何とか選択度を確保していました。
しかしながら、低い中間周波数では単同調アンテナコイルだけによる選択度の低さにより受信周波数から中間周波数の2倍離れた別の信号が混信する、イメージ混信が課題となりました。
そこでもっと高い中間周波数に持っていくとイメージ混信は解決しますが、中間周波増幅での選択度が不足します。 となれば同一周波数で、もっと選択度の高い同調回路が必要となる訳です。(2004/04)
Acc (db) = 20LOG10{(1+2*(ΔF/F * Q)**4)/2} 但し Q は共振回路の鋭さで、100とします。
例えば、スーパーで 450 kHz の複同調 IFT 1個について取り上げると、その10 kHz 離調点での減衰度 A10/450 は
A10/450 (db) = 20LOG10{(1+2*(10/450*100)**4)/2} = 20LOG10{(1+2*(100/45)**4)/2}
:= 20LOG10{(1+2*(2)**4)/2} = 20LOG10{(1+2*16)/2} := 20LOG10{17} := 20 * 1.2 = 24db
となり、このような仕様の IFT を 2個通せば、隣の周波数 (+-9kHz) の局はバリバリ聞こえる状態ですが、二つ隣 (+-18kHz) ならば、気にならない程度まで落とせて、高一ラジオに比べれば選択度はかなり改善されます。(2004/04)
[1] 周波数変換−中間周波増幅の段間(段間用) および
[2] 中間周波増幅−検波・低周波増幅の段間(検波用)
に各一個使用するので、計二個組みとなります。 前者をAnn、後者をBnn (nn は形番の数字) と呼んだメーカーもあり、現在でもその呼び方が残っているかもしれません。
なお、中間周波増幅二段にて構成する場合には、一段目と二段目の段間にもう一個、上記の [1] に準じる段間用 IFT を配置します。
では次に、どのような IFT が作れるか、仮設計してみましょう。
コイル=L/キャパシタ=Cと略称して、IFT の構造には同調の取り方によってL固定C可変の「C同調」、L可変C固定の「L同調」とがあります。
現在、市販の部品を使って複同調とするに適当な可変L (インダクター) の入手は望めそうもありません。 そこで部品の入手が容易なC同調にて構成することにします。
仮に 1mH のインダクタ(高周波チョーク)が入手できるとして、中間周波数
(Fi) = 455 kHz の同調回路として並列接続するCの値は
C = 1/{(2πf)**2*L} = 1/{(6.28 * 455*10**3)**2 * 10**(-3)} = 1/{(6.28
*455)**2*10**3)
= 10**3/{(6.28 * 455)**2} = 1000/8,165,000 = 1/8,165
= 0.000122 = 122 pF
と求められ、50~150pF 程度の羽根の多いトリマーを殆ど入れた辺りで、または100pF の固定キャパシタに 20pF のトリマーを抱かせて後の不足分は真空管の入出力容量や配線浮遊容量で補うとしてトリマーは半分回した状態で、丁度 455 kHz 辺りになるでしょう。
課題は誘導結合した二つのコイル間隔です。 これを変化させると
◇ 遠すぎれば結合が「疎結合」すぎてゲイン不足
◇ 最適の「臨界結合」ではゲインと帯域幅が両立
◇ 近すぎれば結合が「密結合」すぎれば双峰特性特性〜中弛みの裾拡がり、ゲイン低下
のような変化を伴うので、コイルの間隔を 40mm 位の「疎」状態から始めてゲイン増加が止まる「臨界」辺りに様子を見ながら接近させることになります。
但し、一組みの IFT のうち、[2] 検波用では、同調回路の負荷が低インピーダンスの二極管検波であるため、Q がダンプされてしまい [1] 段間用の様にシャープに反応しません。 そこで [1] 段間用をシッカリ調整する必要があります。
昔、市販されていた複同調 IFT では、ある程度の通過帯域幅 (中心周波数から -3 db 低下する点の+-周波数) を確保しないと、検波した音声が高域不足となるため、臨界結合よりやや密結合にした IFT を2個使い、帯域幅と選択度を両立させていましたが、その後現われた安価なトランジスタラジオでは単同調 IFT のものもありました。
4.1 試作 IFT に使用したインダクタ
● 裸でベーク芯にハネカム巻き 500μH (従って並列 C は可変 250pF 程度に変更)、
● 鼓み型フェライトコアに巻いた1mH インダクタ (並列 C は可変 150pF 程度)、
の二種類を試験しました。
前者の裸コイルを [1] 段間用にシールドなしで使うと中間周波増幅段にて猛烈に発振するので、もっぱら [2] 検波用に使用しましたが、後者のコイルを [2] 検波用に使っても何とか性能は確保できます。
後者の鼓み型フェライトコアに巻いたインダクタは、そのまま裸でも発振しないので [1] 段間用に使いました。 しかしこのインダクタは外部に漏れる磁束が少なく、コアを接近させて双峰特性になっても、信号の誘起が少ないためかゲインが不足気味でした。
4.2 試作 IFT のインダクタ間の結合度調整
過去の誘導結合方式による既製品 IFT のハネカム巻きコイルの間隔が 40 mm 程度であったと記憶していたので、その辺りに一応設定してから調整に入る事にしました。
鼓み型フェライトのインダクタでは、最初は全くゲインがなくて焦りましたが、接近するにつれて動作が確認され、インダクタのリード線を長いまま取り付けておいたので、調整の結果臨界結合と思われる状態は、間隔を 10 mm に設定し、且つ二つのインダクタを斜めに相互に 90度に傾けた場合に得られました。
この設定条件は、インダクタの構造およびコアの形状などで変わりうるので、一概にこのような値および形状になるとは限りませんから、実験的に設定するしかありません。
次に、微小容量 (Cc = Capacitor Coupling) による容量結合を試して見ました。 結果的には調整が面倒なので、誘導結合に戻してしまいましたが・・・
この微小容量とは、細いビニール線とアミラン線等を数回ほど撚ったもので実現できるので、ワザワザその容量のものを購入する必要はありません。 これで数 pF 程度が得られるので撚り幅が 2cm ぐらいからニッパで切りながら調整できます。 撚った端を少し延ばしておき、切りすぎて不足したら撚って回復します。
容量結合の場合でも、誘導結合と同様に Cc の値により「疎」〜「臨界結合」〜「密」と変化し、密結合状態では双峰特性となりゲイン低下に至ります。
但し容量結合の場合では、Cc を大きくして双峰特性となる場合に、単峰の周波数は固定のまま低い方に他の峰が発生するので、予め若干周波数の高い側にて単峰同調にて合わせておき、双峰の中心が中心周波数に来るように調整する必要がありますが、多寡だか数 kHz の誤差だから、成り行きに任せてキレイに揃わなくても実用上はあまり問題ありません。 この点では誘導結合の方が遥かに扱い易いです。
4.3 試作 IFT の組み立て
IFT のリード線の引き出しは、(できればジュース缶代用のシールド・ケース内で)リード線がブラブラしない様に、ラグ板またはベーク板等に固定し、底板の穴に通します。 トリマーは外から調整可能とするため、シールド・ケースの横腹に穴を開けておけば便利でしょう。
実際の試作品ではシールド・ケースに入れず、裸のままでしたが・・・片方のコイルには B 電圧が掛かっているので、調整が終ったら、感電防止のためにプラスティックの筒等を被せるか、キッチン・ラップにてくるんでしまうと安全です。 またはアクリル筒をはめた US プラグつきのプラグ・イン・コイルにマウントすれば最高のデキバエとなるでしょう。
トランス自体は 30mm 穴に四隅のビスにて取り付け、シールド・ケースは適宜シャーシに取り付けます。 実際の試作品ではラグ板をL金具等にてシャーシのソケット取り付け穴に固定しただけでしたが・・・
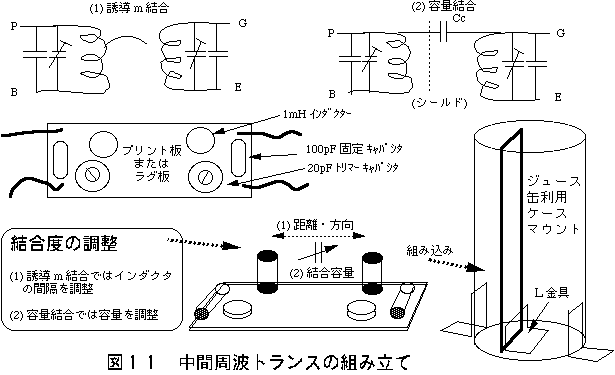
(2) 中間周波一段増幅での選択度改善例 〜IFT の小改造 (2003/10)
一段増幅用の自作 IFT でも実用上は何ら問題ではないのですが、夜間に遠距離局が多数入感しはじめると、選択性の甘さが・・・音質的にはワイドでよいのですが・・・気になります。
そこで対策ですが IF 増幅二段にして同調回路を増やすのは大改造になるし・・・高一ラジオと同様に同調したカソード・フォロワ出力を二極管の検波段に追加するか、増幅する代わりに同調カソフォロ一段の追加も考えました。 でもミニチュア管をシャーシ内に収容したり、FET のソース・フォロワでカバーすれば「カンニング」となるし、カソフォロ/ソースフォロ出力はローインピーダンス、同調Cの他に固定C併用のマッチングも必要です。
そこで単に同調回路を一個追加して様子を見ることにしました。 周波数変換段〜 IF 増幅段間の IFT に、同じ仕様の鼓型 1mH インダクタと150pF トリマーを抱かせたものを、電磁結合しないように離して IFT ラグに取り付けて、微小Cにて容量結合しました。 実際には下記図に示すとおり、
(1) 追加した同調回路の一端はグランド側、他端には IF 増幅段のグリッド・キャップへのリード線を付け替えて、
(2) もとの IFT 二次側から推定 1pF 程度の微小C・・・グリッドへのリードに単線を二回程度巻き付けて結合させ、
(3) 単峰同調になるように微小Cを加減して、同調を取り直しました。
その結果、ゲインの低下は殆ど判らない範囲にて、選択度は角型アルミケースに入った本式 IFT と遜色がない程度までに改善できました。
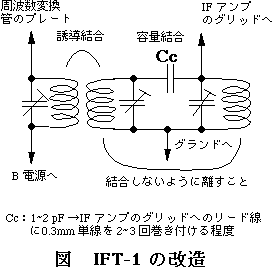
本件は重複しますが、別項目の「並四、高一、スーパーの再現」のページ、四球スーパーの部分にて説明しています。 ご参照ください。(2003/10)