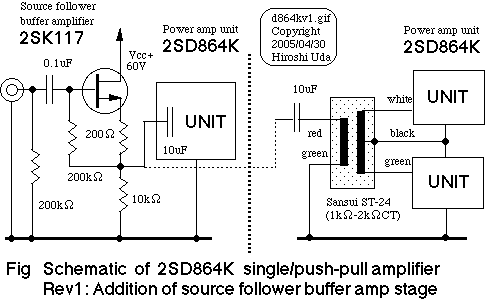2005/02-2005/08 宇多 弘

左はマナイタ上のシングル・アンプ、右はプッシュプル・アンプ

2SD864(K) (以下、単に Tr)を「裸」で動作させては明らかにゲイン・オーバーでしょう。 そこでコレクタ/ベース/接地間のブリーダ方式による「C-B NFB? 併用の固定バイアス」にて動作の安定性を得、ゲインを抑制し、音質を確保しようとモクロミました。 真空管回路での P-G NFB と同様の効果を期待しようというものです。
この Tr はダーリントン構成であり、内部では「前段」の小エレメントのエミッタが「終段」の大エレメントのベースに接続され、小エレメントのコレクタが大エレメントのコレクタに接続されて、C-B NFB 回路を構成することになります。 従って、上記のモクロミ回路では、欲張ってさらに外側からも C-B NFB 回路を適用しようという訳です。
ただし、ダーリントン構成の小エレメントの Hfe が大で、大エレメントの Hfe が小であれば、NFB 効果は大したことはありませんが、その逆ならそれなりの効果が見込めます。 その「内情関係」・・・どのような比率であるかは、規格表には記載されず類推できません。 このような関係は真空管どうしによるダーリントン構成=準超三結回路にて、ハイμ管カソフォロ・ドライバのプレートをローμ管終段のプレートで吊った場合は終段の P-G NFB が浅くて超三結効果が少なく、逆にローμ管カソフォロ・ドライバのプレートをハイμ管終段のプレートで吊った場合は深く掛かって超三結効果が大きい・・・のと似たような関係にあるものと類推されます。
試作の途中、上記のモクロミ回路が一応鳴った段階において、その効果を確認するために「裸」回路による固定バイアスに一旦戻してみました。 すなわち電圧配分ブリーダを +Vcc/ベース/接地間に変更して「裸」状態としました。 発振はしなかったのですが、ゲインが上がると同時に我慢しないと聴き続けられないほど音質が低下したので、モクロミ回路は的中らしい・・・
しかし色々イジッテ見ると、後述する C-B NFB 量の加減が、回路構成上から複雑であるとの問題点が明らかになりました。
(2) バイアス回路と C-B NFB 回路との共用による問題とその解決
動作点維持が主目的である、上記のブリーダによる電圧配分を、C-B NFB 用の信号電圧配分にも併せて利用するのには問題が残ります。
何故ならば、ベースへの信号入力インピーダンスがベース〜エミッタ間の抵抗に並列に入らざるを得ないからです。
さらに単段のまま、ポテンショメータ型の入力調整ヴォリュームを併用するとなると、スライダーの位置・・・ベース/グランド間の抵抗値によって NFB 量が変わり、それにつれて音質も変わることになります。
低い信号入力インピーダンスに対応しながら C-B NFB を確保するため、コレクタ〜ベース間のインピーダンスも同様に小さくすると、出力をロスするなどの問題が併発します。
信号入力経路に直列抵抗を挿入して影響を避けようとすると、ゲインが低下して単段構成が困難になります。
それで、完全な解決のためには、上記以外の何らかの方法により入力インピーダンスの隔離が必要になります。
ソースフォロワ等のバッファ・アンプを一段追加すれば上記の問題は解決ですが、単段アンプになりません。
それで、本アンプにて使用する入力調整手段は抵抗値が一定のアッテネータに限ることで決着しました。
実際には10kΩ B型二連ヴォリュームによるT型アッテネータの併用を条件に、アンプ本体はヴォリューム無しとしました。
ベースへの信号入力カップリングCは 1uF と少なめのフィルムコン、小さい OPT に見合うローカットのつもりです。
(3) OPT、ヒートシンク、電源まわり、エミッタ電流の監視
● 併用するシングル用 OPT:
真空管に比べてコレクタ電圧 Ec が低くコレクタ電流 Ic が大きい Tr が相手なので、一次側のインピーダンスを低く設定します。
また Ec が低いので Ic は目一杯流して出力を確保すべく、OPT の許容電流値を確認します。
できれば OPT を特注したい所ですが、ある程度までなら出力真空管用 OPT を工夫して流用できます。
別ページに示した 2SC4029 タマリントン超三結アンプ試作例および Ebb=30V アンプ試作例では、何種類かの OPT につき下記の低インピーダンス化を実験して応用しました。
◇ 同一 OPT を二個使い、一次並列・二次直列
(巻線比 1/2 、インピーダンス比 1/4・・・PP の場合も適用可、二個以上も可)
◇ SG タップのあるもの:P 端子 -SG 間
(巻線比が 56%なら、インピーダンス比 1/3・・・但しシングルのみ)
◇ SG タップのあるもの:SG -B 端子間
(巻線比が 44%なら、インピーダンス比 1/5・・・PP の場合も適用可)
しかし、一般に適正な通過帯域および適正マッチング条件を同時に満たすことは困難のようであり、試行錯誤のうえ通過帯域を優先することになるでしょう。 また同一 OPT の複数使用の場合には、縦方向への重ね方・・・OPT どうしを密着させた場合のコイルの向きの関係、ある程度の間隙を保った場合・・・および巻きはじめ巻き終わりの反転などによる接続方法によっても音質にかなりの影響があるので、試行錯誤が必要になります。
本アンプでは春日無線変圧器製 54B57 を二個使い、5mm 程度間隔を開けて縦に重ね、一次側 7kΩを単純に並列接続、二次側 16Ωを単純に直列接続としました。 この接続方法にて換算するとインピーダンス比が 875Ω:8Ωとなり、出力10W、一次許容 DC 電流は2倍の max 120mA まで対応できることになります。
● ヒートシンク:大きめの 100x200mm 程度のサイズ、当然自然空冷です。
● 電源トランス:一次 100V 二次 48V0.3A、これをブリッジ整流しました。
● エミッタ電流 Ie の監視:エミッタ回路に挿入の DC NFB 抵抗 Re の両端の電圧、100Ωなら読みを 10倍して mA 相当です。
(4) NFB 併用固定バイアスの抵抗値等の調整
OPT により Ic が制限されることもあるし、エミッタ抵抗 Re の値も NFB 併用固定バイアス・ブリーダ用のコレクタ→ベース間の抵抗 Rcb、ベース→接地間の抵抗 Rbg の値が見当がつかないので、この三者を電源電圧〜コレクタ電圧 Ec を上げながら「手探り」にて求めることにしました。
エミッタ電流抑制用/監視用抵抗 Re の値はオーダーすら判らず、動作原理から考えれば最初は大きく設定して順次減らしていくべきですが特に理由もなく 20Ω を挿入、ブリーダの Rcb/Rbg も適当に設定すると、一発 Ec=30V 程度で問題なく音が出て、ひとまず安心しました。
次に Rcb/Rbg をいろいろ取り替えながら Ec=50V に上げて Ie=60mA 前後で動作させました。 この動作点では許容コレクタ電力の 1/10 です。 パワー on 後に Tr の温度上昇により徐々に Ie が増加する一方、熱容量の大きい電源トランスなどの発熱〜抵抗値の増加〜電圧降下により Ie が抑制されるらしく、若干「うねり」が起きました。
しばらく稼働するとパワー Tr 直上位置にて室温より約 +10C゚温度上昇して熱的に平衡しました。
この状態なら OPT の許容電流に余裕があり Ie を増やせます。
また定電圧電源の併用は必要ないと考えました。
(5) 温度上昇試験および温度補償の調整、出力調整等
次にヘアードライヤにてアンプを加熱して温度安定性を点検しました。
厳密には Tr を加熱した場合の内部抵抗の変化によるベース電位およびエミッタ電位 (Eb/Ee) の変動を点検して DC NFB 用の Re を調整するものと考えます。 実際には Tr・抵抗・ヒートシンクが不均等に加熱され、抵抗の温度係数やヒートシンクの熱容量、熱伝導などの要素も加わり、時間的な遅れも生じます。 しかし実用的には室温から 60゚C 程度までの範囲にて定常状態になった(と思われる)時点にて調整すれば支障はまず無いと判定しました。
まず Re=20Ωの場合、加熱すると Ie が見るみるうちに +50%も増加してビックリしました。 急遽ドライヤを送風に切り替えて冷却、実際は Tr はビクともしない範囲ですが、明らかに補償不足です。
そこで Ie をより大きくエミッタ電位に反映させるべく Re/Rcb/Rbg を回路図に示した値に調整して、室温 =10゚C 環境にて熱平衡時に Ie =80mA に設定しました。 ここで再度、加熱点検すると Eb/Ee の上昇はプラス数%程度に抑えられました。
更に半日のランニング・テストで確認しても Ie は殆ど動かず、まずまずの安定度でした。
この程度の安定度なら、直射日光に晒して動作させなければサーミスタによる安定化は不要かなと、ひとまず勘弁してもらいました。
また L/R チャネル各アンプの電圧を当たると、 DC NFB の効果によるものか半導体とは思えない程よく一致してビックリ、これなら無調整にてプッシュプル・アンプが楽に構成できると思いました。
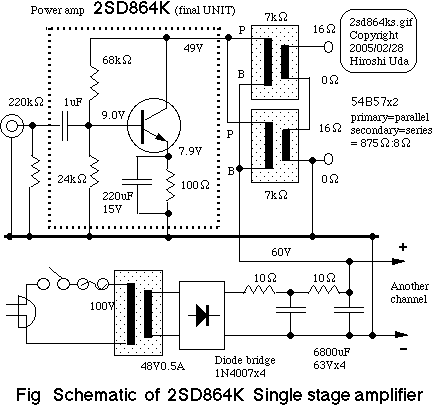
(6) ついでのプッシュプル・アンプ化
シングル・アンプが一応収まったので、例のごとく簡単なプッシュプル・アンプをトライしました。
● 上記のシングル・アンプの片側を1ユニットと看做し、4ユニットを用意、
● 2ユニットを一つの 100x200mm 程度のヒートシンクに取り付け、
● 山水 ST-24 トランスにて入力信号の片側を位相反転し、
● 出力トランスには東栄変成器製 OPT-20P の SG タップ−B 間を利用し、
● 電源トランスを大型化 (二次:48V0.75A) して出力電流を確保しました。
各アンプ・ユニットの Ec を点検すると約 9V=90mA 前後とよく揃っており、DC バランスは調整不要でした。
AC バランスには特に不揃いの要素は見当たらない・・・とモクロミ回路を信用?することにしました。
OPT は フル使用時の半分以下の巻き線部分である SG タップ−B 間を利用したので、有効巻き数(アンペアターン)も半分以下、直流抵抗分も半分以下、流した Ic は OPT の一次許容 DC 電流(max 100mA)の範囲内であり、発熱および磁気飽和には問題ありませんでした。
直ちにスピーカを接続し、信号を入力してランニング・テスト兼レコード鑑賞しながらヒートシンクの温度上昇を点検し、室温 +15度程度に収まることを確認しました。
シャーシの Tr 直下はガランドウ、マッフィン・ファンを取り付けるスペースを確保、夏を越せなければ追加する覚悟・・・でも、まず不要でしょう。
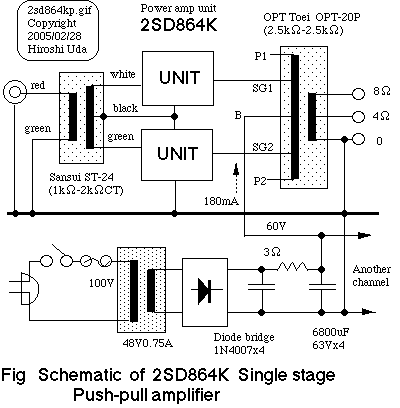
(7) 追加の改造 (2005/04)
シングルおよびプッシュプルの各アンプをしばらく運用してから下記の改造を加えました。 改造部分図は一枚にまとめました。
● バッファ・アンプを追加
シングルおよびプッシュプルの各アンプの前段に小信号 FET のソースフォロワを付け加えました。 ドライブが楽になりゲインが大幅に上がりました。 追加目的は、T型アッテネータ以外の、単なるポテンショメータ式のヴォリューム・ボックスおよび真空管式のカソード・フォロワ一段バッファ・アンプなどの併用による、他アンプとの比較実験などを行う場合の「可用性 (usability)」の確保・・・すなわち利用環境の制約緩和にあります。
シングルの場合にバッファ・アンプから終段へ入力するカップリング・キャパシタ、またプッシュプルの場合に位相反転用トランスへ入力するカップリング・キャパシタは、いずれも 10uF としました。 ソースフォロワ用の FET は 2SK117 の他に 2SK30A-Y を使っても同様に動作しました。
● シングル・アンプの出力トランスの変更実験
フト思い付いて、東栄変成器製 T-1200 を二個使い、一次側は 0〜3kΩ間を並列、二次側は 0Ω〜8Ωを直列にして 750Ω/8Ω相当にて動作させ、十分実用になりました。