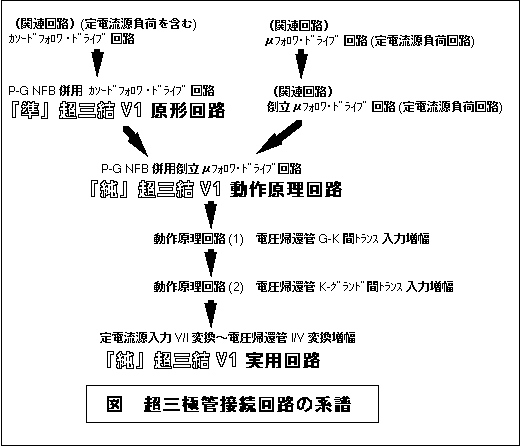
目次
1 いきさつ・・・本文の目的と課題
2 各種の終段ドライブ回路方式と P-G NFB 適用例
3 基本的な終段回路
4 NFB を併用した終段回路の分析
5 超三結 V1 回路の力点
超三結 V1 の回路動作を拙 HP の「考察」では大量のページにてクドクド説明してきましたが、「なんとも難解である」とのご意見を沢山頂戴して、筆者の記述力と表現力の稚拙さも然ることながら、アプローチ方法に問題があり、次第にその本質がハッキリしてきました。
◆クドクド説明・・・
「何10ページなんて不要、10行で説明できるはずだ」とムチャをおっしゃる方もいました。 たしかに10行で簡潔に説明し得ますが、それだけの説明で全てを理解するに必要な予備知識は、その項目だけでも10行ではとても収まらないでしょう。 たとえば古い教科書ではカバーしていない「定電流源」なんていう項目もありますし・・・一般的には相当に困難でしょう。 しかし、整理の必要は感じています。
◆アプローチ方法・・・
どうやら超三結 V1 の動作説明の展開上で、特に最も回路構成部品が少なくてすむ実用回路 (後述) をベースにしたのでは、判りやすく説明することも理解していただくことも困難であり不適当だったのですが、最近もっとわかりやすく説明するステップにて何とか打開できる見通しを得たのです。
結論から言うと、初期段階にて超三結 V1 回路の具体例として P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路をベースラインにすれば、動作説明はもっと円滑に進んだ筈ですね。 この結論に到るまでに筆者はエンエンと遠回りしました。
と言うのも、実装の簡便さを前面に押し出して、超三結 V1 回路動作説明は、むしろ最も難解な P-G NFB 併用 倒立μ フォロワ・ドライブ回路 (後述) 一本のベースラインが確実だと筆者は固執して、それが結局遠回りとなってしまったです。
何故難解な方法を選んだか・・・回路動作が P-G NFB 併用前と併用後では一変してしまう事に関しての一般的理解レベルが期待できない状態では、他の回路との関連を断ち切らないともっと混乱しそうだったからでもありました。
・・・実際に拙 HP にて超三結 V1 回路図をご覧になった方々から、例えば下記のような直ちに返答に窮するコメントを何回となく頂戴し、なかなか本来的な回路構成の動作とネライが理解されずに落ち込みました。
◆既存回路を頼りに「ロフティン・ホワイト回路の変形である」と先方から定義されて、
折角の P-G NFB は一体どうしてくれるんだョ・・・
◆素子の性格上から「P-G 間に信号入力する SRPP ドライブ回路」と言われ、
動作要素は残るから誤りではないが程度・相対的な問題であり、目的外だし
◆伝統的な「カソードフォロワ回路 (プレート接地回路) と類似の回路」との定義でも、
動作要素は残るから誤りではないが程度・相対的な問題であり、目的外だし
気を取り直してこれらの「異なった解釈」の原因を分析してみると P-G NFB への理解と、定電流源 (動作) への理解がキーポイントらしいと判明し、このまま放置しておいても進展しないと考え、筆者にできる対策として「P-G NFB から超三結 V1 回路への橋渡し」を意識した終段の P-G 間入力回路を中心に本文の初版 Version 1 を記述しました。
Version 1 では、超三結 V1 回路を正しく理解しておられる方・・・超三結 V1 の極意は P-G NFB・・・とおっしゃる方達からの、何件かの誤り箇所等についてのご指摘を頂戴して適切に改訂・更新できました。(文中ながら有難うございました。)
その後、前述のように実験を重ね見通しがよくなりました。 今回の Version 2 への書換えに際しては記述内容を見直して発展的内容にすべく心がけて、 Version 1 では SRPP →カソフォロ・ドライブの記述順であったものを、入れ替えてより自然にするなど改善に努めましたが、まだ肝心な事項が抜けていたり(本節のような) 冗長な記述も多いと思っています。
後述しますが、便宜上筆者が命名したものには、超三結 V1 の回路には、動作原理を説明するに都合の良い動作原理回路、および実際に試験・稼働させるに適した実用回路の二種があり、それらの変形として派生した回路・・・実は動作原理回路よりも説明しやすい回路なので筆者が勝手に命名してしまった・・・原形回路もあります。
筆者は便宜上、正式な「回路形式上の名称」の他に「超三結 V1 の分類名称」としても下記のように名称づけしました。 もし回路形式名称にて表現すると長くなり不便であり、別名にすると超三結 V1 系統内での区別が簡便になります。 それらは下記のように二系統、三種類に大別できます。
(1)回路形式名称:P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路
→{英} P-G NFB jointed cathode follower driven circuit
超三結分類名称:準 超三結 V1 回路 →{英} Semi-STC V1 circuit
・・・説明上の都合により(超三結 V1) 原形回路とも称する。 →{英} Original circuit
・・・理解しておくと(2)の理解が大変楽になる、実用例もある回路。
・・・上條氏の解説には現われなかったので「準」がつきます。
(2)回路形式名称:P-G NFB 併用 倒立μ フォロワ・ドライブ回路
→{英} P-G NFB jointed inverted Mu follower driven circuit
超三結分類名称:純 超三結 V1 回路 →{英} (Pure-) STC V1 circuit
・・・上條氏の解説に最初に現われたもので「純」です。
(2.1)これに含まれる回路とその名称 (1) (超三結 V1) 動作原理回路
→{英} Theoretical (STC V1) circuit
・・・下記の(2.2)実用回路に先だって理解を要する中間的回路。
(2.2)これに含まれる回路とその名称 (2) (超三結 V1) 実用回路
→{英} Practical (STC V1) circuit
・・・コスト・パフォーマンスの高い、筆者の試作例に大幅に適用した回路。
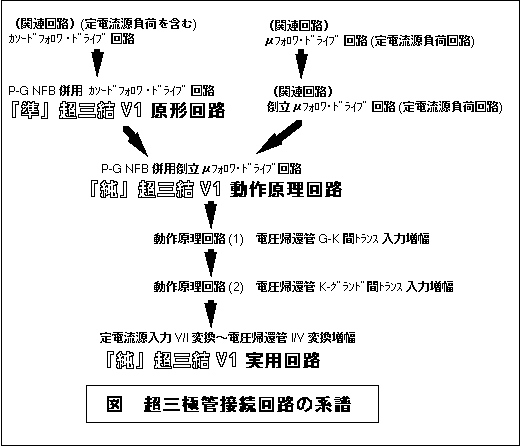
準 超三結 V1 回路=原形回路の試作試験および動作確認等を経るなど、説明方法の模索の末に整理したのが、下記の「説明〜理解ステップ」です。
(1) まず原形回路である準 超三結 V1 回路 にて基本動作を導入・理解してもらい、
(2) 原形回路との関連性を考慮しながら、次のステップである 純 超三結 V1 回路を、
まず動作原理回路として理解して貰い、
(3) つぎに更に複雑な、しかし回路は簡単で実装に適した実用回路を関連性をもって理解して貰う、
・・・このようなステップが、もっとも円滑に説明でき、理解してもらえそうである〜との結論に到り、本文および拙 HP 別文の「動作概説」を大幅に書き直しました。
●電圧帰還管:
オリジネータである上條氏の命名による、終段プレートから P-G NFB を掛ける三極管の名称です。
(1) P-G NFB 併用 カソード・フォロワ・ドライブする三極管のプレートを終段プレートに接続しても、
(2) P-G NFB 併用 SRPP ドライブする上の三極管のプレートを終段プレートに接続しても、
(3) P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブする三極管のプレートを終段プレートに接続しても、
いずれも電圧帰還管の動作となります。 但し (3) の場合は、電圧増幅動作を伴います。
●超三結的効果:
筆者が考案した名称です。 超三結 (V1) または類似の回路構成〜NFB の適用により、終段管が
通常の電力増幅動作から変質して、電圧成分が抑制されること・・・または電流成分が強調されること。
その結果、スピーカを駆動すると超三結 (V1) 固有の個性的な音質に変わることをいいます。
余談ですが、動作原理回路に対しては、筆者の別名にて原理説明回路の定義もあり、また回路的に無理をしていないと言う意味から理想回路と意訳して下さった方も居られました。 それぞれ、名は体を表わしているのですが、この際は混乱を避けて動作原理回路に統一します。
| (1) カソード接地 基本回路 |
(2) グリッド接地 基本回路 |
(3) カソードフォロワ 基本回路 |
(4) (直結)二段 抵抗分割 |
(5) カソードフォロワ ドライブ |
(6) SRPP ドライブ |
(7) μ フォロワ |
(8) 倒立μ フォロワ |
|
| P-G NFB 併用なし |
一般回路 | ☆ 特殊回路 |
プリ出力 など |
ロフティン・ホワイト 回路 |
伝統的回路 低インピ対応 |
伝統的回路 大振幅対応 |
高ゲイン 対応 |
高ゲイン 対応 |
| P-G NFB 併用 |
○伝統的 NFB 回路 |
? | ? | Flat amp or Buffer amp 等 |
◆超三結 V1の 原形回路 |
●五極三極は =(8)超三結 V1実用回路 |
? | ◎超三結 V1 動作原理回路 且つ実用回路 |
(注1)☆カスコード・アンプ、カソード結合位相反転の下半分、高周波リニア・アンプ等。
(注2)○フラット・アンプ等、伝統的回路としてはラーメン帰還と呼ばれた五球スーパー低周波段の簡易 P-G NFB 等。
(注3)◆カソフォロ・ドライブ段に終段プレートから直接 P-G NFB を適用したもの。
超三結 V1 実用回路の変形回路 〜前段にて増幅しない場合〜 に相当する回路だが、
動作説明の順序としては原形回路と位置付けするのが説明〜理解しやすく好都合である。
(注4)●以前、筆者は P-G NFB 併用の三極管〜三極管による SRPP ドライブには初段の定電流性が
ないために別物として扱ったが、本表では再びこの欄に含めている。
(注5)◎P-G NFB 併用 五極管〜三極管 SRPP ドライブ にて、電圧帰還管の内部抵抗が十分に低く、
初段が定電流源動作ならば、P-G NFB 併用倒立μフォロワドライブ回路相当、同一回路である。
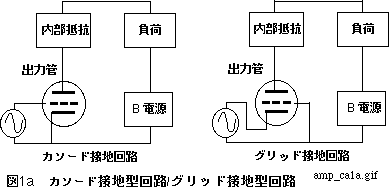
●μ+1 分の NFB が掛かって、
●ゲインは A=μ/(μ+1):=:1、
●内部抵抗は Rp=1/Gm
となる回路です。 もともと内部抵抗を減らす NFB が回路に組み込まれています。
裸のカソードフォロワ回路を変形していくと、グリッド〜プレート間に信号入力することによって、カソードフォロワ回路動作が実現することを「図1b カソードフォロワ回路」に示します。 ここで、入力信号は信号源そのものでも、または信号源の負荷となった受動素子・・・実際には抵抗が最も手軽ですが・・・でも構わない訳です。
そこで、終段のプレートから前段のプレートに直接 P-G NFB を掛けたり、前段の抵抗負荷への B 電源供給を終段のプレートに求めると、変形したカソードフォロワ回路になりうるという事です。 しかし必ずそうなる訳ではありません。 これについては逐次後述します。
また、カソードフォロワ回路を構成することとは、積極的に内部抵抗を減らす回路にすることと同義です。
本回路によるパワーアンプとしては「手作りアンプの会」江口氏による試作例があります。(2001/12 Version 2.1)
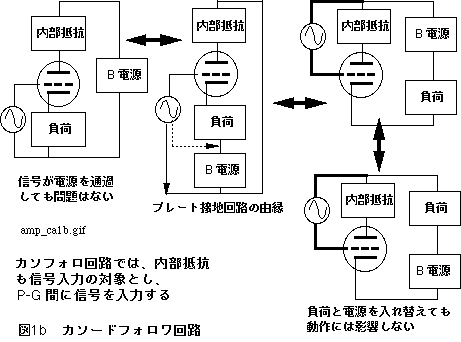
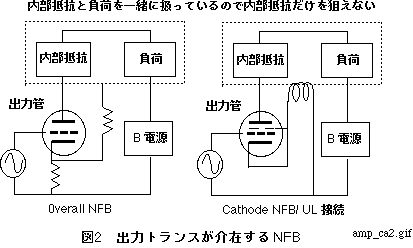
参考までに、伝統的な出力トランスが関係したカソード接地回路ベースの NFB 併用回路をレビューします。
伝統的な NFB 回路では;
(1) 主として出力トランスの二次側または三次巻線から初段に NFB 信号を戻す Overall NFB、
(2) 主として出力トランスの二次側または三次巻線から出力管のカソードに NFB 信号を戻す
局部 NFB の一種である Cathode NFB、
(3) 多極管の場合に限り、出力トランスの一次側からタップまたは別巻線でスクリーングリッドに
局部 NFB を掛けて内部抵抗を減少させた局部 NFB の一種である Ultra linear 回路、
(4) またはこれらを複合して適用した場合、
が殆どでした。 いずれの NFB 方式であっても、出力管内部インピーダンスおよび負荷インピーダンスを区別せず 〜実際には区別できずに、まとめて一括の NFB を掛けていることが判りました。
従ってこれらの回路方式では、出力トランスのインピーダンス込みとなり、終段の内部インピーダンスだけを「狙い撃ち」して低下させることができず、内部インピーダンス低下〜出力インピーダンスの抑制目的には十分適合しない訳です。
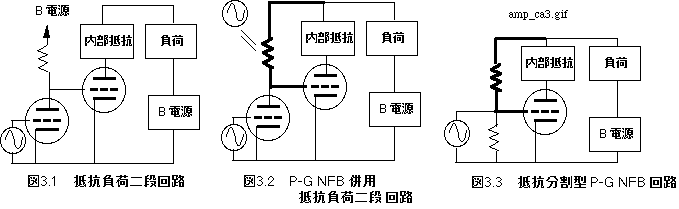
抵抗負荷の直結二段回路はあまり見掛けませんが、彼の有名なロフティン・ホワイト回路がこれに該当します。
●P-G 間入力回路として動作する理由
「図3.2 P-G NFB 併用 抵抗負荷二段回路」を参照してください。
前段負荷抵抗を終段の P-G 間に接続すれば、初段の出力信号を P-G 間に入力するのと同義であり、P-G 間入力回路の一種となることが判明しました。
●NFB の回路構成
終段出力電圧成分、すなわち NFB 信号を、上の抵抗負荷と初段の内部抵抗にて電圧配分して NFB 回路を構成することになります。
「図3.3 抵抗分割型 P-G NFB 回路」を参照してください。
この場合は、単純に終段出力電圧成分を抵抗にて分圧して P-G NFB を構成しています。 五球スーパーラジオの低周波電圧増幅段と出力段のプレート〜プレート間に 1MΩなどを接続した「ラーメン帰還」と呼ばれる伝統的な P-G NFB が、これに該当します。
本回路にて深い NFB を掛けようとすると、グリッドリークよりも少ない抵抗値を選択せざるを得ず、終段の入力インピーダンスが低くなります。 また、NFB 抵抗には直列にカップリング・キャパシタを入れる必要もあり、時定数への配慮が必要です。 NFB 抵抗にて出力の一部を消費するし、前段の出力インピーダンスは下げて且つ振幅を大きくとる必要が生じ、SRPP ドライブ対応が必要となる場合もあります。
本回路によるパワーアンプ試験例としては「手作りアンプの会」田村氏による南例かの「強 NF アンプ」があります。(2001/12 Version 2.1)
抵抗分割型 P-G NFB (ドライブ) 回路は、 NF 型アナログ・イコライザ回路、NF 型トーンコントロールまたはフラット・アンプ等の伝統的な電圧増幅回路ではおなじみです。 これらもカソードフォロワ回路に形態的には類似であることが判明しましたが、分割する抵抗値の比率により、G-K 間入力振幅が大となれば P-G 間入力回路から外れることになります。
●回路の名称
終段のドライブに関する限り「抵抗分割型 P-G NFB ドライブ回路」でしょう。 英語名では「resistor distributed P-G NFB driven circuit」とでも言うのでしょうか。 何方かご教示下さい。
●P-G NFB の併用
「図4.1 カソードフォロワ・ドライブ回路および P-G NFB 併用回路」を参照してください。
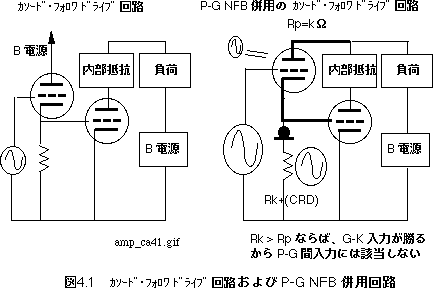
三極管によるカソフォロ・ドライバーのプレートを終段のプレートで吊って・・・B 電源および NFB 信号を同時に供給して P-G NFB を掛けたらどうかと考え、抵抗分割 P-G NFB 類似の回路を動作試験した結果、相当の超三結的効果を得ました。
回路動作は「4.2 抵抗負荷二段回路および抵抗分割型 P-G NFB 回路」にて説明した NFB 信号の分割抵抗を、カソフォロ・ドライブ管の内部抵抗とカソードに挿入した(定電流素子および)負荷抵抗とに置き換えた状態です。
前段の出力振幅は、カソード・フォロワ段のグリッドに入力されるため、前段の出力インピーダンスは高いまま、大振幅を加えることができる反面、抵抗分割型では心配の余地のなかった、カソード・フォロワ段の非直線プレート特性が NFB に反映される可能性が出てきます。(2001/12 Version 2.1)
回路構成としては、超三結V1 回路の電圧帰還管から増幅機能だけを除いた形式になります。 従って信号入力方法の相違を除いて、終段の動作のみに着目する限りでは超三結V1 回路と同じ動作です。
●P-G 間入力回路は成立しない
一般には P-G NFB 効果を得るため、カソフォロの負荷インピーダンスに定電流源を含ませたり、高抵抗とマイナス電源で引く等して、カソフォロ・ドライバの内部インピーダンスよりも大きくとれば、G-K 間入力振幅が遥かに大きくとられ、P-G 間入力回路には該当しません。
●回路の名称
言うまでもなく「P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路」です。 筆者は「準超三 (結)」V1 回路として、また本文の今回改訂 (Version 2) から超三結V1 「原形回路」としても区別し分類しています。 英語名としては「P-G NFB jointed cathode follower driven circuit」となります。
●P-G NFB の回路構成
終段のプレートから上の真空管負荷のプレートに直接接続することにより、動作に必要な DC 電圧、および NFB 信号を直接受け取ることになります。 終段からの出力電圧成分〜 NFB 信号は、上の電圧帰還管と下の電圧増幅管の初段にて電圧配分して NFB 回路を構成します。
●P-G 間入力回路として(も) 動作する場合
SRPP の電圧帰還管のプレートを出力管のプレートに接続すると、終段の P-G 間に信号入力を行うのと同義であり、P-G 間入力回路の効果が出てきます。 ただしこれが適用されるのは同一三極管による SRPP・・・それぞれの内部インピーダンスが近い・・・比が概ね 1:1 の SRPP 構成の場合です。
同一三極管による SRPP の場合、上の電圧帰還管と下の電圧増幅管は、NFB 信号電圧を概ね 1/2 づつ分担するのが精一杯なので、それ以上深い P-G NFB を掛けることはできませんが、弱い超三結的効果が得られます。
回路的には不完全な超三結に相当し、筆者は超三結 V1 回路とは峻別して除外しています。 筆者は以前この回路についても三極出力管何例かについて実験しました。
●回路の名称・・・SRPP 動作の場合
筆者の案では、回路名称を「P-G NFB 併用 SRPP ドライブ回路」、英語では「P-G NFB jointed SRPP driven circuit」と分類・命名して超三結 V1 回路とは峻別し、超三結の分類からは除外するものの、関連回路として位置付けています。
●P-G 間入力回路として動作しない場合
SRPP の素子構成を「五極管〜三極管」とした場合、五極管の負荷および動作点の設定によっては、五極管部が定電流源としての動作・・・高い内部インピーダンスとなることによって、上の三極管〜電圧帰還管の負荷として動作し、終段に対しては P-G 間入力回路ではなくなり G-K 間入力回路に変ります。 五極管の代わりに FET/BJT* とした場合も同様です。
P-G NFB 併用の「五極管〜三極管」による SRPP ドライブ回路の場合では、五極管と電圧帰還管の内部抵抗の比を 10:1 程度にまで設定できるため、殆どの NFB 信号電圧を五極管に背負せることになり、深い NFB を掛けることが可能になります。
「図4 SRPP ドライブ回路とその NFB 併用回路」を参照してください。
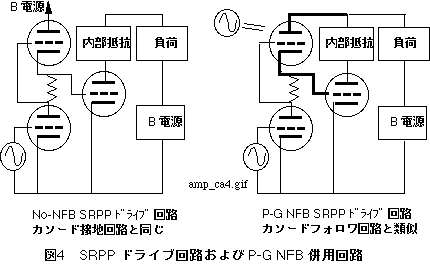
なおこの回路は、上條氏の考案された「超三管接続回路V1」と殆ど同じもので、後述の「4.5 倒立μフォロワ・ドライブ回路およびその P-G NFB 併用回路」にて説明する P-G NFB 併用の場合の回路動作と同等になることが判明しました。
動作の概要は下記の通りです。
◇ 初段を五極管または FET/BJT* とした場合で、更に上の三極管の内部抵抗が低い場合には、
◇初段は、定電流源動作すると同時に入力信号の V/I 変換を兼ねて、電圧帰還管に電流信号を送り込み、
◇電圧帰還管のカソード抵抗にて I/V 変換し、
◇初段の定電流源を負荷とするカソード入力回路= grounded grid 回路によって電圧増幅し、
◇終段の P-G 間に信号入力し、更に初段と電圧帰還管にて終段プレートに現われる
◇出力信号=NFB 信号を電圧配分して P-G NFB に対応しているのですね。
*(注) BJT:バイポーラ (ジャンクション) トランジスタのこと。
●回路の名称・・・倒立μフォロワ・ドライブ回路動作の場合
言うまでもなく次節「4.5 倒立・・・」に述べる「P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路」、「P-G NFB jointed inverted Mu follower driven circuit」となり、筆者が超三結 V1 実用回路とも称するものです。
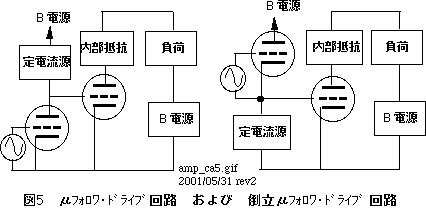
●倒立μフォロワ・ドライブ回路の概要
再び「図5 μフォロワ・ドライブ回路 および 倒立μフォロワ・ドライブ回路」を参照してください。
倒立μフォロワ・ドライブ回路とは、筆者が勝手に命名したμフォロワ・ドライブ 回路の変形です。
それは電圧増幅段の負荷である定電流源を、電圧増幅段のカソードの下に持ってきたもので、これでも増幅動作は損なわれることなく、出力段をしっかりドライブする点では、μフォロワ・ドライブ回路と同様です。
しかし、大変困ったことにホット側〜グランド側で構成される非平衡方式による入力信号を受け入れるには、ライン入力トランスによる隔離 (接地のセパレーション) が必要です。 平衡方式ならライン入力トランスが必然ですから問題になりませんが、実際には非平衡方式〜 RCA ピンジャッグ方式が大勢を占めて主流です。
●倒立μフォロワ・ドライブ回路に P-G NFB を併用すると〜P-G 間入力回路としては動作しない
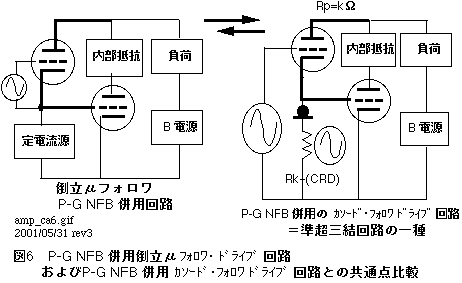
「図6 P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路および・・・」を参照してください。
電圧増幅段のプレートを、B 電源から終段のプレートに接続変更すると、電圧帰還管に直ちに早変わりします。 電圧帰還管にて増幅した信号は、カソード〜接地間に置かれた定電流源を負荷として、終段の G-K 間に入力されます。 負荷には終段の負荷である出力トランスも含まれるものの、インピーダンスの値では定電流源に比べれば無視できるオーダにあると考えられます。
従って、終段は G-K 間入力振幅が大きくなるので、P-G 間入力回路〜カソードフォロワ 類似動作ではなくなります。 また、 P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路とは、信号入力の方法が異なる以外は同一の構成です。
●NFB の回路構成
終段出力電圧成分を、電圧帰還管と定電流源にて電圧配分して NFB 回路を構成しており、前述の P-G NFB 併用 カソードフォロワ・ドライブ回路とは、信号入力の方法が異なり、電圧帰還管が増幅機能を持っていること以外では、P-G NFB に関する限り同じ構成と動作になります。
P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路は、実は、上條氏の考案された超三結 V1 動作原理回路と殆ど同じものです。 上條氏の回路では終段入力を電圧帰還管のカソードに挿入した抵抗の上から入力しています。 この点から入力することにより、定電流源の動作に対して終段管のグリッド電流〜インピーダンス低下〜からの影響の防止・回避策となるもの考えられます。
従って、前掲「4.4 SRPP ドライブ回路およびその P-G NFB 併用回路」にて記述したとおり、P-G NFB を掛けた SRPP ドライブ回路であっても、初段が定電流性をもつ五極管または FET/BJT の場合で、電圧増幅段の内部抵抗が十分に低く、初段が V/I 変換が主動作となる場合は超三結 V1 実用回路に接近する、またはそのものになる・・・という動作点の設定に関係することも判ってきました。
超三結 V1 実用回路の場合は、前掲の五極管〜三極管による SRPP ドライブ回路のように見えますが、動作原理回路での五極管または FET/BJT が単なる定電流源素子として動作するのとは異なります。 すなわち五極管または FET/BJT は
(1) 制御グリッドまたは ゲート/ベースに加えられた入力信号により電流変調 (V/I 変換)として動作して
信号電流を発生し、電圧帰還管はカソード抵抗で I/V 変換し増幅し、・・・ここが全く異なる部分です。
(2) 同時に電圧帰還管とで P-G NFB の信号電圧の分圧抵抗として動作し、殆どを背負い・・・これは共通です。
(3) 同時に適正な動作 DC 電圧を電圧帰還管には多く、自体は少なく分けあって動作します。・・・これも共通です。
・・・と、このように大変込み入った多重機能動作をしています。 さらに詳しい説明は、拙ホームページに記載の <<<超三結アンプの実装法考察>>>構成・動作原理:(前半) をご参照ください。
補足になりますが、前記本文 「4.3 カソフォロ・ドライブ回路およびその P-G NFB 併用回路」に示した回路と超三結 V1 動作原理回路 {P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路}との共通性が、「図6 P-G NFB 併用倒立μフォロワ・ドライブ回路および・・・」からも確認できます。
●回路の名称
補足の余地はありません。
(1) 電圧増幅機能の適用の有無。
前者はカソードフォロワ動作で、グリッド入力信号を忠実にカソードに反映する機能であり、電圧増幅は行わない。 後者は電圧増幅を行っている。 この差がどのように終段入力信号の波形の差となるか、を追及する必要があります。
(2) P-G NFB の信号電圧配分素子としての動作。
設定される動作点、およびカソードフォロワの負荷または定電流源負荷が同一の諸元ならば、NFB の動作についても同一と看做せます。 しかし、実際の実用回路では、初段との関係等によって電圧帰還管を、たとえば 1mA 以下などの、かなりの小電流モードにて動作させているため、一般に使われる単純なカソードフォロワ動作とはかなり異なります。
ここにいたって、超三結 V1 回路の特徴、力点を (1) P-G NFB による終段の増幅率μの抑制効果に置くのか、または (2) P-G NFB に三極管の非直線性を混入させる事に置くのか、の課題に立ち返る訳です。
上條氏の初期の記事では後者が主体になっていたように記憶しています。
一方、筆者の考え方は超三結 V1 回路の特徴は、あくまでも前者 (1) の出力電圧振幅を抑制する回路特性に重きを置くものとしています。 その理由は、筆者の考えでは、電圧振幅を抑制しない、いわゆる「電圧アンプ」との対比という観点に立って超三結 V1 回路を位置付けようとしているからです。
類似の性格を持つ V1 回路以外の超三結回路についてもほぼ同様な考え方が
適用されると考えられます。 また超三結以外の類似の性格を持つ回路のアンプとしては、「手作りアンプの会」の江口氏が研究・実験されている「カソードフォロワ終段アンプ」、同じく「手作りアンプの会」の田村氏が研究・実験されている、抵抗による P-G NFB にて構成した「強 NF 回路によるアンプ」が含まれるものと考えます。(2001/12 Version 2.1)