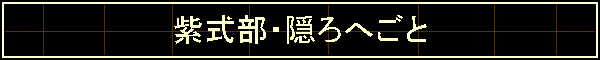藤原為時の二女(?)。母は藤原為信女。
天禄元(970)年〜天元元(978)年ころの出生とされているが確証はない。若年時の足跡はほとんど不明で、長徳元(996)年、27歳ころに受領の父藤原為時に従って越前国(福井県武生市)に下ったこと、翌年帰京して藤原宣孝と結婚し一女賢子を生んだこと、長保三(1001)年に夫と死別したことなどが知られるだけである。このころ「源氏物語」を書き始めたと思われ、寛弘二(1005)年ころ、その才能を買った藤原道長の求めに応じて中宮藤原彰子の後宮に出仕した。彰子の漢籍の家庭教師、および源氏物語の執筆が主な仕事であったらしい。
長和三(1014)年を境に文献に現れなくなること、父為時の出家などの理由から、40歳代で死没したと見られている。
ここに着目!
 | 空白の少女時代と恋の相手 |
「源氏物語」より、紫式部自身の肉声がはっきり読み取れるのが「紫式部日記」や「紫式部集」である。幼いころ、父が弟(兄ともいう)惟規に漢籍を教えているのを横で見ていた式部は、惟規よりうまく読んでしまった。それで、父に「男でないのが残念だ」と言われたというエピソードが日記に載っている。そのほか、家集には幼友達と交わしたらしい歌があることから、従姉妹(平維将女という説がある)と仲が良かったのではないかと言われている。成人するまでの式部に関しては、このように断片的な話をつなげていくしかない。
その一つとして、父為時の失職がある。寛和二(986)年、花山天皇が半ば騙されて出家した事件で、為時は式部大丞の職を退いた。花山天皇の側近であった藤原義懐と姻戚関係だったことから、おそらく花山天皇寄りの立場にいたと思われる為時は、その後長く職に就くことができなかった。紫式部の家は典型的な受領階級であって、為時も早くから受領になるため奔走していたはずである。失職して10年目になる年、やっと下国(4等級ある国の格付けで最低の国)淡路国守に決まった。為時がそれを不服として、一条天皇に漢詩を奉ったことは有名である。
この父の失職時代が、式部の生涯の中で最もわからない時期である。彼女はどんな風に生きていたのか? 史料だけでは不明というほかないので、ある程度類推を入れてみるのもよいかもしれない。
式部は若いころ、出仕したという説がある。具平親王というのが出仕した先ではないかという。親王は式部には又従兄に当たり、後中書王と呼ばれた村上天皇の皇子である。親王の娘の隆姫は、道長の一男頼通の室であるから、道長にも認められた人であったらしい。日記の中で式部は、隆姫たちの縁談のことを道長に相談されたが、親王には屈折した思いがあるという意味のことを述べている。以前親王の邸に出仕して、しかも具平親王との間に恋愛感情でもあったということも考えられなくはない。親王は康保元(964)年生まれで式部より6〜14歳年上だったことになる。また、漢詩や和歌に秀でた親王は、学者の為時、式部の伯父で歌人の為頼とも非常に親しかった。まったく荒唐無稽とも言えない想像である。
ただ、具平親王とは身分の隔たりが大きい。紫式部のような内省的な人は、高貴な男に対しては身の程を考えて引いてしまい、恋にのめり込むことはなかったのではないか。出仕後、道長と関係があったかどうかは古来問題になっていることだが、たとえ道長が式部の局を訪れることがあっても、それを以て式部が道長に夢中になっていたとは、考えにくい。
式部が身分の違いを気に懸ける必要のない男と言えば、さしづめ同じ受領階級の出身であろう。式部は出仕するまで、曾祖父兼輔の建てた堤邸(現在の廬山寺周辺と言われている)に住んでいたと考えられるが、そこには伯父の為頼や為長も同居していたらしい。受領になれば地方暮らしだが、京に帰ってきたときは堤邸に住む。伯父たちにはそれぞれ数人ずつ息子たちがいた。式部は同じ年ごろの従兄弟たちと顔突き合わせて暮らしていたのかもしれない。その中の誰かと、あるいは夕霧と雲居雁のように恋をしたということはあり得る。ただ、従兄弟たちは為頼や式部自身と違って、あまり歌才はなかったらしく、家集はもとより歌人だという記録もない。式部の相手としてかろうじて可能性があるのは、藤原通経という従兄である。この人は、母方の伯父に源為憲という著名な学者がいるからである。さらに言えば、長保元(999)年、道長のもとへ越後守藤原道経という人物が訪れて志(受領の贈る進物)を道長に渡している。これが通経のことだとすれば、長徳元(996)年ころ、通経は越後に受領として下ったことになる。そのことと、式部の越前行きが何か関係があるかもしれない。従来、夫となった藤原宣孝としか紫式部は恋愛をしていないように言われているが、その方がよほど不自然である。真実は新たな史料の発見のない限りわからないが、式部の若いころの恋の相手は、案外近くにいたのではないだろうか。 |