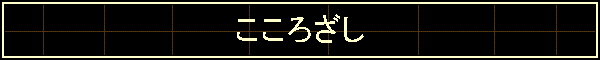彰考館本『伊勢大輔集』・群書類従本『伊勢大輔集』・国歌大観本『伊勢大輔集』
紫式部きよみづに籠りたりしに、参りあひて、院の御れうに、もろともに
御あかし奉りしを見て、樒の葉にかきておこせたりし
9 心ざし 君にかかぐる 燈(ともし)火の おなじ光に あふがうれしき
かへし
10 古(いにしへ)の 契りもうれし 君がため おなじ光に 影をならべて
松に雪のこほりたりしにつけて、おなじ人
11 奥山の 松ばにこほる 雪よりも 我が身よにふる 程ぞはかなき
かへし
12 消えやすき 露の命に くらぶれば げにとどこほる 松の雪かな
【通釈】
紫式部が清水寺に参籠していたときに、わたしが(伊勢大輔)が参籠しにきて
たまたま会ったので、上東門院の御料にと、一緒に御燈火を奉納したのを
見て、後で樒の葉に付けた紙に書いてよこした歌
同じ思いを抱いて、上東門院のために同じ御燈火を奉り、あなたに逢って一緒に
上東門院の快復を祈願できたのはうれしいことです。
返事
前世からの縁があったことだとうれしく思います。上東門院のために、同じ御燈火の
光で二人影を並べてご快癒を祈ることができたのは。
松に雪が凍りついたものに付けて、同じ人がよこした歌
人里離れた、深山に生える松の葉の上に氷る雪はやがて消えるものです。
ですがその雪よりも、わたしがこの世に生きている時間は、はかないものです。
返事
簡単に消えてしまう露のような命に比べれば、なるほど、雪は松の葉の上に
留まって、しばらくの間は凍っていることですね。
【語釈】
●きよみづ……京都市東山句清水一丁目、音羽山を背にした北法相宗本山清水寺。
●きよみづに籠りたりし……長和3(1014)年正月、皇太后宮彰子は病気であった。ここはそのときに紫式部が主の快復を願って清水寺に参ったのだと思われる。
●しきみ……モクレン科の常緑高木。仏事に用いられる。実は有毒。
●君にかかぐる……燈火を奉る意と、燈火の灯心をかきたてる意を懸ける。中宮彰子の健康息災を祈願して奉納する。
●奥山の松葉にこほる雪……人里離れた深山に生える松の葉の上に氷る雪。
●世にふるほど……この世に生きている期間。「降る」と「経る」を懸ける。
●はかなき……主観的な悲しいという気持ちを表すのが「かなしき」とすれば、「はかなき」は客観的な判断に基づく概念的な悲観の感情。
●とどこほる……雪が松の葉に「とどこほる」と「氷る」を懸ける。
【参考】
桂宮本『伊勢大輔集』
「とう式部、きよみづにまいりあひて、御前のおほんれうにみあかしたてまつりつるをきゝて、しきみの葉にかかす
心ざし 君にかかぐる ともしびの おなじ光に あふがうれしさ
かへし
世々をふる ちぎりもうれし 君がため ともす光に 影をならべて
おなじ人、まつの雪につけて、
おく山の まつ葉にかかる 雪よりも 我身世にふる ほどぞかなしき」
『新千載集』巻九、釈教、933
「清水に籠りたりけるに、伊勢大輔参りあひて、もろともに御燈明(みあかし)奉りて、しきみの葉に書きつけて、つかはしける
心ざし 君にかかぐる ともし火の おなじ光に あふがうれしき」
『続後撰集』巻八、冬、513
「松の枝に、雪の凍れるを折りて、人のもとに遣はすとて
奥山の 松葉にこほる 雪よりも わが身世に経る ほどぞ悲しき」
|